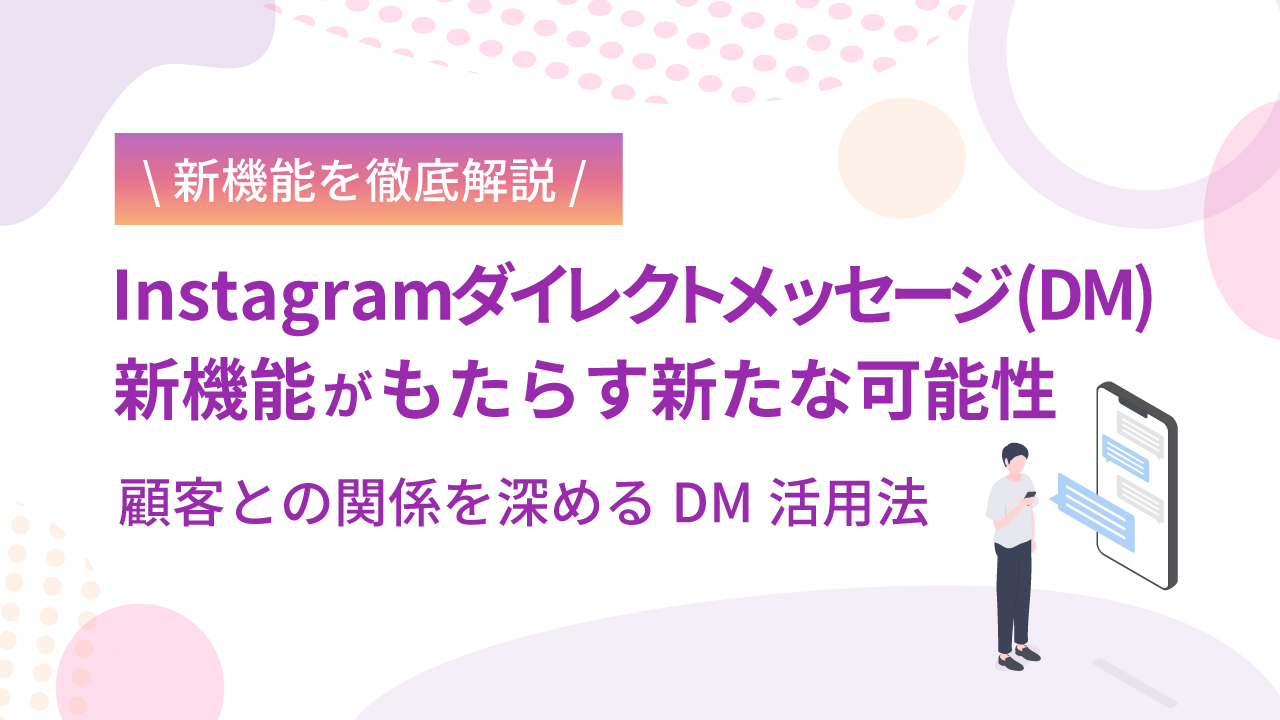2025.7.28
Xでフォロワーの心をつかむ!共感投稿の作り方と企業がやるべき発信とは?
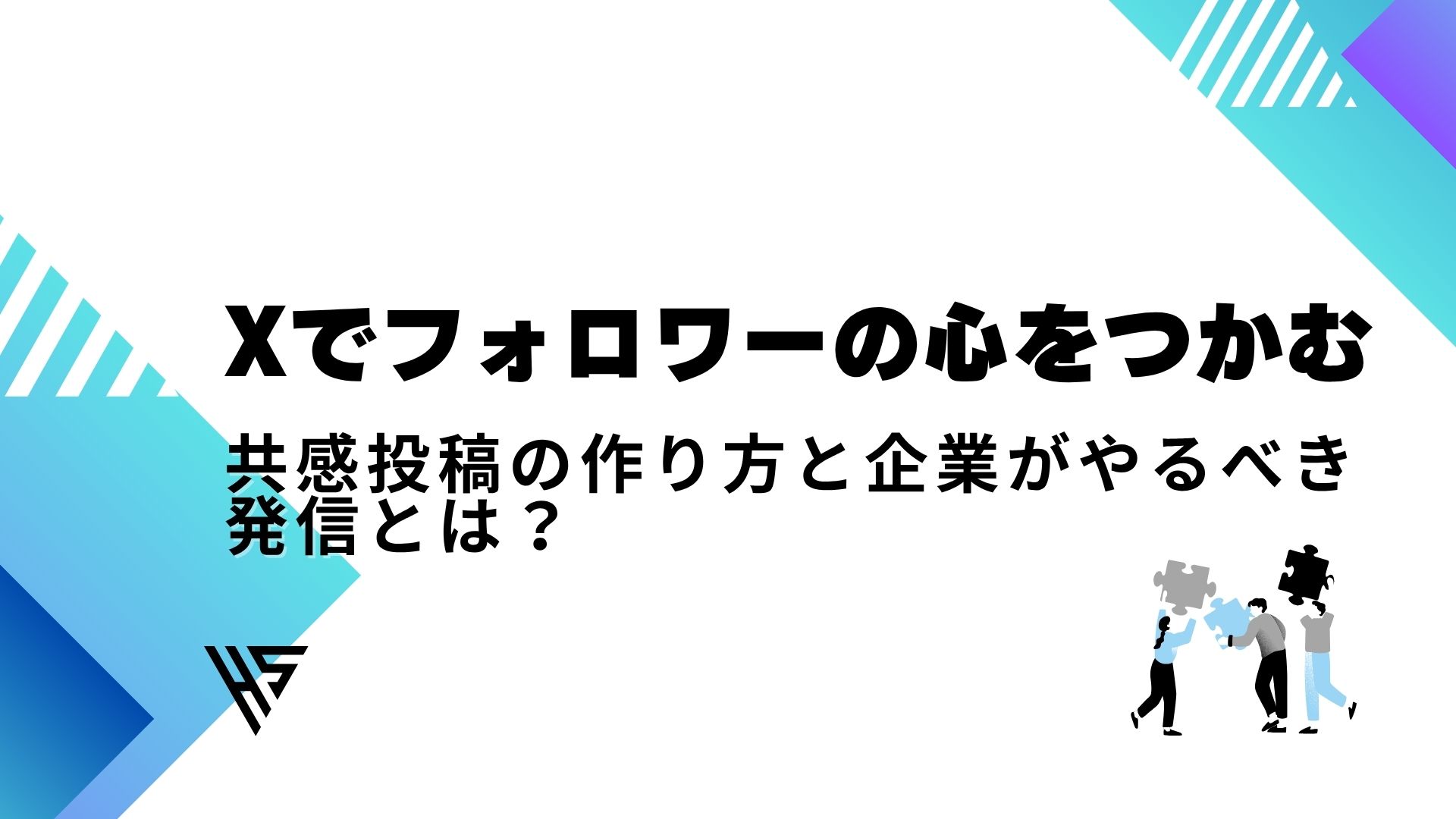
X(旧Twitter)を企業アカウントで運用していると、こんな悩みを抱えていませんか?
「一生懸命キャンペーン情報やサービスを投稿しているのに、全然“いいね”がつかない」
「フォロワー数は増えても、投稿にリアクションしてくれる人がほとんどいない」
「インプレッションはあるのに、何も起きない…」
それ、もしかすると“宣伝一辺倒”な投稿になっているのかもしれません。
いま企業のSNS運用に求められているのは、ただの情報発信ではなく「共感」を生むコンテンツです。
本記事では、
・フォロワーの心に届く“共感投稿”とは何か?
・バズを狙わず、安定的な信頼とエンゲージメントを築くには?
・実際に共感で成果を上げている企業の事例
などを紹介しながら、SNS運用代行ならではの「共感設計」のポイントを解説していきます。
目次
1. なぜ“共感投稿”が企業X運用に求められるのか?

企業のX(旧Twitter)運用でありがちなのが、サービス紹介やキャンペーン情報ばかりの“お知らせ型”投稿。
もちろん、それ自体が悪いわけではありません。ですがそれだけでは、フォロワーの心を動かすことはできません。
いまXの中で求められているのは、「情報」よりも「感情」に触れる発信です。
たとえば、
・社員がふと感じたこと
・プロジェクトの裏話
・商品開発の裏側やちょっとした失敗談
こうした投稿は、企業というより“人”の発信に見え、親近感が湧きやすくなります。
フォロワーにとってXは、“感情をシェアする場所”。
その空気感の中で「企業っぽさ全開」の投稿ばかりが並んでいると、どうしても浮いてしまうんです。
共感される投稿には「わかる!」「その気持ち、知ってる!」という読者のリアクションがつきます。
この共感の蓄積こそが、企業アカウントの“信頼の資産”となり、
長期的なエンゲージメントにつながっていくのです。
2. “共感される投稿”の特徴とは?

共感される投稿には、いくつかの“パターン”があります。
企業アカウントであっても、「人」を感じる発信ができれば、フォロワーの心に届くのです。
ここでは、実際に共感を生みやすい投稿の特徴を紹介します。
① 日常のリアルが伝わる“素の投稿”
たとえば、「今日のオフィスランチ」といった何気ない一枚や、
「月曜の朝はちょっとテンション低めです…」というつぶやき。
こうした“なんてことない発信”に、意外と「いいね」が集まります。
なぜなら、フォロワーが“あなたと同じ”と感じられるから。
BtoB企業であっても「中の人の素顔」が見える投稿は、好感を呼びやすいです。
② “あるあるネタ”や共通体験のシェア
「月末の経理処理、Excelとの戦い…」
「全員リモートの日に限って急な来客が…!」
このように、誰もが一度は経験したことがあるようなシーンは、共感の宝庫。
笑いや“うんうん”の共感が得られるため、リプライもつきやすく、
Xのエンゲージメント向上にも貢献します。
③ 少しの“自己開示”で距離を縮める
フォロワーが「応援したくなるアカウント」には、
ほんの少しの“個人的な要素”が含まれています。
・新人担当者が初めてX投稿を担当しました
・今年入社したスタッフが企画したキャンペーンです
・この写真は商品企画チームの〇〇さんが撮影しました
こうした自己開示は、「中の人」がいるという実感につながり、
企業=無機質、というイメージを打ち消す効果があります。
④ 感情が動いた瞬間を丁寧に切り取る
単なる報告や結果だけでなく、そこに至るまでの“気持ち”も共有することが大切です。
NG:「本日、展示会に出展しました」
OK:「展示会に向けて2ヶ月準備してきました!朝は不安で手が震えたけど…無事終了!」
このように、感情の流れを一緒に追える投稿は、フォロワーに「物語」を感じさせ、
“ただの実績”よりも深い共感を呼びます。
このように、「人間らしさ」や「感情」がにじむ投稿は、企業アカウントでも強い共感を生み出します。
次章では、こうした共感を“どうやって見つけるか?”のヒントを掘り下げていきましょう!
3. 共感を生む“切り口”の見つけ方

企業アカウントにとって最大の悩みの一つが「ネタがない」問題。
でも実は、共感されるネタは“意外と社内に転がっている”んです。
ここでは、共感投稿に活かせる切り口を5つ紹介します。
これをもとに、明日からの発信にもすぐ取り入れられるはずです。
① 社員の声・人柄が見える投稿
新人スタッフのつぶやき、ベテラン社員のこだわり、ちょっとした本音トーク。
「どんな人が働いているのか?」が見えると、企業への親近感はぐっと増します。
例:
「新卒2年目の〇〇です!はじめて営業先で褒めてもらえて泣きそうでした…!」
② オフィスの“ちょっとした日常”
季節感のあるデスクの様子、会議中の裏側、休憩中のホワイトボード落書き…。
こうした日常こそ、共感のタネになります。
例:
「会議室の空調が壊れて、全員うちわ持参でのミーティング🤣」
③ “しくじり”や失敗談の共有
完璧じゃない姿にこそ、人は共感します。
企業アカウントでも、ちょっとした“やらかし”を共有してみましょう。
例:
「投稿予約したと思ったら下書き保存だった件…。担当者しばらく立ち直れませんでした。」
④ 社内イベントや行事の裏話
歓迎会、表彰式、誕生日祝いなどの行事を“ありのまま”で出すと、あたたかさが伝わります。
例:
「誕生日ケーキを用意したけど、冷蔵庫に入れ忘れて若干溶けてた事件🍰(でも喜んでもらえました)」
⑤ “あるある”を自社目線で切り取る
業界あるある、部署内の文化、朝礼の定番など、
自社の中で普通になっていることが、外の人から見ると面白く映ります。
例:
「うちの朝礼、なぜか毎週“今日のおすすめコンビニ飯”が紹介されます。」
こうした“共感の切り口”を日々ストックしておくと、
「ネタがない…」という状態を脱することができます。
とくにSNS運用代行を行っている場合は、
クライアントから“人の気配がする素材”をヒアリングすることで、
差別化されたコンテンツ設計ができるようになりますよ。
4. 共感で伸ばしている企業事例

実際にXで共感型の投稿を武器にして、フォロワーとの信頼関係を築いている企業アカウントがあります。ここでは、戦略的に“人”を見せることで成果を上げている2つの事例を紹介します。
事例1|株式会社トリドールホールディングス(丸亀製麺)
丸亀製麺のXアカウントは、商品の紹介だけにとどまらず、店舗スタッフの裏話や開発エピソードを積極的に発信しています。
例:「今日も天ぷら職人の〇〇さんがサクサクに仕上げてくれました!」
こうした“人”の見える発信は、食の安心感や親しみにつながっており、コメント欄にも「〇〇店の天ぷら、本当においしい!」といった共感の声が多数集まっています。
さらに、時には「ちょっとした失敗談」や「開発裏の奮闘」も織り交ぜ、フォロワーとの距離感をうまく縮めています。
丸亀製麺 Xアカウント→https://x.com/UdonMarugame
事例2|株式会社大垣書店(書店運営)
大垣書店のXでは、店舗スタッフが「好きな本」「今日の気分」「気になる展示物」などを自由に投稿しており、商業的な売り込みではなく“読書のある日常”を自然体で届けています。
例:「朝からこの一冊を読んでいて、気持ちが少し前向きになれました。」
売り込み要素をほとんど感じさせない発信にもかかわらず、多くの読者が反応し、「その本気になってました」「うちの店舗にもありますか?」といったやりとりが生まれています。
株式会社大垣書店 Xアカウント→https://x.com/azabudai_ogaki
このように、企業の立場を前面に出すよりも、担当者自身の気持ちや感情を織り交ぜることで、「人の声」として届いているのが特徴です。
共感型の投稿は、拡散力よりも“じわじわとした信頼”を積み上げるもの。
その分、ファンになったフォロワーは長く関係を保ちやすく、結果としてブランドの支持にもつながります。
次章では、この共感型運用をSNS運用代行の強みにどう活かせるかをまとめていきます。
5. SNS運用代行こそ「共感設計」で差がつく

SNS運用代行と聞くと、多くのクライアントは「定期投稿してくれる」「トレンドを反映してくれる」といった表面的な運用を想像します。
しかし本当に成果につながる運用とは、投稿の“設計思想”に共感や信頼の視点が組み込まれていることです。
特にXでは、投稿文のちょっとした言い回しやタイミング、ビジュアルの使い方ひとつで、受け取られ方が大きく変わります。
だからこそ、SNS運用代行としては次のような「共感設計の視点」を提供できると、他社との差別化にもつながります。
1. 投稿に“人の気配”を取り入れる企画力
商品の紹介だけでなく、「誰が」「どんな想いで」関わっているかを軸にコンテンツを設計します。
2. 共感を生む素材のヒアリング設計
社内のストーリー・スタッフの声・日常の風景など、共感を生むネタを引き出すためのヒアリング項目を整備し、運用に活かします。
3. 代行ではなく“共に発信する”関係構築
一方的な投稿代行ではなく、企業の中にある温度感や人柄をどう発信に反映させるかを考える“伴走型”の支援を重視します。
バズを狙う派手な運用ではなく、フォロワーに「この企業、なんか好きだな」と思ってもらえる関係性づくりこそが、X運用で成果を出す鍵。
そしてそれは、共感を軸とした投稿設計があってこそ実現できます。
「何を伝えるか」よりも「どう伝えるか」。
共感を設計できる運用代行として、クライアントに選ばれる立場を築いていきましょう。
まとめ|共感は“設計”できる。だからこそ成果につながる
企業アカウントがXで成果を出すには、
情報や数字だけではなく、“人”の感情やリアルな日常を届けることが大切です。
単なる宣伝ではなく、
「ちょっとしたつぶやき」や「人の気配がにじむ投稿」が、
フォロワーにとっては“共感”のきっかけになります。
共感される投稿には、いくつかの共通点があります。
・感情が動くエピソード
・日常のリアルな描写
・ほんの少しの自己開示
・しくじりや“あるある”の共有
そして、そのすべては「意識して設計できるもの」です。
SNS運用代行を提供する立場であれば、
投稿ネタの発掘から、発信のトーン設計、共感を引き出す視点の提案まで。
“ただの運用”に留まらない、ひとつ上のサービスとして展開することが可能です。
数字より“人”を集める企業運用術──
その中心にあるのは、共感の設計力。
これからの企業X運用において、もっとも注目すべき視点の一つです。