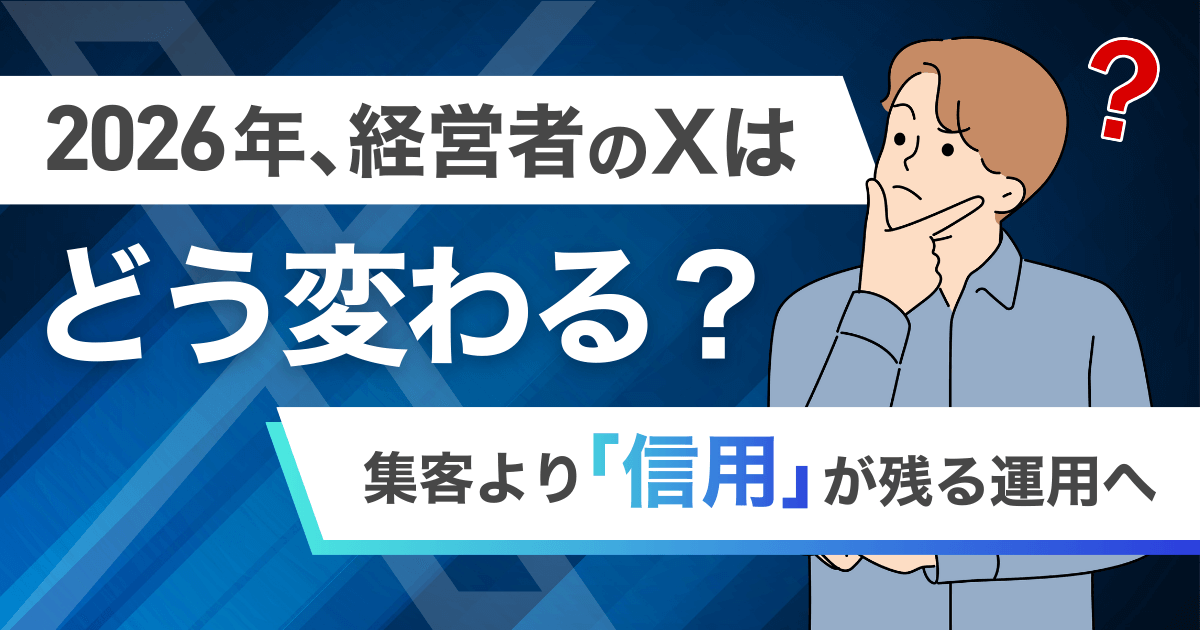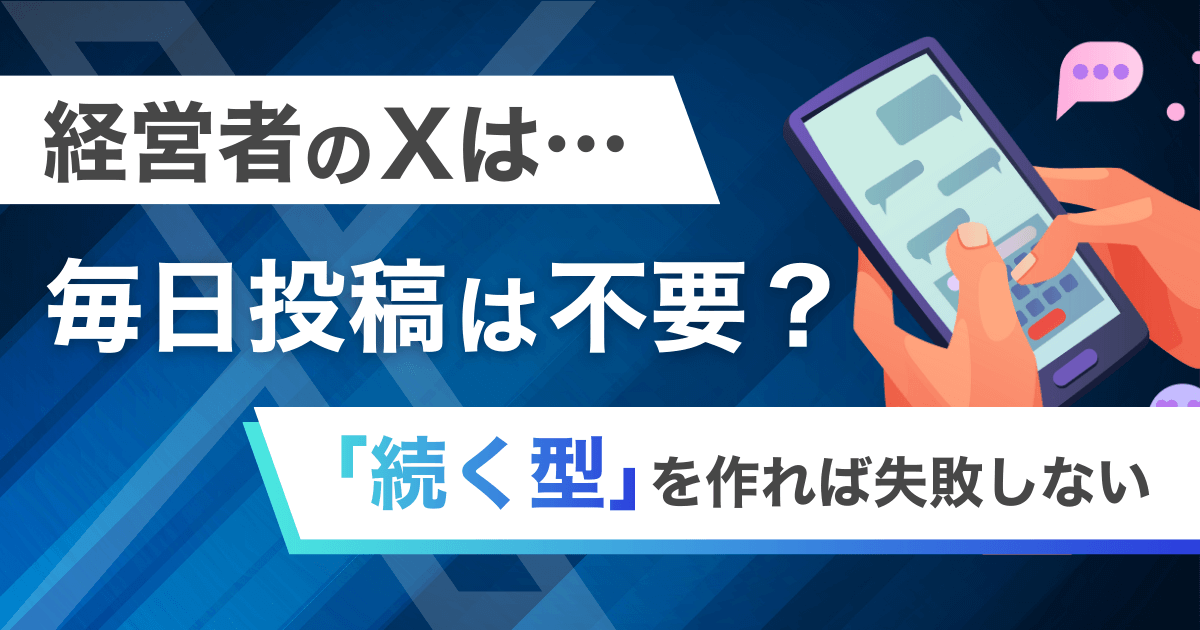2025.7.18
拡散より“共感”を選ぶ時代|企業アカウントがバズを追わない理由

SNSマーケティングにおいて、「バズらせる」ことは正解なのでしょうか?
もちろん、拡散力のある投稿は一時的な注目を集め、インプレッションやフォロワー数の増加につながることもあります。しかし、すべての企業にとって“バズ”は本当に必要でしょうか。
近年、多くの企業アカウントが“バズ狙い”から距離を置き、あえて地に足のついた「共感」を軸にした運用へとシフトしています。
本記事では、企業アカウントがなぜ「拡散よりも共感」を重視するようになったのか、その背景と理由を深掘りしながら、“バズりすぎない戦略”がもたらす本当の成果について解説します。SNS運用代行や戦略設計を検討している企業担当者の方にとって、信頼につながるSNS活用のヒントとなるはずです。
目次
1章:バズ=成功ではない?企業アカウントが抱える“違和感”とは

企業アカウントのSNS運用において、“バズる”ことが一つの成功指標のように扱われてきた時期がありました。派手な投稿が一夜にして拡散され、「いいね」やリツイート、フォロワーが急増する現象は、担当者にとっても上司への説明材料として魅力的に映ります。
しかし、そんな“バズ体験”を経た企業の中には、ある種の違和感を覚えるケースも増えてきました。
たとえば──
・一時的に注目されたが、顧客や見込み客とは関係ない層の反応ばかりだった
・炎上ギリギリを狙った投稿が社内で問題視された
・フォロワーは増えたが、継続的なエンゲージメントや売上には結びつかなかった
こうした事例は決して珍しくありません。むしろ「バズったあと」が大変だったという声も聞かれるようになっています。
企業のSNSは、単なる拡散装置ではなく、“ブランドとの関係性を築く場”として機能すべきです。そのため、瞬間的な盛り上がりよりも「共感」「信頼」「安心感」といった“積み重ね型”の価値が重視されはじめているのです。
2章:なぜ“共感重視”の運用が増えているのか?

企業がSNSを活用する目的は、「話題になること」ではなく、「関係性を築くこと」にあります。
昨今、“バズ”ではなく“共感”を軸に運用方針を切り替える企業が増えている背景には、いくつかの大きな変化が関係しています。
1. SNSの目的が「広報」から「関係性構築」へ変化した
かつてのSNS運用は、“会社の情報を伝える場”という一方通行型の広報が主流でした。
しかし現在では、SNSは企業と生活者の間に“対話”や“感情の共有”が生まれる場へと変化しています。
フォロワーに「自分ごと」として感じてもらえる投稿こそが、真のエンゲージメントを生み、ブランド理解やファン化につながっていきます。
その中核にあるのが「共感」です。
2. バズの“数字”より、共感の“信頼”が重視されるようになった
「インプレッション10万」や「エンゲージメント率5%」などの数値指標は分かりやすく、報告資料には向いています。
しかし、SNS運用の本質は「誰とつながっているか」「どんな関係性が築けているか」です。
たとえば、少数でも“自社の価値観に共感してくれる人”が定期的に投稿に反応し、ブランドに好意的なイメージを抱いてくれている状態こそ、SNSが企業にとって真に価値を発揮している状態です。
この“静かなエンゲージメント”が、商談やリピーター、口コミといった本質的な成果に直結していくのです。
3. 炎上リスクや“ノイズの多さ”に慎重になる企業が増えている
拡散を狙った投稿は、思わぬ角度からの批判や炎上リスクをはらみやすくなります。
バズと炎上は紙一重であり、拡散によって本来の意図がねじ曲げられて届いてしまう可能性もあるのが現実です。
こうした背景から、「誰に届けるか」を明確にし、その人にちゃんと届く“共感型コンテンツ”を丁寧に作る姿勢へとシフトしている企業が増えているのです。
3章:共感投稿とは?“ちょうどいい距離感”をつくるコツ

「共感を生む投稿をしましょう」と言われても、ただ“いい話”や“感動系”を投稿すればいいというわけではありません。
企業アカウントが意識すべきは、ユーザーとの“ちょうどいい距離感”を保ちながら、共感ポイントを丁寧に設計することです。
ここでは、共感投稿を構成する代表的な要素と、それぞれのコツを紹介します。
✅1. 「人」を感じさせる投稿
企業アカウントでも、中の人の視点や現場の空気感が伝わる投稿は共感されやすいです。
例:
・社員の何気ない日常(ちょっとした笑い話や失敗談)
・お客様対応の裏話(こんな想いで接しています、など)
・商品が生まれたストーリー(開発裏のエピソードや試行錯誤)
こうした「人の体温が伝わる話」は、ブランドを“人間らしい存在”として認識してもらうきっかけになります。
✅2. 「読者の気持ち」に寄り添う切り口
企業目線の一方的な投稿ではなく、ユーザーの悩みや日常を前提にした発信は強い共感を得られます。
例:
・「忙しい朝、もう◯◯で悩まない」→日常の困りごとに寄り添う
・「“やる気が出ない日”にも、〇〇を選んでほしい理由」→気分に共感しながら商品訴求
キーワードは“共感の一歩手前の共通点”を探すこと。ユーザーが「わかる〜」「自分にもある」と感じられるトピックを扱いましょう。
✅3. 言い過ぎない・押しつけない
共感投稿では、押し売り感を出さないことがとても重要です。
あくまで「こういう考えもありますよ」「こんなふうに使ってもらえたら嬉しいです」と、語りかけるようなトーンが理想的です。
「買って!」より「共感してくれたら嬉しいな」くらいの、ゆるやかな距離感が心地よさを生みます。
✅4. “コメントしやすい余白”を残す
投稿の中にあえて「余白」を設けることで、ユーザーが自分の考えや体験を重ねやすくなり、自然なコメントや共感のアクションが生まれます。
たとえば──
・「あなたならどうしますか?」と問いかける
・「これはまだ社内でも意見が割れています(笑)」など、結論を曖昧にしてみる
・「わかる方いますか?」という“共感ベース”の問いかけ
こうした仕掛けが、“人の声を集める投稿”をつくるうえで大きな武器になります。
4章:共感で“安定して伸びている”企業アカウントの事例

SNS運用というと、「バズらなければ意味がない」と思われがちですが、実際には地道に共感を集めながら“安定したファン層”を築いている企業アカウントが数多く存在します。
ここでは、バズ一辺倒ではない、“信頼型SNS運用”を実践している企業の事例を紹介します。
■ 事例①:北欧、暮らしの道具店(Instagram)
通販サイト「北欧、暮らしの道具店」のInstagramでは、商品の紹介だけでなく、暮らしの中でふと共感できる感情や視点を大切にした投稿が中心です。
たとえば──
・「週末に少しだけ余裕をつくるために私がやっていること」
・「料理がめんどうな日の“逃げ道レシピ”」
このように“誰もが感じる日常の小さな悩み”にそっと寄り添うことで、「自分ごと」として読まれ、自然なエンゲージメントが集まっています。
華やかではないけれど、「いいねの質」が非常に高いアカウントの代表例です。
プローフィールリンク:https://www.instagram.com/hokuoh_kurashi/
■ 事例②:タカラトミー(X)
おもちゃメーカーのタカラトミー公式X(旧Twitter)は、商品説明に終始せず、遊び心と親しみやすさをもった投稿が人気です。
特に注目すべきは「ゆるい投稿」と「中の人のキャラ立ち」。
例:
・「みんな、寝たふりってする派?タカラトミーはたまにする派です。」
・「今日は社内で『好きなポケモン会議』が始まって誰も働いていません(嘘)」
こうした“ゆるい発信”は、商品の売り込み感がゼロ。それでも、「人間味」があることで共感を呼び、結果として商品にも好感を持たせることにつながっています。
プロフィールリンク:https://x.com/takaratomytoys
■ 事例③:サントリー(X)
飲料メーカーのサントリーは、一見ふつうの「季節ネタ」や「雑談風投稿」が多く、一つ一つは地味ですが、長期的に見ると非常に安定した運用をしています。
投稿例:
・「金曜の17時がいちばん好きな飲み物ってなんですか?」
・「土曜日の昼下がりに聴きたい音楽、教えてください」
こうした投稿は一見すると販促とは関係ないように見えますが、ユーザーの日常の“気分”に寄り添っているため、ファンが離れにくく、エンゲージメントが長期的に持続します。
共通しているのは、「売り込みより、関係づくり」。
そして、フォロワーが安心して声を出せる“空気感づくり”に成功している点です。
プロフィールリンク:https://x.com/suntory
5章:バズらなくても成果は出せる|“共感設計”が企業にもたらす3つの価値
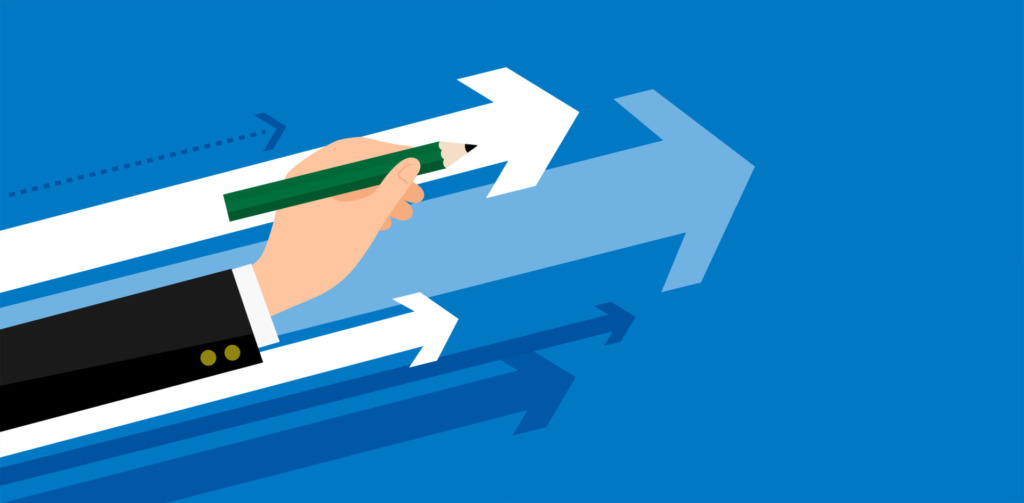
「SNS=バズらせるもの」という固定観念から離れ、共感をベースにした“静かな運用”を続けている企業は、着実に成果を上げています。
ここでは、バズを狙わない“共感設計型”の運用によって得られる3つの価値をまとめます。
① 信頼と親近感が積み上がる
共感ベースの投稿は、ユーザーに「この企業はわかってくれてる」と感じさせる力があります。
それが継続されることで、企業やブランドへの信頼感・安心感が育ち、ファンやリピーターを生む土台になります。
一度だけのバズよりも、10回の「共感した」の方が企業の“資産”になります。
② コンバージョンにつながる“濃いファン層”が育つ
共感を得てつながったフォロワーは、単なる“数字”ではなく、商品やサービスへの高い関心を持った“見込み顧客”です。
たとえば、
・Instagramで共感→ECサイトで商品購入
・Xで雑談風投稿→社名や理念に好印象→採用サイトへ
というように、長期的な“顧客導線”としての役割を果たしてくれます。
③ SNSが“ブランディングの武器”になる
共感運用は、「この企業、なんか好きだな」と思ってもらうブランディング効果が高く、競合と差別化する“空気感”の演出にもつながります。
特に中小企業やスタートアップにとって、広告に頼らず“ファンづくり”ができるSNSは、コストパフォーマンスに優れたブランディングツールとなります。
▷ SNS運用代行として“共感設計”をどう提案するか?
SNS運用代行を提供する立場としては、クライアントに対して「拡散=成果」という誤解を解き、“共感設計”の価値を言語化して提案することが鍵になります。
提案の切り口としては──
・バズ狙いではなく、ブランドに合った「等身大の発信」を育てましょう
・炎上リスクを抑えながら、顧客との信頼関係を築いていく運用が可能です
・継続的にエンゲージメントを得られる設計にすることで、広告に頼らない“自走するSNS”になります
こうした視点をもとに、「共感を積み上げるSNS戦略」をクライアントに提案できれば、差別化にもつながりやすく、商談獲得にも直結していきます。
✅まとめ
SNSの本質は“人と人とのつながり”です。
だからこそ、企業アカウントが共感を起点に信頼を築く運用は、時代を超えて強く支持されていく運用スタイルと言えるでしょう。
短期的なバズよりも、長期的なブランド価値の蓄積。
「バズらないSNS」には、静かに成果を生み出す力があるのです。