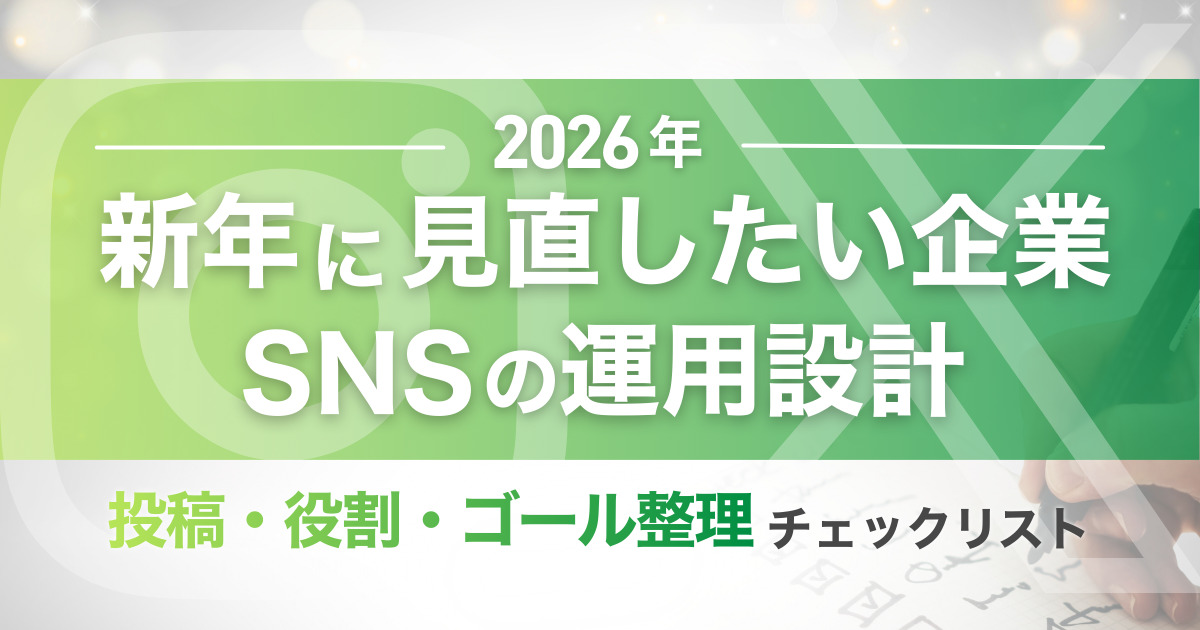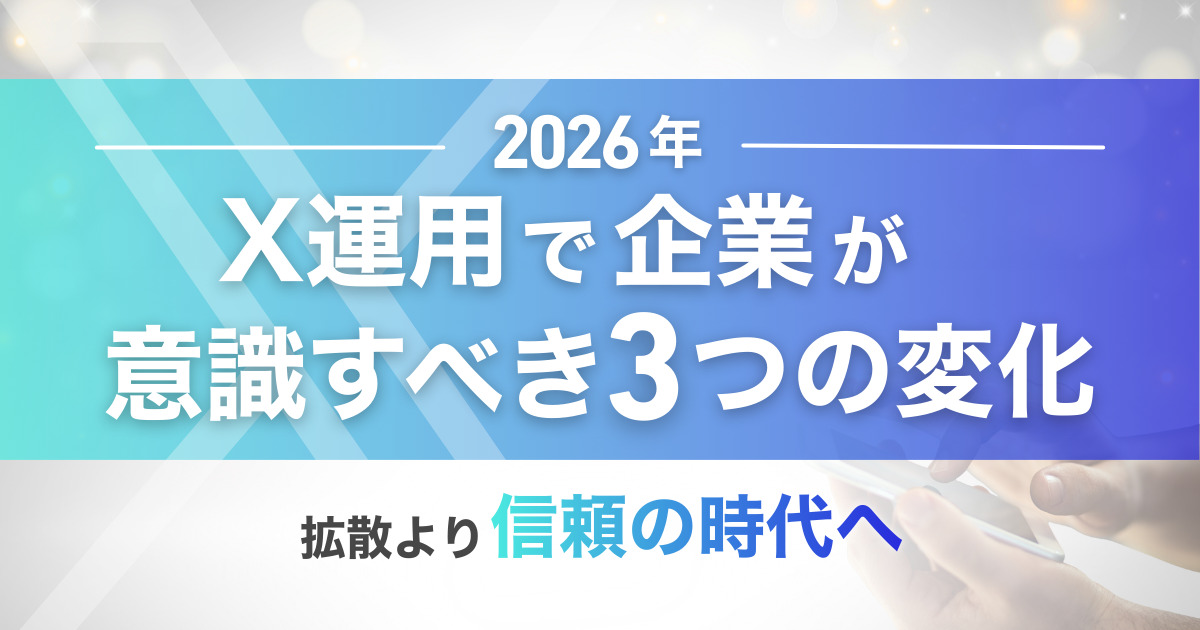2025.8.15
Xの企業アカウントが社員を前面に出すべき3つの理由と実践ステップ
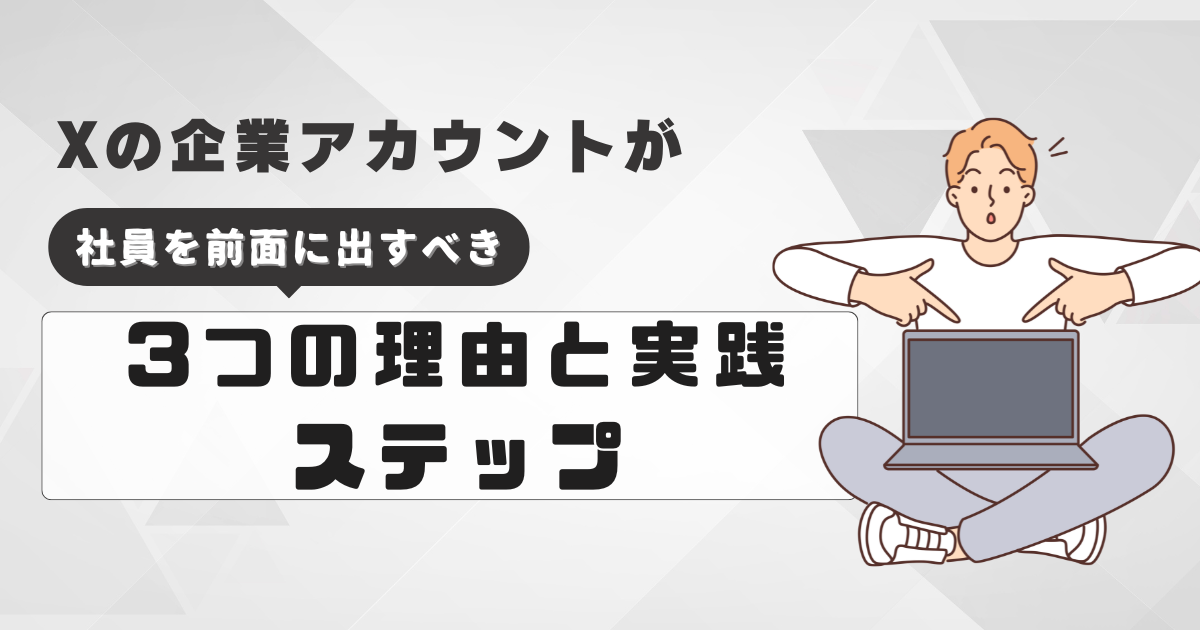
企業のX(旧Twitter)アカウントといえば、かつてはロゴや社名だけの匿名運用が主流でした。しかし近年は「中の人」や社員を前面に出し、“顔が見える運用”に切り替える企業が増えています。背景には、SNSにおける共感や親近感の重要性の高まりがあります。匿名の公式発信よりも、人柄やストーリーが感じられる発信の方が、フォロワーの関心やエンゲージメントを高めやすいのです。
特にXは、短文でのやりとりやリプライなど双方向の会話が生まれやすいプラットフォーム。担当者のキャラクターが立っていることで、企業としての発信もより柔軟かつ自然なものになり、結果的にブランドへの信頼感や好感度の向上につながります。
本記事では、Xの企業アカウントが“顔”を出すべき理由を3つの視点から解説し、実際に運用に取り入れるための具体的なステップまでご紹介します。
目次
第1章:顔出し運用が生む3つの効果

企業アカウントが“顔”を出すことは、単なる見た目の変化ではなく、フォロワーとの関係性や発信の広がり方に大きな影響を与えます。ここでは、特に効果が大きい3つのポイントを解説します。
1. 親近感と信頼感が高まる
担当者や社員の顔が見えることで、発信内容に“人”の温度感が加わります。フォロワーは「誰が発信しているのか」を意識しやすくなり、ブランドへの信頼感や好意が生まれやすくなります。特にBtoB企業の場合、商談前から担当者への心理的距離を縮める効果があります。
2. 投稿に共感が集まりやすくなる
人間味が見える発信は、フォロワーの感情を動かしやすい傾向があります。例えば日常の出来事や社内の裏側、ちょっとした失敗談などは、無機質な公式情報よりも共感やリアクションを得やすく、リプライや引用ポストなどの双方向コミュニケーションにもつながります。
3. 拡散のチャンスが広がる
“中の人”が前面に出ることで、個人アカウント同士のような交流が生まれ、フォロワー外にもリーチが広がりやすくなります。フォロワーから「この人の投稿をシェアしたい」と思われれば、自然な形でポストが拡散され、結果的に企業全体の認知度向上にもつながります。
第2章:Xならではの「顔出し効果」が生まれる理由

同じSNSでも、プラットフォームごとに特性やユーザー行動は大きく異なります。顔出し運用が特にXで効果を発揮しやすいのは、次のような理由があります。
1. リアルタイム性と会話の文化
Xはニュースや時事ネタ、トレンドに対する即時反応が重視される場です。顔が見える担当者は、フランクな一言や軽いツッコミなど、臨機応変なやりとりがしやすくなります。この“人感”のある反応は、公式アカウントらしい堅さを和らげ、会話の輪に入りやすくする効果があります。
2. リプライや引用ポストで広がる人脈
インスタのコメント欄は投稿単位で閉じた会話になりがちですが、Xのリプライや引用ポストは、フォロワー外にも会話が広がります。顔出しをしていると「誰が話しているのか」が明確になり、他企業や個人とのコラボややりとりが自然に増え、結果的に拡散の機会も多くなります。
3. インスタとの差別化によるブランド強化
インスタはビジュアル主体の世界観づくりに強みがありますが、顔出し運用は必ずしも中心ではありません。一方、Xはテキスト主体の軽快な発信に加え、担当者の個性を前面に出すことで「ここでしか見られない発信」を作れるのが特徴です。複数SNSを運用する企業にとっては、プラットフォームごとの役割分担が明確になり、ブランド全体の印象を強化できます。
第3章:顔出し運用を始める前に押さえるポイント

顔出し運用は効果が大きい反面、計画性やリスク管理が欠かせません。ここでは、導入前に必ず検討しておくべきポイントを3つ挙げます。
1. 社内合意と役割の明確化
担当者を前面に出す場合、その人物が企業の顔となります。発信内容や対応の範囲、立ち位置を社内で明確にし、承認フローを整えておくことが重要です。突然の炎上や誤解を招く発信を避けるためにも、事前にルールや責任範囲を合意しておきましょう。
2. 個人情報とプライバシーへの配慮
担当者の氏名や詳細プロフィールをすべて公開する必要はありません。必要以上の個人情報は伏せつつ、「顔」と「キャラクター」が伝わる工夫をしましょう。背景や服装、発言内容などから個人が特定されすぎないよう配慮することも大切です。
3. ネガティブ対応のガイドライン策定
顔が見える発信はポジティブな反応を得やすい一方、批判やクレームの矢面に立つ可能性もあります。ネガティブなコメントへの対応方針や禁止ワード、対応者の交代フローなどをあらかじめガイドライン化しておくことで、安心して運用を続けられます。
第4章:顔出し運用を成功させる3つの実践ステップ

顔出し運用は、ただ担当者を前面に出せば良いというものではありません。計画的に準備し、段階を踏んで運用することで効果を最大化できます。ここでは、実践しやすい3つのステップをご紹介します。
ステップ1:担当者キャラの設定とトーンを決める
顔出し運用の第一歩は、「どう見せたいか」を決めることです。
・親しみやすい友達のような雰囲気
・専門家として頼れる存在感
・おちゃめでユーモラスなキャラ
など、ブランドの方向性に合うキャラクターを設定し、発信トーン(語尾、絵文字の使い方、ユーモアの度合い)を統一します。
ステップ2:初期は日常+業務を半々で発信
いきなり業務や商品紹介ばかりだと、宣伝感が強くなります。初期は社内の日常や裏側、担当者の小さな気づきなど、“人”が見える内容を多めに混ぜることでフォロワーの心を掴みやすくなります。実際、食品宅配の「三ツ星ファーム」も担当者の素朴なコメントや社内エピソードを交えることで、宣伝投稿の反応率が向上しています。
ステップ3:フォロワーとの会話量を増やす
顔出し運用は「投稿」だけでなく「返信」でこそ効果を発揮します。リプライや引用ポストで積極的にやりとりし、相手の発信にも反応することで“関係性”が育ちます。この双方向のやりとりは、アルゴリズム上の露出増にも直結します。
第5章:まとめ|顔出しはブランドの“信頼資産”になる
顔出し運用は、フォロワーとの距離を縮め、ブランドの信頼資産を積み上げる強力な手法です。発信に人の温度感が加わることで、単なる商品・サービスの紹介を超えた「ファンづくり」が可能になります。
しかし、効果的に成果を出すためには、キャラクター設計、コンテンツ企画、炎上リスク管理、効果測定など、複数の要素を同時に回す必要があります。さらに、SNSのアルゴリズムやトレンドは日々変化するため、社内だけで常に最適解を出し続けるのは容易ではありません。
そこで選択肢となるのが、SNS運用代行の活用です。
運用代行であれば、
・ブランドや業界に合わせたキャラクター設定と発信トーンの構築
・顔出しを活かしながらも炎上を防ぐ投稿・対応ルールの策定
・投稿ごとの効果測定と改善提案の継続実施
など、成果に直結する運用をプロの視点で支援できます。
「顔出し運用に挑戦したいけれど、リスクや手間が心配…」
そんな企業こそ、プロと組むことで安心かつ効果的な“顔が見えるSNS運用”を実現できます。まずは小さな一歩から始めて、ブランドの信頼資産を育てていきましょう。