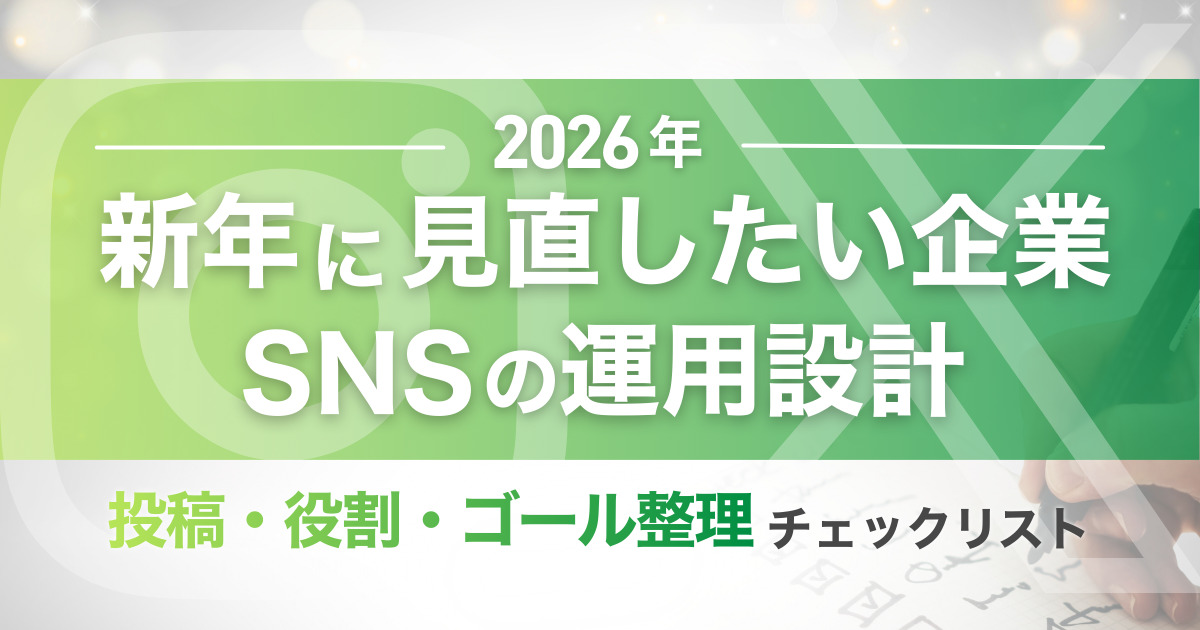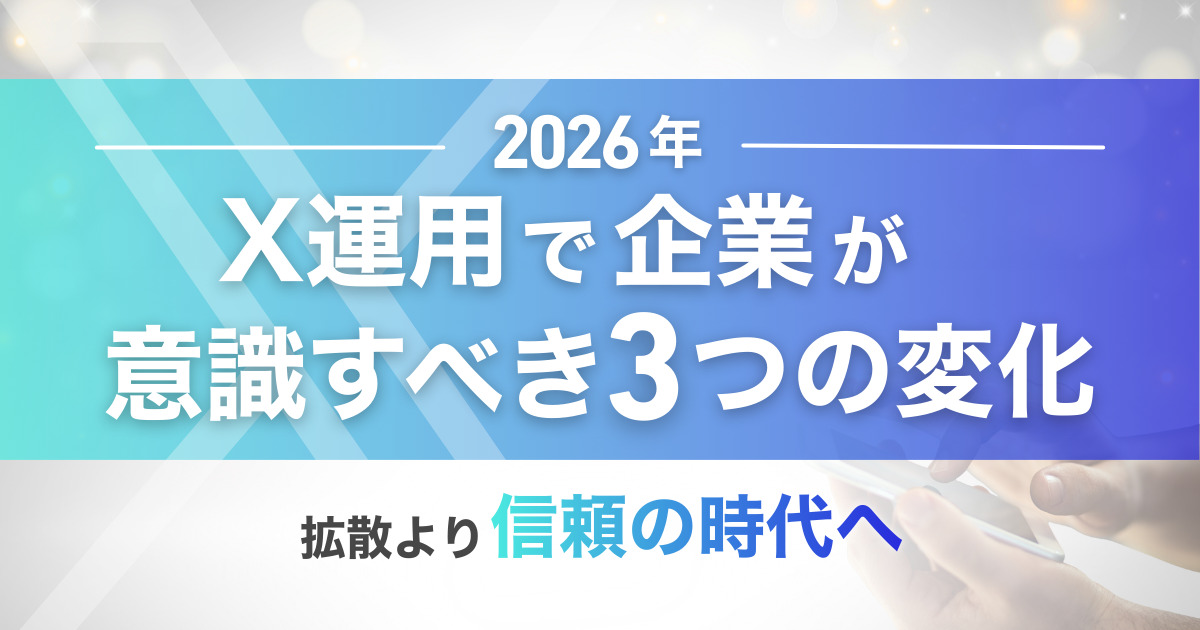2025.8.17
X(旧Twitter)でUGCを活用する方法|ファンの声を企業運用に生かす投稿設計術
でUGCを活用する方法.png)
SNS運用の世界で近年注目を集めているキーワードのひとつが「UGC(User Generated Content)」です。UGCとは、企業ではなくユーザー自身が作成・発信したコンテンツのことを指し、レビュー、写真、動画、コメントなど形はさまざまです。第三者の自然な声は広告以上の説得力を持ち、他のユーザーに強い共感や行動喚起を与えます。
特にX(旧Twitter)は、UGCが生まれやすく、かつ広がりやすい環境が整っているプラットフォームです。短文や写真1枚で投稿できる手軽さ、拡散性の高いリツイート機能、引用ポストによる会話の広がりなど、ユーザーが日常的に発信したくなる条件がそろっています。企業がこの流れをうまく設計すれば、広告費を大きくかけずともブランド認知や信頼を飛躍的に高めることが可能です。
しかし、UGCは「自然発生するものだから運に任せる」という考えでは成果につながりにくく、戦略的にきっかけを作り、拾い、広げる仕組みが必要です。これを怠ると、せっかく生まれたUGCが埋もれてしまったり、ブランドと無関係な方向へ拡散されるリスクもあります。
本記事では、XにおけるUGCの強みを整理し、自然にユーザーが投稿したくなるきっかけ作りから、企業公式アカウントによる拾い方、拡散の方法、そして注意すべきポイントまで、実践的な投稿設計術をご紹介します。さらに、成功事例や活用の落とし穴も交えながら、UGCを継続的なブランド資産に変えるための運用のヒントをお届けします。
目次
第1章:XにおけるUGCの強み
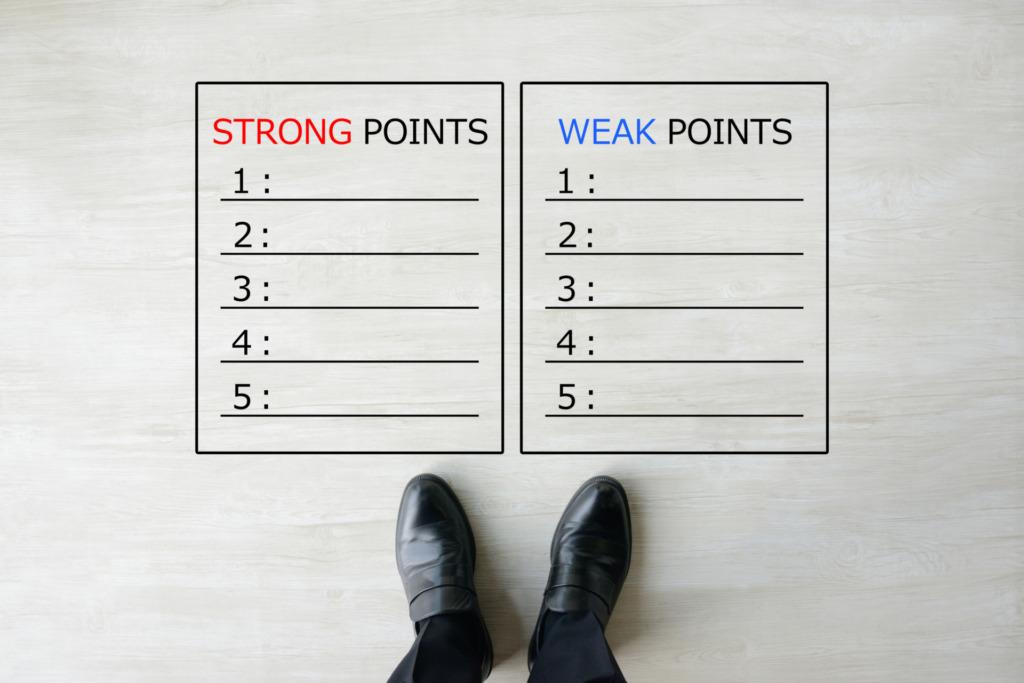
UGCはSNS全般で効果を発揮しますが、特にX(旧Twitter)は他のプラットフォームよりもUGCの価値が活きやすい特徴があります。ここでは、その理由を3つの視点から解説します。
1. 拡散力が高く、情報が広がりやすい
Xは「リツイート」や「引用ポスト」によって、フォロワー外へ情報を一気に広げられる仕組みがあります。例えば、ユーザーが商品を使った感想をポストすると、それをフォロワーがリツイートし、さらにその先のフォロワーにも届くため、短期間で大きな認知拡大が可能です。UGCは第三者の声であるため、広告よりも受け入れられやすく、拡散の連鎖が生まれやすいのが特徴です。
2. 第三者視点による高い信頼性
UGCの大きな価値は、その発信者が「企業ではない」という点にあります。ユーザーが自発的に投稿したレビューや感想は、宣伝色が薄く、同じ立場の消費者としてのリアルな声として受け止められます。特に新規顧客や検討段階にある見込み客にとっては、この第三者視点が購入や利用の後押しになります。
3. 会話から生まれる継続的な関係性
XではUGCが発生した時点で終わりではなく、その後のやりとりによって関係性が深まります。企業がUGCに対して感謝のリプライを送ったり、引用ポストでコメントを付けることで、発信者との距離が縮まり、再びポストしてもらえる可能性が高まります。こうしたやりとりは他のユーザーの目にも触れるため、「このブランドはユーザーを大事にしている」というポジティブな印象を広く与えることができます。
第2章:UGCを生み出す3つの仕掛け

UGCは「偶然生まれるもの」ではなく、企業が意図的に環境やきっかけを整えることで発生しやすくなります。ここでは、ユーザーから自然に投稿を引き出すための3つの仕掛けを紹介します。
1. 投稿したくなる“きっかけ”を作る
人は、テーマや理由があると行動を起こしやすくなります。X上でUGCを生むには、投稿したくなる「きっかけ」を設計することが重要です。
- ハッシュタグ企画:例)#◯◯チャレンジ、#私の◯◯体験
- 質問ポスト:「あなたのおすすめの使い方は?」など参加型の問いかけ
- 季節やイベントに絡めたテーマ:年末、GW、周年記念など
こうした「参加する理由」を提示すると、普段は発信しないユーザーも投稿に踏み切りやすくなります。
2. ユーザーに負担をかけない参加方法
UGCは投稿のハードルを下げるほど発生しやすくなります。文章を長く書く必要がない、特別な機材やスキルがいらない、といった条件がポイントです。
- 短文でもOKにする
- 写真1枚・動画数秒などライトな形式
- 既存のポストにリプライするだけの参加形式
負担を最小限にすることで、「ちょっとやってみようかな」という軽い参加が増えます。
3. 企業側が積極的に拾いに行く姿勢
UGCは、発生させたら終わりではありません。ユーザーが投稿してくれたら、それを見つけて反応することが重要です。リプライでお礼を言ったり、引用ポストで感想を共有したりすることで、発信者は「見てもらえた」という満足感を得られ、再び参加してくれる可能性が高まります。
- ブランド名やキャンペーンハッシュタグでの検索
- リスト機能で常連参加者をフォロー
- モニタリングツールを使って効率的に発見
UGCを積極的に拾う姿勢は、参加者だけでなく周囲のフォロワーにも「この企業はユーザーを大切にしている」という印象を与えます。
第3章:UGCを拡散につなげる公式アカウントの動き方

UGCは投稿された瞬間がゴールではありません。むしろそこからが、ブランド認知やエンゲージメントを広げるチャンスです。公式アカウントがどのようにUGCを拾い、拡散に結びつけるかが成果の分かれ目になります。
1. UGCを見つけやすくする仕組みを作る
UGCを効率的に発見するためには、日々のモニタリング体制が必要です。
- 検索機能の活用:ブランド名やキャンペーンハッシュタグで定期検索
- リスト化:UGCをよく投稿してくれるユーザーをリストに追加
- 通知設定:特定ワードやタグを含む投稿があったら通知が届くように設定
- SNS分析ツールの導入:MentionやTweetDeckなどで複数ワードを同時監視
2. 二次発信時の注意点
UGCを引用ポストや公式投稿で取り上げる際は、必ず発信者の許可を取りましょう。引用ポストは原則として相手の投稿がそのまま表示されますが、スクリーンショットや編集を伴う場合は著作権・肖像権のトラブルを避けるために事前確認が必須です。
- 許可取りはDMまたはリプライで簡潔に依頼
- 引用時はユーザー名を明記し、感謝の言葉を添える
- 不特定多数に見られても問題ない内容か再確認する
3. 拡散とブランド強化を両立する引用ポスト
UGCを広げる際は、単なる共有に留まらず、ブランド価値を高めるコメントを加えましょう。
- 具体的な利用シーンを説明:「◯◯様はこんな風にご活用いただいています」
- 他ユーザーへの参加を促す:「皆さんのおすすめの使い方も教えてください」
- ブランドストーリーとつなげる:「このアイデアは創業当初からの想いに通じます」
こうすることで、UGCは単なるユーザー投稿ではなく、ブランドメッセージを強化するコンテンツとして機能します。
第4章:UGC活用の成功事例

UGCの価値を最大限に引き出すには、企業の目的や業種に合わせた活用方法が必要です。ここでは、BtoC、BtoB、イベント活用という3つの切り口で、実際の成功パターンを紹介します。
1. BtoC企業|日常使いと感想投稿を促す
事例候補:コカ・コーラ ジャパン 公式アカウント (@CocaColaJapan)
国内でも親しみやすいGIFや写真、季節感のあるUGCを幅広くリツイートし、ブランドへの日常接点を強化する運用が見られます。
ユーザー投稿を自然に活かし、飲料ブランドとしての親近感を高める効果が期待できます。
2. BtoB企業|専門分野の知見共有
事例候補:SHARP(シャープ)公式アカウント (@SHARP_JP)
生活家電や辞書ブランドとして親しみやすさを重視し、「家事あるある」などユーザーの声を引き出す投稿がUGCにつながりやすい事例です。
企業と生活者が共感を軸に会話するスタイルは、BtoBに転用しても信頼構築に有効です。
3. イベント・キャンペーンとの掛け合わせ
事例候補:原宿「友達がやってるカフェ」関連投稿
コンセプトと体験設計
- 2023年4月22日に原宿でオープンしたこのカフェは、「友達のバイト先に遊びに行くような感覚」を体験できるコンセプトで話題に。関連記事
- 店員は俳優やモデル、クリエイターなど「演技ができる人」が担当し、お客をあたかも“友達”に対して話すようなタメ口接客を行っていました (“80%のテンションで”という自然な距離感も意識されていた)。
SNSでの爆発的な拡散
- プレオープンの動画コンテンツはTikTokやX上で150万再生以上を記録し、特にZ世代の共感を集めました。関連記事
- 同店は、CyberAgentによる「Z世代ヒットトレンドランキング2023」で1位(モノ・コト部門)、TikTok上半期トレンド大賞へのノミネートなど、複数のトレンド賞を受賞しています。
店舗概要と運営背景
- 場所は渋谷区神宮前の原宿ベルピア3F、カフェタイム(昼)からバー営業(夜)への切り替えスタイル。メニュー名も「いつも飲んでるやつ」「大変そうだからすぐ出せるので大丈夫だよ」などユーモア感あふれる言葉でした。
- 店というより“実験空間”として企画されたこの店舗は、企画制作会社 kakeru(代表:明円卓氏)のチームによる創造的プロジェクトの一環だったそうです。
営業期間と将来展望
- 非常に高い注目を集めながら営業は終了し、2024年9月末に閉店しました。
- 閉店後、kakeru社は同スペースを再び別企画で使用する予定があると発表しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 説得力 | 実店舗の詳細な施策とリアルユーザー反応を示すことで、UGC生成の仕組みの有効性が具体的に伝わる。 |
| バズの構成要素 | コンセプト(友達接客)、演出(俳優スタッフ)、投稿しやすいストーリー性がSNS投稿を促進。 |
| 成功から学ぶ設計 | “非日常+遊び心+参加しやすさ”の組み合わせがUGCを自然に生み出す構成となる。 |
| 注意喚起的活用 | 店舗閉店という結果も示すことで、一過性の演出に留まらない運用設計の必要性を強調できる。 |
イベントや空間の体験そのものがUGCのきっかけになる好例です。
UGC活用についてさらに詳しく知りたい方は、
こちら(Forest Daliのコラム)もぜひご覧ください。
第5章:UGC活用の落とし穴と回避策

UGCは強力なマーケティング資産ですが、運用には注意点もあります。事前にリスクや課題を理解し、適切な対策を取ることで、安心して活用できます。
1. ネガティブ投稿の拡散
UGCの中には、商品やサービスに対する批判や不満の声も含まれることがあります。これを不用意に取り上げると、マイナスイメージを広げてしまう恐れがあります。
回避策:
- 投稿を引用・共有する前に内容を精査する
- ネガティブ意見は引用ではなく、個別対応や改善報告で返信
- 炎上や誤解につながる投稿は無理に拾わない
2. 著作権・肖像権のトラブル
ユーザーが投稿した写真や動画には、第三者が写り込んでいる場合や、他人の著作物が含まれている場合があります。無断で引用や再利用すると、権利侵害のリスクがあります。
回避策:
- 二次利用時は必ず投稿者に許可を取る
- クレジット表記を明記し、感謝のコメントを添える
- 企業が事前に利用ルールを告知しておく
3. ブランドと無関係なUGCの拡散
ハッシュタグ企画を実施すると、全く関係のない投稿が混ざることがあります。これを拾ってしまうと、ブランドメッセージが薄まり、混乱を招く可能性があります。
回避策:
- ハッシュタグの事前リサーチで既存利用状況を確認
- ブランド名や固有性の高いフレーズを組み込む
- 拾う投稿はテーマとの関連性を優先
4. モニタリング負荷の増加
UGCを活用するには、常に投稿を探し、対応する体制が必要です。社内リソースだけでは見落としや対応遅れが発生する可能性があります。
回避策:
- 検索・通知機能やツールを活用して自動化
- 優先度を決めて拾う投稿を選別
- 必要に応じて運用代行や外部サポートを利用
第6章:まとめ|UGCは企業とファンが育てる資産
UGCは、単なるユーザー投稿ではなく、企業とファンが一緒に育てていくブランド資産です。特にX(旧Twitter)は拡散性と会話性に優れ、ファンの声を自然な形で広められる土壌があります。
本記事で紹介したように、
- きっかけ作りでUGCを生み出し
- 拾って反応する姿勢で関係性を深め
- 拡散とブランド強化を両立させることで
UGCは広告以上の影響力を持つマーケティング施策となります。
しかし、その運用は思っている以上に手間がかかります。モニタリングや許可取り、拡散時のコメント設計、ネガティブ対応まで、日々の業務の中でこれらをすべて行うのは容易ではありません。
そこで選択肢となるのが、SNS運用代行の活用です。UGCを生むための企画立案から、日々のモニタリング・拾い上げ・拡散・効果分析までを一貫してサポートできるため、ブランドの魅力を最大限に引き出しながら、安全かつ継続的なUGC運用が可能になります。
UGCは短期的なキャンペーンだけでなく、長期的なファンづくりにも直結する“信頼の資産”です。自社だけで抱え込まず、外部の力も上手に取り入れながら、UGCを企業成長のエンジンにしていきましょう。