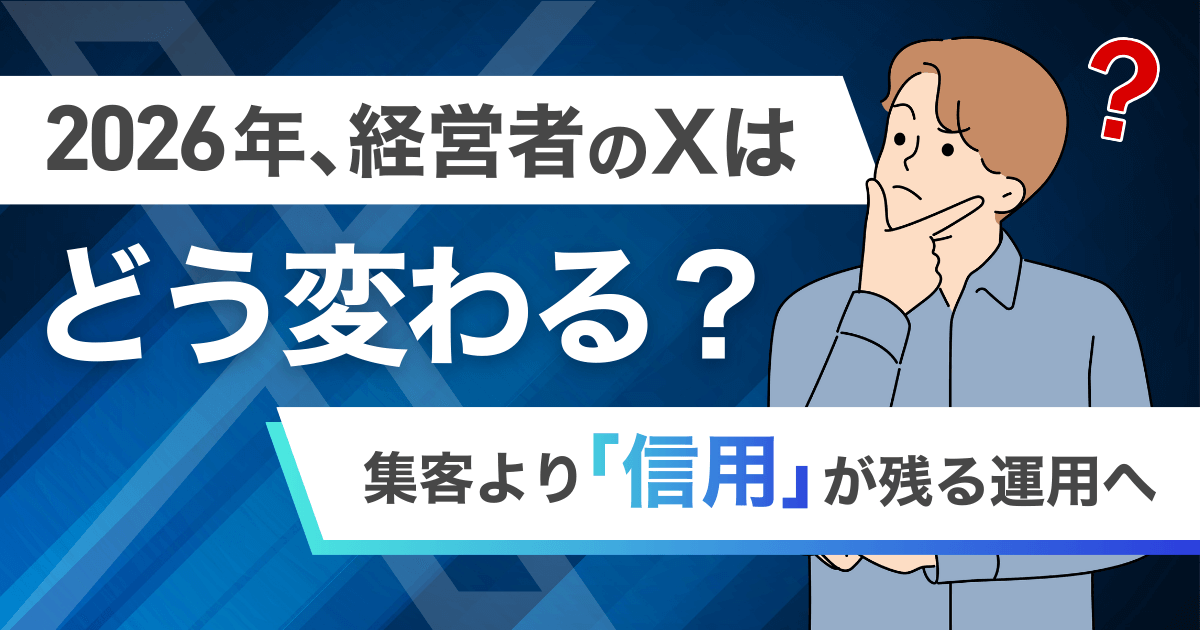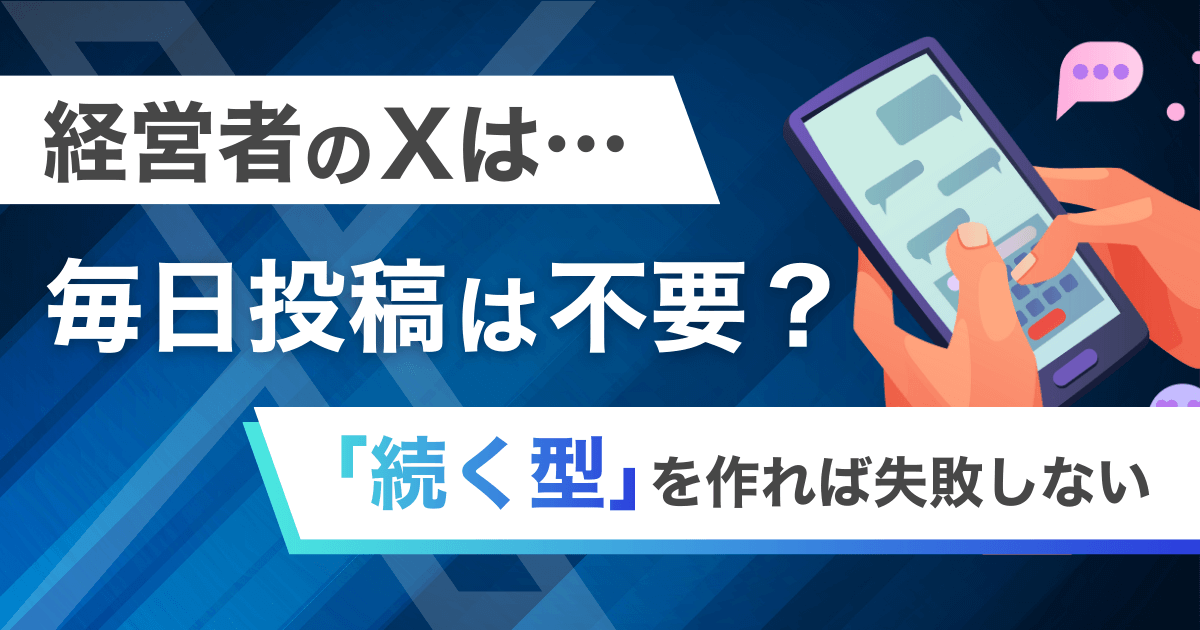2025.9.6
食品ブランドのX戦略|レシピ動画と調理Tipsでファンを育てる方法
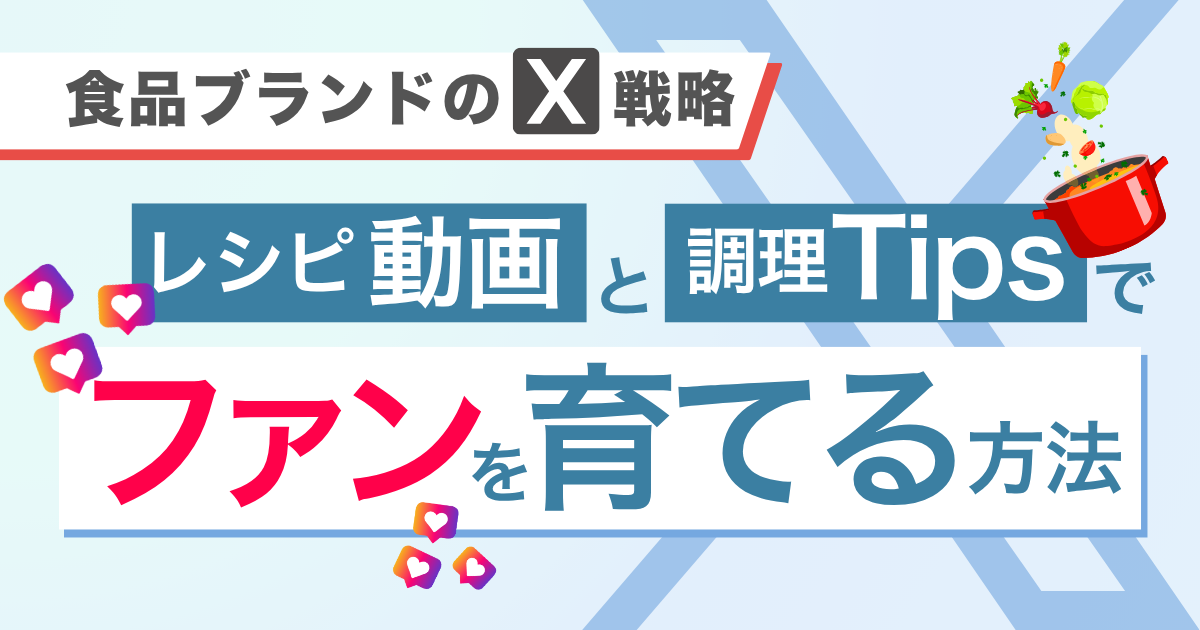
食品ブランドがSNSを活用する際、X(旧Twitter)は拡散性と情報の即時性に優れており、新規顧客との接点づくりや既存顧客との関係強化に大きな効果を発揮します。なかでも「レシピ動画」と「調理Tips(ちょっとした調理のコツ)」は、生活者の関心を引きやすく、保存やシェアを通じてファン化を促すコンテンツとして注目されています。
消費者は日々の食事づくりに役立つ情報を求めており、「簡単に作れるレシピ」や「知って得する調理法」は、誰もが気軽に反応できるテーマです。食品ブランドにとっては、商品を自然な形で紹介できるだけでなく、「役立つ情報をくれるアカウント」という信頼を積み上げるきっかけになります。
本記事では、食品ブランドがXでファンを育てるための戦略として、レシピ動画と調理Tipsをどう活用すべきかを解説し、具体的な事例や運用のポイントを紹介していきます。
第1章:食品ブランドがXでファンを育てる意義

食品ブランドにとってXは「商品を売る場所」というよりも、ファンを育てて長期的な関係を築く場として活用するのが効果的です。SNSを通じたコミュニケーションは、一度の購入で終わらず「また買いたい」「このブランドの商品なら安心」と感じてもらうきっかけをつくります。
1. フォロワー=潜在顧客ではなく“ファン候補”
多くのブランドがSNS運用を「フォロワーを増やすこと」と捉えがちですが、食品業界において重要なのは「フォロワーをファンに育てること」です。レシピや調理Tipsの発信を通じて「役立つ」「便利」「楽しい」と感じたユーザーは、そのブランドにポジティブな印象を持ち、購買や継続利用につながりやすくなります。
2. 情報の即時性と日常への浸透
Xは日常的にチェックされやすく、料理や食事に関するちょっとしたヒントが生活の中にすぐ浸透します。たとえば「今日の晩ごはんに使えるレシピ」や「保存方法の豆知識」は、ユーザーがその日のうちに実践できるため、投稿が日常行動に直結しやすいのです。
3. ファン化がブランドロイヤリティを生む
食品は生活必需品であり、選択肢が多いジャンルです。その中で選ばれ続けるには、商品の良さだけでなく「信頼できるブランド」としての印象を積み重ねることが大切です。Xで継続的にレシピやTipsを提供することで「役立つ情報をくれるブランド」というポジションを確立でき、ブランドロイヤリティの強化につながります。
4. コミュニケーションの積み重ねが差別化に
同じカテゴリの商品を扱う企業は数多く存在しますが、消費者が「情報を通じて親しみを感じるブランド」として認識するのは限られています。レシピ動画や調理Tipsで日々接点を持つことは、価格や商品特徴ではなく「関係性」で選ばれるブランドへの成長につながります。
第2章:レシピ動画の活用術

レシピ動画は食品ブランドがXで発信するうえで、最も拡散性と保存性の高いコンテンツのひとつです。ユーザーは「おいしそう!」「作ってみたい!」と感じると、リポストやブックマークを自然に行い、情報の拡散とアーカイブが同時に進みます。ここではレシピ動画を活用する際のポイントを整理します。
1. ショート動画でテンポよく
Xのタイムラインは流れが早いため、動画は30〜60秒程度のショート動画が最適です。材料紹介から調理、盛り付けまでをテンポよくまとめることで、ユーザーが最後まで視聴しやすくなります。調理工程を短縮して見せたり、テロップを簡潔に入れたりすることで、「真似したい」と思わせる要素が強まります。
2. 商品を自然に登場させる
レシピ動画の最大の利点は、ブランドの商品を“自然に”紹介できることです。たとえば調味料メーカーなら「このタレを使えば味付けが一瞬で決まる」といった見せ方が可能です。広告色を強めるのではなく、「生活に役立つ情報の中で商品が登場する」構成にすることで、ユーザーに受け入れられやすくなります。
3. 季節性やイベント性を掛け合わせる
「夏にぴったりの冷やしレシピ」「クリスマスの華やかメニュー」といった形で、季節やイベントを絡めるとさらに拡散が狙えます。食品は季節性との相性が良いため、レシピ動画のテーマをイベントカレンダーと連動させることが効果的です。
4. 成功事例
大手冷凍食品メーカーは、Xで「3分で完成!お弁当に便利なレシピ」動画を継続的に発信し、数万件単位のエンゲージメントを獲得しています。時短・簡単という切り口は働く世代に強く刺さり、商品の購買促進につながりました。また、スイーツブランドでは「見た目が映えるレシピ動画」を投稿し、UGCや口コミを拡大させています。
関連記事→食品業界のX活用術|季節イベントと“今日は何の日”投稿で売上を伸ばす
第3章:調理Tips投稿の効果

レシピ動画と並んで食品ブランドのX活用で効果的なのが、調理Tips(ちょっとした調理のコツや豆知識)の発信です。短くても役立つ情報は保存・シェアされやすく、ユーザーに「このブランドはためになる」と思わせる強力なきっかけになります。
1. 気軽に試せる情報が共感を呼ぶ
「卵をふんわり仕上げるコツ」や「冷凍ごはんをふっくら解凍する方法」など、誰もがすぐ試せる情報は共感されやすく、リポストやブックマークにつながります。日常的な課題を解決する内容は「生活に寄り添ってくれている」というブランドの信頼感を高めます。
2. 豆知識投稿は拡散力が強い
Tipsは一見小ネタに見えますが、ユーザーが「知らなかった!」「今度やってみよう」と感じる情報は拡散されやすい傾向があります。特に画像やGIFで視覚的に説明すると、ユーザーがシェアする動機がさらに高まります。
3. UGC(ユーザー投稿)を誘発
調理Tipsは「実際にやってみた」というUGCが生まれやすい点も大きな魅力です。たとえば「この方法で唐揚げがカリッと揚がった!」という消費者の体験がX上で拡散されることで、ブランドへの信頼性と親近感が自然に高まります。
4. 成功事例
調味料メーカーが「冷蔵庫に余った野菜をおいしく使い切る方法」をTips投稿したところ、数千件のリポストと共に「試してみた!」というUGCが相次ぎました。こうしたTipsは広告感が少なく、消費者から「役立つブランド」として認知されるきっかけになっています。
関連記事→Xで成果が出る“共感投稿”の作り方|数字より“人”を集める企業運用術
第4章:事例紹介

実際にXでレシピ動画や調理Tipsを活用し、ファンづくりに成功している食品ブランドは数多く存在します。ここでは代表的な事例をピックアップして紹介します。
1. 大手調味料メーカーのレシピ動画
ある調味料メーカーは「5分で完成するおかずレシピ」をショート動画で定期的に発信。材料と調味料の組み合わせをシンプルに提示するだけで、数万件規模のエンゲージメントを獲得しました。特に「働く世代」「子育て世代」からの共感が大きく、商品の購買増加にもつながりました。
2. 冷凍食品ブランドの時短調理Tips
冷凍食品メーカーは「冷凍ご飯をふっくら解凍する方法」や「揚げ物をサクサクに戻す裏技」といったTipsを投稿。手軽に真似できる実用性が話題を呼び、ユーザーが写真付きで「やってみた!」と投稿するUGCが多数生まれました。結果として、ブランド全体の信頼性が高まり、商品の再購入率アップにつながりました。
3. スイーツブランドの映えレシピ活用
洋菓子ブランドは「映える盛り付けレシピ」を動画で展開。「#おうちカフェ」というハッシュタグと掛け合わせることで、消費者が自発的に写真を投稿。SNS上で「見た目がかわいい」と話題化し、若年層を中心にブランド認知を拡大しました。
4. 地域ブランドの豆知識発信
地域の調味料メーカーは「地元野菜と相性抜群のレシピ」や「昔から伝わる保存方法」といったTipsを発信。地域文化を絡めることでローカルコミュニティに強く刺さり、地域外からも「ご当地ブランド」として注目される結果に。地域発の中小ブランドがXを通じて全国的に話題化する好例となりました。
第5章:運用ポイントと成果最大化の方法

レシピ動画や調理Tipsは食品ブランドにとって強力な武器ですが、ただ発信するだけでは効果が限定的です。成果を最大化するためには、戦略的な設計と改善の積み重ねが欠かせません。ここでは押さえるべきポイントを整理します。
1. 投稿カレンダーを作る
レシピやTipsは「いつ、どんなテーマで発信するか」を計画的に設計することが重要です。季節イベント(バレンタイン・夏祭り・クリスマスなど)や「今日は何の日」と組み合わせたカレンダーを作成すれば、コンテンツのネタ切れを防ぎ、継続的に発信できます。
2. ハッシュタグを工夫する
「#簡単レシピ」「#おうちごはん」といった定番タグに加え、自社独自のハッシュタグを作ると、ブランド投稿が蓄積されやすくなります。ユーザーが真似して投稿するときにも使われ、自然にUGCが集まる仕組みが構築できます。
3. 動画×テキストのバランスを取る
動画は視覚的にインパクトを与えられますが、テキストに「ちょっとした工夫」を書き添えると効果が高まります。たとえば「冷凍庫からそのまま使える」「洗い物が減る」といった一言は、ユーザーの共感を呼びやすく、保存やシェアの動機づけになります。
4. リプライ対応とUGC活用
ユーザーがレシピやTipsを実際に試して投稿してくれたら、企業アカウントが「いいね」やリプライを返すことが大切です。小さな反応でも「ブランドが見てくれている」という信頼感を育み、ファン化につながります。UGCを引用リポストすれば、二次的な拡散も期待できます。
5. データ分析で改善を続ける
インプレッション数やエンゲージメント率、プロフィールアクセス数、リンククリック数を定期的に確認し、どの投稿が最も反応を得られたかを分析します。その結果を次の投稿に反映させることで、運用は回を重ねるごとに精度が高まり、成果も安定していきます。
6. 他チャネルとの連携
Xでの投稿をInstagramやYouTube、LINEなど他チャネルと連動させれば、同じコンテンツを多方面で活用できます。例えば「Xで紹介したレシピの詳しい調理動画はYouTubeで公開」といった導線を作れば、ブランド全体の接点が増え、幅広い層へのリーチが可能になります。
さらに詳しいX活用ノウハウは→Xの「リプライ戦略」入門|コメント欄で信頼と拡散を生む企業アクション
まとめ
食品ブランドがXを活用する際、レシピ動画と調理Tipsはファンづくりに直結する強力なコンテンツです。レシピ動画は「作ってみたい」という行動を喚起し、商品を自然に訴求できる手段。一方、調理Tipsは日常の課題解決につながり、「役立つブランド」という印象を消費者に与えます。
これらの投稿を継続することで、ユーザーは「フォローしておけば便利な情報が手に入る」と感じ、ブランドに対する信頼や親近感が高まります。結果的に、単なる一度きりの購入者ではなく、繰り返し商品を手に取るファンへと育っていきます。
また、成功の鍵は「計画性」と「コミュニケーション」。投稿カレンダーを作り、ハッシュタグやビジュアルを工夫し、ユーザーの反応にしっかり応えることが、ファン形成と長期的な売上アップを支える基盤になります。
食品ブランドにとって、レシピ動画と調理Tipsは 売上拡大だけでなく、ブランドロイヤリティを強化する戦略。日常に役立つ情報を届けることで、Xは“商品を売る場”から“ファンを育てる場”へと進化させることができるのです。