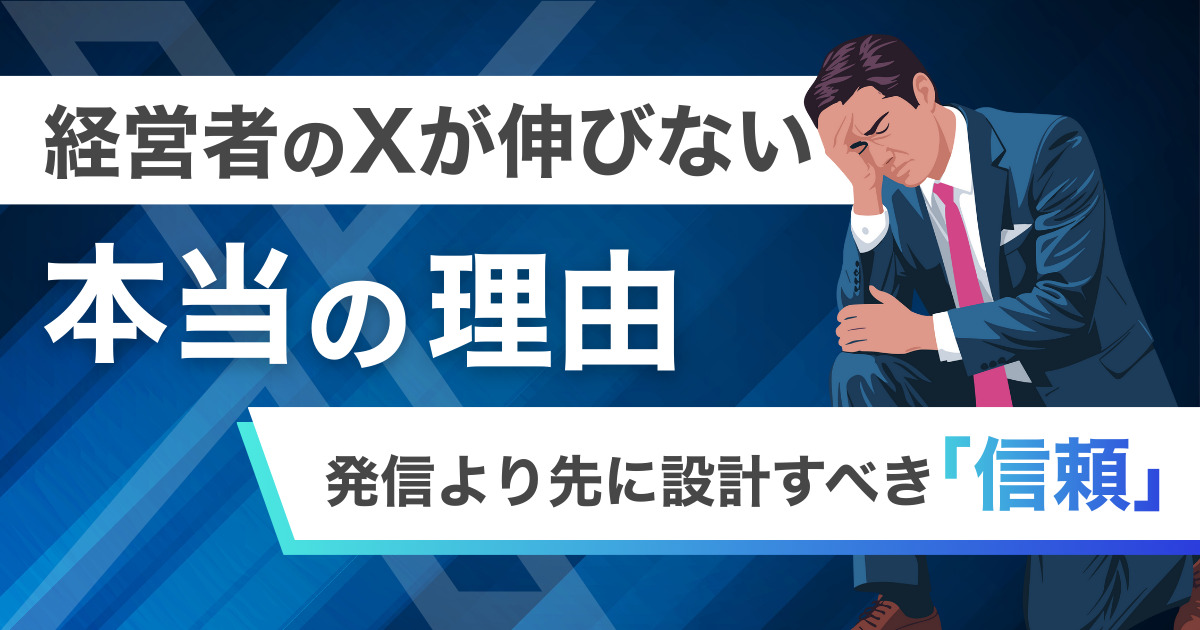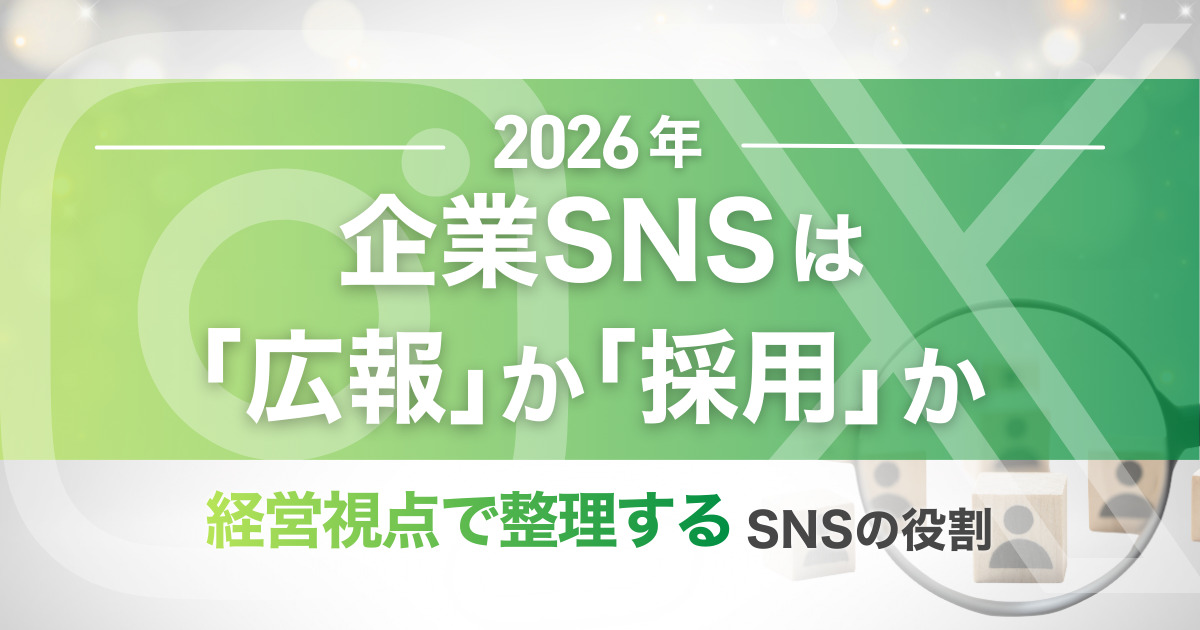2025.10.11
「今日は〇〇の日」をリールで使いこなす!食品業界のインスタ販促テクニック

食品業界の販促では、季節イベントや「今日は〇〇の日」のような記念日ネタが、売上アップのきっかけになることはもう常識ですよね。
これまではX(旧Twitter)でこの手法を活用する企業が多く見られましたが、最近では「Instagram、とくにリールで使いこなす企業」が一気に伸びています。
なぜなら――
- 動画+音楽で“季節感”が一瞬で伝わる
- 「保存」「シェア」されやすく、後から見返してもらえる
- 「今日は〇〇の日」フォーマットが“テンプレ化”できるので、運用がラクになる
つまり、「今日は〇〇の日」や季節イベント系の投稿は、Instagramでは“話題作り”だけでなく、“売上に直結する資産型コンテンツ”に変わるのです。
本記事では、食品業界がInstagram、とくにリールやストーリーズを使って季節ネタを成果につなげる方法をわかりやすく解説していきます。
目次
第1章:食品業界がInstagramを使うメリット

食品業界とInstagramは、視覚的な訴求が軸になるという点で非常に相性の良い組み合わせです。なかでも近年は、リールやストーリーズといった“動画ベースの投稿フォーマット”が普及したことで、これまで以上に「食べたい」「行ってみたい」などの感情を瞬間的に引き出しやすくなりました。音楽やテンポの良い編集と組み合わせることで、写真だけでは伝わらなかった“食の臨場感”をダイレクトに届けられる点は、Instagramならではの強みと言えるでしょう。
また、Instagramは投稿が「保存」されやすいプラットフォームであることも特徴です。たとえば“季節の簡単レシピ”や“この時期に飲みたいドリンクまとめ”のような投稿は、「後で試そう」と思ったユーザーがブックマークしてくれるため、一度の投稿が長期間にわたって見られ続ける傾向があります。これはタイムラインの流れが速いXとは大きく異なるポイントであり、“資産になるコンテンツ”として継続的な効果が期待できます。
さらに、Instagramは拡散構造こそXとは異なりますが、「シェア」「メンション」「おすすめタブ」といった形で、フォロワー以外に広がる導線が複数用意されています。特にリールの場合は“アルゴリズムによるレコメンド表示”が中心となるため、ハッシュタグよりも「動画のテーマ」「視聴維持率」「音源の選び方」といった要素がリーチを左右します。食品業界のように視覚・嗅覚に訴える商材は、この構造と非常に相性が良く、狙った季節感や記念日を軸にリーチを伸ばしやすいジャンルです。
さらにECや店舗販促との連動がしやすいのもInstagramの魅力です。ストーリーズにリンクを載せたり、スタンプで予約ページへ誘導したり、投稿の最後に「〇月限定メニューはこちら」と動画内で案内したりと、SNS上の認知から購買の行動導線までをひとつの流れとして作りやすくなっています。
このように、食品業界がInstagramを活用する意義は単なる“認知拡大”にとどまりません。リールによる視覚的な魅力訴求、保存による長期的な接触、アルゴリズムによる拡散、そしてストーリーズからの購買導線。この4つの要素が組み合わさることで、季節イベントや「今日は〇〇の日」といった日常的なネタも、“日々の話題づくり”から“売上につながる資産型施策”へと進化させることができるのです。
第2章:季節イベントをInstagramで売上につなげる方法
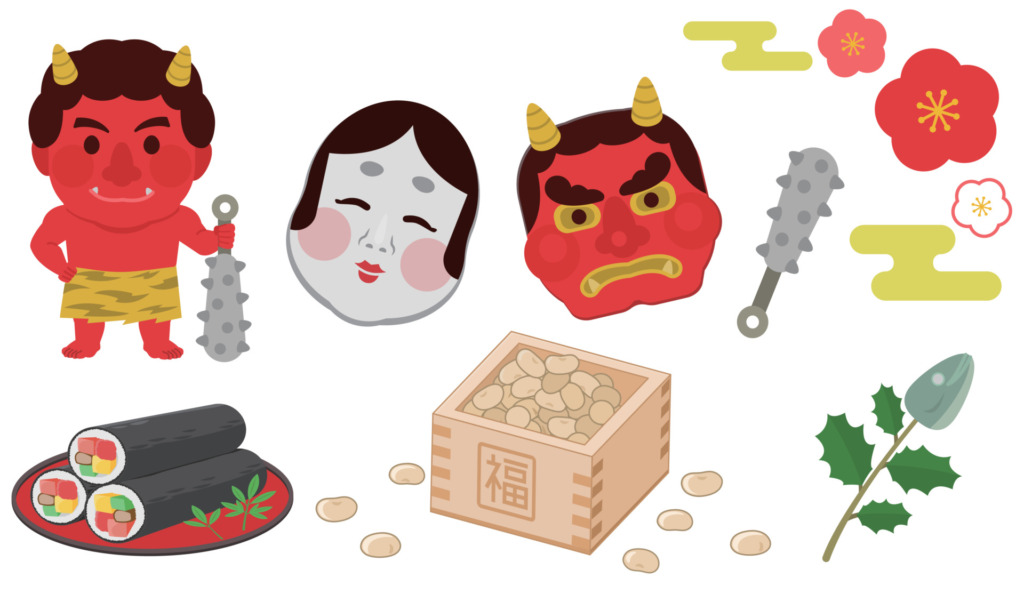
食品業界における季節イベントは、Instagram運用と最も相性の良いテーマのひとつです。日常的な情報を発信するだけではユーザーの印象に残りにくい一方で、「ハロウィン」「クリスマス」「母の日」「夏の土用」「〇〇フェア開催中」などの“特別感のある文脈”を持たせることで、投稿が自然に受け入れられ、購買意欲につながりやすくなります。
中でもリール投稿は、季節の空気感を映像と音で届けられる点に強みがあります。たとえば、ある大手スイーツチェーンでは、ハロウィン限定ケーキの断面をスロー再生で見せるリールに人気の音源を載せ、「今年もこの季節がきました」というコピーを添えて投稿したところ、大きな広告出稿をしなくても自然とシェアが広がり、店舗への来店客から「インスタで見て気になって来ました」という声が多数寄せられました。
一方で、地域密着型の和菓子店のような小規模店舗でも、季節ネタは強力な武器になります。たとえば「節分」「お月見」「彼岸」など、全国規模ではなく地域の生活習慣に寄り添った行事をテーマにすることで、「ここで買おう」という“近さ”を感じてもらえるきっかけになります。Instagramの投稿文やストーリーズには商品そのものを出すだけではなく、「◯◯地方ではこの日には家族で〇〇を食べる習慣があります」といった小さな豆知識を加えると、販促ではなく“文化や物語としての投稿”として受け取ってもらいやすくなります。
季節イベントの投稿で重要なのは、「売り込み色を出さないこと」です。単なる「◯◯発売中」では広告として認識されやすいため、まずは「季節感を楽しむ投稿」「視覚的にワクワクする投稿」として成立させることが先決になります。その上で、投稿の後半やストーリーズのリンク導線などで予約や購入への案内を自然に添える形にすると、嫌味なく売上につなげることができます。
また、複数の商品をまとめて紹介する「季節の◯◯ラインナップ紹介」も効果的です。人気の音源に合わせて3〜4商品をテンポ良く切り替えるリールは“カタログの動画版”として保存されやすく、「この中だったらどれが好き?」というキャプションを添えることでコメントも集まりやすくなります。数を並べることで「このお店は季節イベントを大切にしている」という好印象にもつながり、ファン化のきっかけになります。
季節イベントは、単発のキャンペーンで終わらせるのではなく、「毎年恒例のシリーズ投稿」にしてしまうことが理想です。1年目は小さな反応でも、2年目・3年目になると「今年もこの投稿が来た」と待ってもらえる存在になり、ブランドとしての“年中行事”が育っていきます。Instagramはアーカイブを遡って見られる特性があるため、過去の投稿が“歴史”として残る点も活かすべきポイントです。
季節イベントはどの食品ブランドにも平等に訪れるチャンスであり、投稿の見せ方を少し工夫するだけで“話題づくり”から“売上のきっかけ”へと変えることができます。商品そのものだけでなく、「季節を楽しむ体験」を一緒に届ける視点を持つことが、Instagram運用で成果を出す第一歩になります。
関連記事→https://coco-and.jp/blog/food-x-marketing-event-post/
第3章:「今日は何の日」投稿をInstagramで活用する方法

「今日は〇〇の日」という記念日投稿は、Instagram運用の中でも最も取り入れやすく、かつ継続しやすいフォーマットです。特定のイベントや商品発売のタイミングを待つ必要がなく、すでに決まっている記念日カレンダーに沿って投稿できるため、運用担当者にとっても準備がしやすいのが大きなメリットです。
Instagramでは、こうした記念日ネタを単なる情報発信として終わらせるのではなく、「共感」「参加」「シェア」のきっかけに変えることがポイントになります。たとえば「5月9日=アイスクリームの日」であれば、「今日はアイスの日。あなたの定番フレーバーはどれですか?」と問いかけるだけでコメントが集まりやすくなります。ストーリーズ機能を併用し、「チョコ派?バニラ派?」といったアンケートスタンプを載せれば、参加型のコミュニケーションへと発展させることができます。
リールで活用する場合は、冒頭に「今日は〇〇の日」のテロップを入れるだけで、コンテンツの意味が一瞬で伝わります。たとえば「今日はカレーの日」と表示した上で、スパイスを振りかける瞬間や、盛り付け工程をリズミカルに見せる映像をつなげると、それだけで“見たい理由”が成立します。余計な説明をしなくても、記念日という文脈があることで視聴者の理解が追いつくため、短尺動画との相性が非常に良いフォーマットです。
また、「今日は何の日」投稿は“ストーリーズの連載企画化”にも向いています。毎週月曜日は「今週の記念日カレンダー」として「◯◯の日が3つあります」「あなたならどれを投稿に使いますか?」といった形式にすれば、フォロワーは“習慣的に見に来るきっかけ”を持つようになります。食品業界の場合、特に「〇〇の日」が多く設定されているため、この形式を続けるだけで運用カレンダーが自然に回りやすくなるのも利点です。
さらに応用的な活用として、「今日は〇〇の日」投稿をUGC(ユーザー生成コンテンツ)に発展させる方法があります。たとえば「今日は〇〇カレーの日。ハッシュタグをつけて、あなたのカレー写真を教えてください」と呼びかけることで、ユーザー投稿を巻き込むことができます。実際に、あるレトルトカレーブランドは「#うちの具材自慢カレー」というタグを設け、「毎週1名、公式がリールで紹介します」と宣言したことで多くの投稿が集まりました。投稿する側にとっても「紹介される可能性がある」というだけでモチベーションが高まり、ファン参加型の仕組みとして長期間継続することができます。
「今日は〇〇の日」投稿は、一見すると小さなネタのように思われがちですが、積み重ねることでブランドとの“習慣的な接点”を生み出せるのが最大の価値です。日常の会話に溶け込むように投稿することで、「今日もこのアカウントが面白い記念日を教えてくれた」という安心感や親近感が蓄積されていきます。食品のように生活に密接したジャンルだからこそ、小さな話題の積み重ねがファン形成と購入のきっかけに直結します。
第4章:Instagram活用の企業事例

季節イベントや「今日は〇〇の日」を活用したInstagram運用は、企業規模を問わず成果に直結しやすい手法です。ここでは、大手ブランドから個人店舗まで、実際に成果を出している活用パターンをいくつか紹介します。
大手スイーツチェーンによる期間限定リール活用
全国展開しているスイーツチェーンでは、ハロウィンやクリスマスといった大型イベントのたびに、限定商品の断面映像をリールで公開しています。印象的な音源に合わせてケーキを切る瞬間やトッピングのクローズアップをテンポよく見せることで、広告色を出すことなく“視覚的な誘惑”を演出しているのが特徴です。キャプションでは販売情報をあえて最小限に抑え、「今年もこの季節がやってきました」という共感型のメッセージにとどめることで、視聴者からのシェアが自然に広がり、来店客の中にも「リールで見て気になった」という声が多く挙がっています。
EC食品ブランドによる「開封動画×記念日」戦略
冷凍食品のD2Cブランドでは、「今日はカレーの日」「〇月〇日は麺の日」といった記念日に合わせて、商品を開封して温める様子をリールで公開する手法を定番化しています。調理工程をそのまま映すのではなく、“湯気が立ち上がる瞬間”や“パッケージを開けたときの音”など、五感に訴えるカットを中心に構成しているのがポイントです。また、キャプションの最後に「あなたの〇〇の日はどんなメニューでしたか?」と添えることで、コメント欄がちょっとした投稿広場のようになり、UGCが自然に蓄積される仕組みができています。
地域密着型飲食店の「文化紹介型ストーリーズ」
地方の和菓子店や飲食店では、「◯◯県ではこの日に〇〇を食べる文化があります」といった“豆知識付きのストーリーズ”が好反応を得ています。商品そのものを紹介するのではなく、その背景にある文化や家族の習慣を映像とテキストで丁寧に伝えることで、宣伝ではなく“物語”として受け取ってもらえるのが大きな利点です。地域外のユーザーからも「知らなかった」「その文化好きです」といったコメントが寄せられ、オンライン上でファンコミュニティが広がっています。
UGCを巻き込む「紹介企画型リール」
ユーザー参加型の事例としては、「あなたの◯◯を教えてください」というテーマで投稿を募集し、集まった内容をリールで紹介する形式が効果的です。ある飲料メーカーは「#私の乾杯スタイル」というハッシュタグを設定し、ユーザーの投稿を毎週1件ずつ公式が紹介する取り組みを継続しています。このように“取り上げられる可能性がある”という仕組みを用意すると、単なるキャンペーンではなく“参加する楽しさ”が生まれ、結果的に投稿数が増え続けるサイクルができます。
関連記事→https://coco-and.jp/blog/ec-food-x-campaign-ugc/
第5章:Instagram運用で効果を最大化するためのポイント

季節イベントや「今日は〇〇の日」の投稿は、そのまま発信するだけでも一定の効果はありますが、成果を安定させるためには「再現性のある型」として運用する視点が欠かせません。単発で終わらせるのではなく、どの担当者でも継続できる“仕組み化”を意識することで、発信コストに対して得られるリターンを最大化できます。
まず重要なのは、投稿テーマを“思いついた順”にではなく、あらかじめカレンダー形式で整理しておくことです。たとえば「1月は〇〇の日が5つ、バレンタイン関連投稿は2週目から開始」など、月初の段階で「イベント候補」「投稿タイミング」「使用する動画や画像の構成」を軽く決めておくだけでも、直前での迷いがなくなり、安定した運用につながります。特にInstagramは画像や動画の制作に時間がかかるため、計画性があるだけでクオリティも継続率も自然と高まります。
次に意識すべきは「見られる投稿」ではなく「残る投稿」を作る視点です。食品業界の場合、単なる“告知型の宣伝”よりも、“保存したくなる投稿”のほうが成果に直結します。たとえば「今日のレシピ紹介」ではなく「来週の弁当に使える5選」のように、未来に向けた用途を想像できる形にすると保存率が高まり、後日になっても閲覧され続ける資産型コンテンツになります。日付が過ぎても見られる投稿は、それだけで運用の効率を大きく押し上げます。
さらに、Instagramでは“運営側の反応”が投稿の価値を決めると言っても過言ではありません。コメントやストーリーズの返信に企業がきちんと反応しているアカウントは、「見てくれる」「向き合ってくれる」という印象が積み重なり、親近感と信頼感が強くなります。とくに食品のように生活に密着する商材では、「買ってくれてありがとう」「その食べ方おいしそうですね」という一言に、広告以上の効果が宿ることがあります。発信するだけでなく“応答する姿勢”を見せることが、ファンづくりに直結します。
最後に、データの振り返りも欠かせません。リーチ数や保存数、プロフィールアクセスなどを小さく記録しておくだけでも、自社の“勝ちパターン”が見えてきます。たとえば「音源をつけたほうが反応が伸びる」「調理工程より完成品のほうが保存される」など、ジャンルを問わず傾向は必ず現れます。分析といっても難しいことをする必要はなく、「また同じ型で作れるか」を判断する材料として数字を見るだけで十分です。運用を“検証と改善のループ”として捉えることで、担当者の勘やセンスに依存しない成果が積み上がります。
まとめ:季節ネタは「話題づくり」ではなく「資産づくり」に変えられる
季節イベントや「今日は〇〇の日」といったテーマは、単なる話題提供のためのネタではありません。Instagram運用においては、投稿の見せ方と流れを整えるだけで、「売上につながる接点」や「ファンとの習慣的な交流のきっかけ」へと変えることができます。
ポイントは、一度の投稿で完結させず、「シリーズ化」「テンプレ化」していくことです。年に1回のイベントでも、毎年同じタイミングで発信し続ければ、それは企業にとっての“年中行事”となり、ユーザーにとっての“楽しみにしている恒例企画”になります。単発のキャンペーンではなく、“記憶に残る習慣”としてブランドを定着させることができれば、広告費に頼らずとも自然に口コミやリピート購入が生まれるようになります。
食品業界は、生活者の「食べたい」「知りたい」「話したい」という感情に寄り添いやすいジャンルです。Instagramのリールやストーリーズを活用すれば、そうした感情に寄り添う発信を日常的に続けることができます。大きな施策を一気に行うのではなく、小さな投稿を積み重ねることで、“ファンにとっての当たり前”をつくる。それこそがInstagram運用における、最も強く、最も再現性の高い戦略となります。
・関連記事