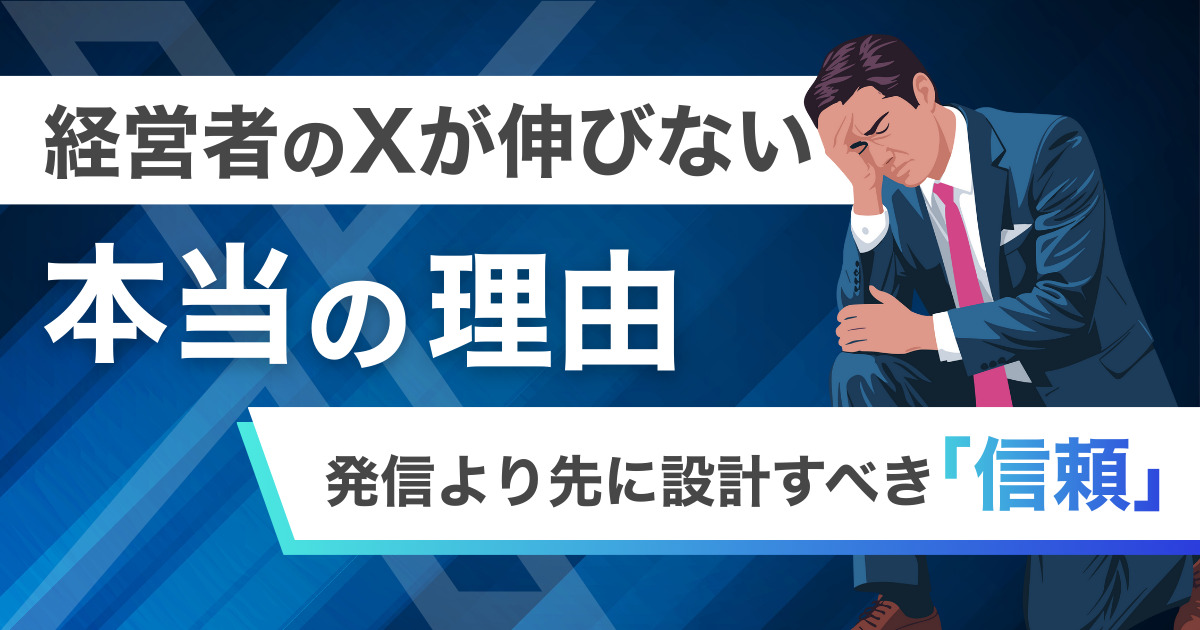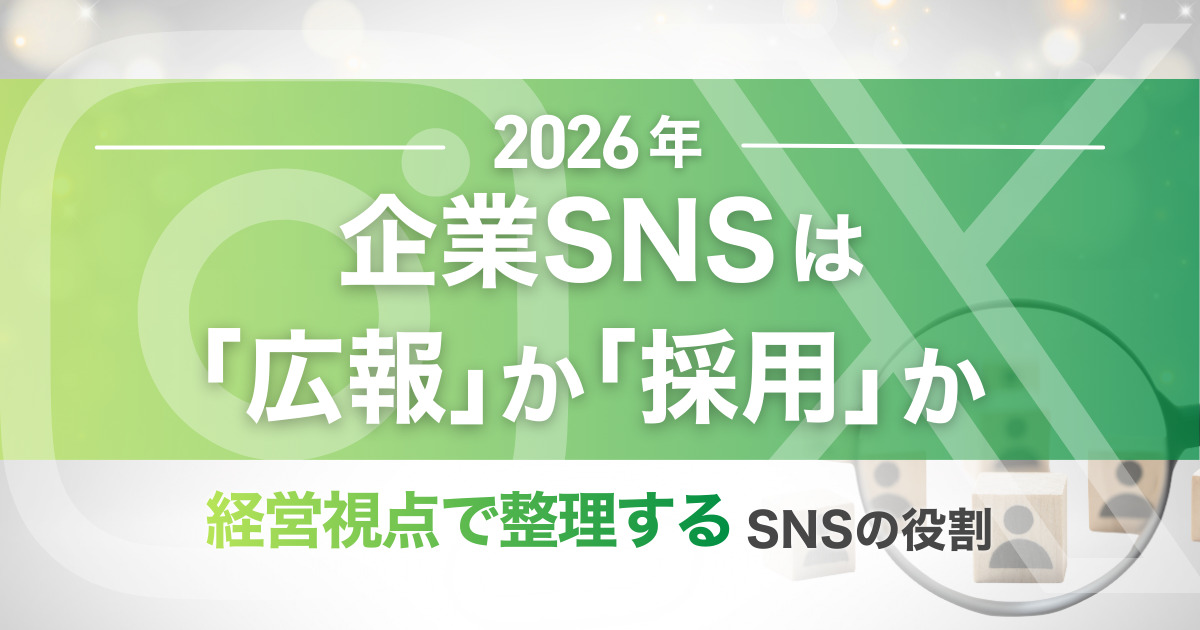2025.10.20
食品ブランドのInstagramキャンペーンでUGCを量産する方法|「#アレンジ」「@メンション投稿」を軸にした拡散設計

Instagramで商品キャンペーンを実施しても、「いいねは付くのに投稿にはつながらない」「応募フォームやDMで終わってしまい、タイムラインに広がらない」という悩みは、食品業界で特によく聞かれます。どれだけ魅力的な商品であっても、ユーザーのフィードやストーリーズに自然に登場しない限り、認知の広がり方には限界があります。
食品カテゴリの場合、ユーザーの投稿を通じて「どのタイミングで食べられているのか」「どんなアレンジが楽しまれているのか」が可視化されることで、商品価値が生活シーンの中に溶け込みやすくなります。そのため、応募形式を“見るだけ・応募するだけ”で完結させるのではなく、“自分自身が食べた・作った・好きだとアピールできる形”に設計することが重要です。
InstagramでUGCを増やす鍵は、「#アレンジ」「#今日のごはん」「#〇〇好きと繋がりたい」といったタグ文化を活かしながら、ユーザーが“投稿すること自体を楽しめる導線”を用意できているかどうかにあります。本記事では、食品ブランドが実践しやすい形で「#タグ付け」「@メンション投稿」を活用した参加型キャンペーンの設計方法を整理します。
目次
第1章 食品カテゴリのInstagramでUGCが生まれるタイミングとは?

食品カテゴリでUGC(ユーザー生成コンテンツ)を増やすためには、「ユーザーがどのような瞬間に食べ物を投稿したくなるのか」を理解することが出発点になります。プレゼント企画やクーポン配布といったインセンティブ型の施策も有効ですが、単に「応募条件:〇〇を付けて投稿してください」と呼びかけるだけでは、投稿は自然には増えません。
食品に関する投稿は、以下の3つの動機によって発生することが多くあります。
① 「自分の好みを誰かに共有したい」と感じたとき
「今日のおやつ」「最近ハマっている食べ方」「推しの冷凍食品」など、自分が好きなものをシェアしたくなる瞬間です。このタイプの投稿は、商品そのものよりも“自分の気持ち”を軸にしているため、強制的に頼まれて投稿するのではなく「自分から発信した」という感覚を大切にする設計が効果的です。ハッシュタグも「#〇〇部」「#〇〇好きと繋がりたい」のように“共感できる仲間探し”につながる言葉を使うと参加が増えやすくなります。
② 「人からリアクションが返ってきそう」と感じたとき
食品投稿は、他ジャンルと比べてリアクションが得やすい傾向があります。「美味しそう」「どこで買えますか」のようなコメントが想定できる場合、ユーザーは自然と投稿する動機を持ちやすくなります。特に「アレンジ投稿」「今日の朝ごはん」「冷凍食品で作ったとは思えない一皿」といった“見てもらいたくなる工夫”が加わることで、UGCの量が大きく変わります。
③ 「取り上げられたら嬉しい」と感じたとき
食品ブランドの場合、企業アカウントがユーザーの投稿をストーリーズで紹介するだけでも大きなモチベーションになります。「投稿してくれた方の中から毎日ピックアップしてご紹介します」「素敵な投稿には公式からいいねをお返しします」といった一文を添えるだけで、参加の温度が明らかに変わります。商品をもらえるかどうかよりも、「ブランドに見てもらえる」「仲間として扱われる」という心理的価値の方が強く働くケースも多く見られます。
このような投稿心理を前提に、キャンペーンの応募条件を「#タグ付け」「@メンション」を軸にした“投稿型の導線設計”へと変えることで、フォロワー数に依存しない拡散構造を作ることができます。次の章では、実際にどのような形式で参加導線を整えればよいのかを具体的に解説します。
関連記事→食品ブランドのX戦略|レシピ動画と調理Tipsでファンを育てる方法
第2章 食品系キャンペーンの応募導線は「#アレンジ」「@メンション」が基本設計になる

食品カテゴリでUGCを増やす際に最も重要になるのは、「どの形式で参加してもらうか」という応募導線の設計です。応募フォームやDMだけで完結させる形式では、参加数がある程度集まっても、その内容がタイムラインに広がらず、キャンペーンそのものが“見えないまま終わる”結果につながります。
食品カテゴリの拡散には、「ユーザー自身のフィード上で投稿されること」が不可欠です。そのための軸になるのが「#アレンジ」と「@メンション」の2要素です。
「#アレンジ」=同じ商品を使う人同士の“連帯感”をつくる導線
食品投稿の多くは「私はこう食べました」「この組み合わせがおすすめです」という、いわば“自分の見つけた正解”の共有です。そのため、「#〇〇アレンジ」「#〇〇のある暮らし」のように「自分の生活スタイルを見せられるタグ」を用意することで、ユーザーは“公式のために投稿する”という感覚ではなく、“自分のこだわりを発信する場”として参加しやすくなります。
また、「#〇〇アレンジ」「#今日の〇〇ごはん」など、ブランド名を直接含めないタグも有効です。商品名を軸にするよりも、「毎日使っている人」「応援している人」として自然に参加できる言葉の方が広がりやすくなります。
「@メンション」=企業に“見てもらえる”安心感とリアクション導線
食品カテゴリのUGCは、メンションの設計によって熱量が変わります。「投稿には @公式アカウント を付けてください」と明示することで、参加者は“自分の投稿がブランドに届く”という安心感を持つことができます。また、企業側もメンションによって投稿を見逃さず、リアクションを返しやすくなるため、ユーザーとの信頼関係が構築されやすくなります。
「投稿してくれた方には順次いいねやコメントをお返しします」「素敵な投稿はストーリーズでご紹介します」という一文を添えることで、“投稿すると何かしらのリアクションがもらえる”という期待が生まれ、参加率が大きく変わります。
2要素を組み合わせることで「自分の投稿がキャンペーンの広告になる」状態が生まれる
- #アレンジ:同じ商品を使っている他の人の投稿が一覧化される
- @メンション:企業との距離が近づき、リアクションの期待が生まれる
この2つが組み合わさることで、「投稿する人が増える」「投稿した人の周囲にも広がる」という循環が発生します。ただ商品を配るのではなく、「投稿そのものを価値に変える」という視点が、食品カテゴリのInstagramキャンペーンでは重要になります。
次の章では、この2要素をどの形式で設計すればよいのかを、フィード・リール・ストーリーズの形式別に整理していきます。
第3章 フィード/リール/ストーリーズ別・食品UGCキャンペーン導線テンプレート

「#アレンジ」「@メンション」を軸にした応募設計は、投稿形式によって伝え方が変わります。食品カテゴリの場合、ユーザーは「映える写真を撮りたい瞬間」「動画で魅せたい瞬間」「気軽に共有したい瞬間」の3種類で投稿行動が分かれます。それぞれのモチベーションに合わせた導線を用意することで、参加のハードルを下げながら自然な広がりをつくることができます。
① フィード(写真・カルーセル)で参加してもらう場合
フィード投稿は「自分のプロフィールに残す価値のあるもの」だけが選ばれる形式です。そのため「アレンジレシピ」「映える盛り付け」「お気に入りの組み合わせ」など、“見せたい”という気持ちに寄り添ったテーマが有効です。
・指定の音源(または「#〇〇」検索で出てくる人気音源)を使用
・冒頭に「〇〇してみた」「〇〇を初購入」などのテロップを入れる
・動画またはキャプション内に @公式アカウント を記載
・ハッシュタグ「#〇〇アレンジ」「#〇〇レビュー」も付ける
・採用された動画は公式アカウントで紹介する旨を記載
事前に「見本投稿」を1つ提示しておくだけで、参加率が大きく変わります。
② リール(動画)で参加してもらう場合
リール投稿は、食品カテゴリにおけるUGC拡散の中心になりつつあります。特に「食べ方・作り方の流れ」「開封〜一口食べる瞬間」「電子レンジ調理のタイムラプス」のような“短くても伝わる体験”はリールとの相性が高い形式です。
・指定の音源(または「#〇〇」検索で出てくる人気音源)を使用
・冒頭に「〇〇してみた」「〇〇を初購入」などのテロップを入れる
・動画またはキャプション内に @公式アカウント を記載
・ハッシュタグ「#〇〇アレンジ」「#〇〇レビュー」も付ける
・採用された動画は公式アカウントで紹介する旨を記載
音源と構成サンプルをセットで提示すると、参加の心理的ハードルが一気に下がります。
③ ストーリーズ(気軽な参加型)で広く集めたい場合
ストーリーズは「今食べている」「冷凍庫にストックしている」など、日常シーンを投稿するのに適した形式です。24時間で消えるため心理的ハードルが低く、最も参加件数が集まりやすい形になります。
・ストーリーズに写真または動画を載せて @公式アカウント をメンション
・スタンプ(質問・投票など)を添えてもOK
・「#〇〇のある暮らし」などのハッシュタグをテキスト入力
・リポストされた投稿は順次公式で紹介
ストーリーズ参加型は「公式に拾ってもらえる期待感」が強く働くため、「○日間は毎日ピックアップ紹介します」と連動させると連日投稿が続きやすくなります。
次の章では、実際に参加率を高めるための呼びかけ文と、食品カテゴリに適したキャプション・構成例を整理していきます。
関連記事→食品業界必見!Xで成功する季節イベント&“今日は何の日”活用法
第4章 食品UGCを増やす“呼びかけ文”とキャプション・構成テンプレート
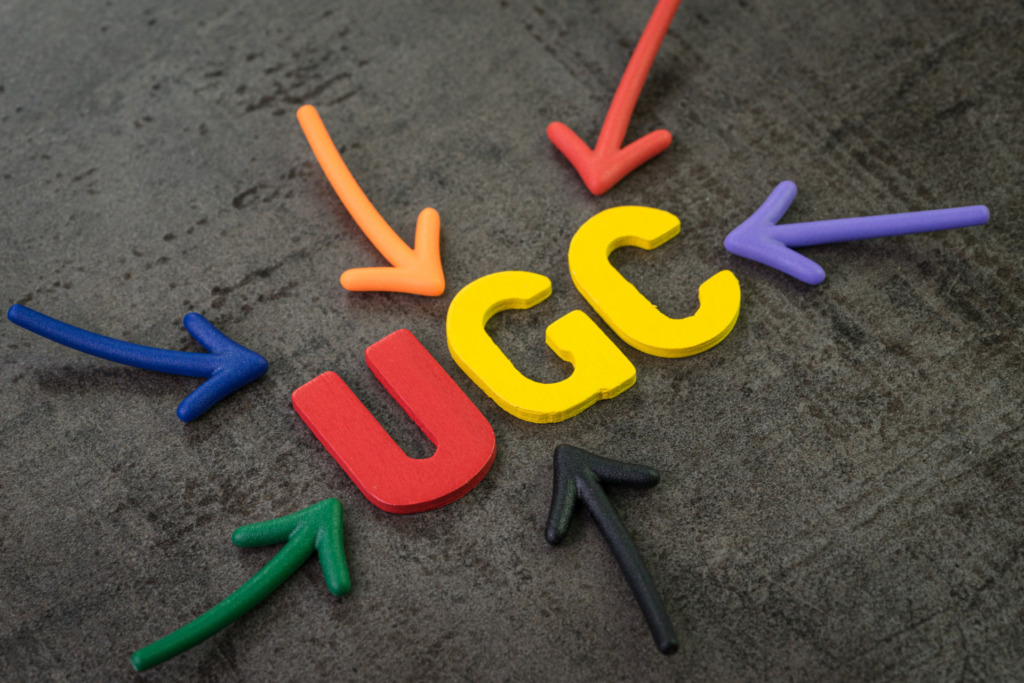
キャンペーンの設計が整っていても、「どのように呼びかけるか」で参加数は大きく変わります。特に食品カテゴリの場合、「写真を撮ること自体は苦ではないが、どんな言葉を添えて投稿すれば良いか分からない」というユーザーが多く存在します。呼びかけ文を工夫し、投稿時の“迷い”を減らすことで、参加率と継続率を同時に高めることができます。
① 参加ハードルを下げる“許可型ワード”
| 意図 | 呼びかけ例 |
|---|---|
| 「これでも参加していいのかな?」という不安を解消する | ・写真1枚だけでも構いません ・文字なし・映える写真でなくても大丈夫 ・料理が苦手でもOK / コンビニアレンジでも歓迎 |
| 「手間がかかりそう」と思わせない | ・普段の食べ方で大丈夫です ・加熱前でもOK / パッケージのままでも結構です ・盛り付けは自由です |
② 承認・紹介される期待を高める“プラス要素型ワード”
| 意図 | 呼びかけ例 |
|---|---|
| 「投稿したら見てもらえる」期待を作る | ・投稿にはすべて目を通します ・素敵な投稿はストーリーズでご紹介します ・いいねやコメントもお返しします |
| 「選ばれなくても得になる」安心感を作る | ・参加者には限定レシピPDFをお送りします ・ピックアップ投稿は後日まとめてご紹介 |
③ 投稿フォーマット例を提示することで“何を書けばいいか迷わない状態”を作る
■ フィード/カルーセル投稿例(テンプレート表示用)
📸 1枚目:完成写真
📸 2枚目:アレンジ前or調理途中(任意)
📝 キャプション例:
「〇〇(商品名)に〇〇を加えてみました。
この組み合わせが最近のお気に入りです。」
@公式アカウント を記載
#〇〇アレンジ #〇〇のある暮らし を記載
■ リール投稿例(構成テンプレート)
① 冒頭テロップ「〇〇を使って今日の◯◯を作ります」
② 調理 or 盛り付けの様子(5〜10秒)
③ 最後に一口食べる or テーブルに置くカット
@公式アカウント を記載
#〇〇アレンジ #〇〇レビュー を記載
■ ストーリーズ参加例
① 写真または動画を投稿
② 「#〇〇のある暮らし」テキスト入力
③ @公式アカウント をメンション
④ (任意)スタンプ「👍」「これ食べたことある?」など
または動画を投稿 ② 「#〇〇のある暮らし」テキスト入力 ③ @公式アカウント をメンション ④ (任意)スタンプ「👍」「これ食べたことある?」など
このように、「呼びかけ文」「許可ワード」「フォーマット例」の3点セットを揃えることで、ユーザーは“参加してもいいか迷う”のではなく“どう投稿しようか考える段階”に移ります。UGCの量だけでなく、自然で質の高い投稿が安定的に集まるようになります。
次の章では、集まったUGCをどのように“公式側が回収し、さらに波及させるか”という二次拡散の設計について整理します。
第5章 UGCは「集めたあと」が本番になる──二次拡散と回収の設計

キャンペーンでUGCを集めることに成功しても、投稿を集めただけで終わってしまうと、その後の広がりが生まれません。食品カテゴリの場合、「投稿してもらったあとに企業側がどう扱うか」によって、参加の満足度と次回のリピート率が大きく変わります。
ここでは、集まったUGCをどのように“回収”し、“さらに波及させるか”という二次拡散の設計ポイントを整理します。
① ストーリーズで「紹介リレー」を行う
UGCの回収方法として最も効果的なのが、「投稿をストーリーズで紹介する」形式です。ただし単にリポストするだけではなく、「連続したストーリーズ企画」として扱うことで、他のユーザーの“後追い参加”を促すことができます。
紹介の組み立て例:
▼1枚目:〇〇チャレンジの投稿が続々届いています
▼2枚目〜:投稿を順にリポスト(1〜3件/日)
▼締め:明日もご紹介します / まだまだ募集中です
ストーリーズを「連続企画」にすることで、見ているだけのユーザーにも参加のきっかけが生まれます。
② 「まとめ投稿」や「ピックアップ動画」で再編集する
UGCが一定数集まった段階で、企業側が再編集してフィードやリールでまとめて紹介する形式も有効です。
例:
- 「#アレンジ選手権 ベスト10」カルーセル投稿
- 「みんなのアレンジをまとめてみました」リール動画
- 「〇〇部の1週間の食卓」スライド形式
ユーザーは「自分の投稿がまとめに入るかも」という期待を持ち、継続的に参加しやすくなります。
③ UGCを“商品開発のアイデア源”として扱う姿勢を見せる
食品カテゴリでは、UGCがそのまま「ブランドへの意見」になります。投稿を見た上で、
- 「こちらのアレンジは来月の公式レシピとして紹介予定です」
- 「この食べ方は社内でも話題になりました」
といった一言を添えるだけで、ユーザーは「参加してよかった」という実感を得ます。投稿者との交流は必ずしも全員に返す必要はなく、「いくつかの投稿にだけ丁寧なリアクションを返す」だけでも、他のユーザーに好印象が広がります。
UGCは「投稿してもらう」ことではなく、「投稿したことを喜んでもらえる」ことがゴールになります。回収と紹介を丁寧に設計することで、単発のキャンペーンではなく「継続的に参加したくなるコミュニティ型UGC」へと発展させることができます。
関連記事→EC食品企業のX運用|キャンペーンと口コミ拡散を両立させる戦略と事例
まとめ UGCは“お願い”ではなく“設計”で生まれる
食品カテゴリのInstagram運用では、キャンペーンの成否は「どれだけ多くのユーザーに参加してもらえるか」ではなく、「どれだけ自然に投稿が広がる構造をつくれているか」で判断されます。UGCは呼びかけやインセンティブで無理に集めるものではなく、“投稿したくなる導線”をどれだけ丁寧に整えられるかによって結果が決まります。
本記事で整理したように、食品ブランドがUGCを増やすために押さえておくべきポイントは次の3点です。
● 投稿を集めるのではなく、「投稿したくなる理由」を設計する
・#アレンジ/#〇〇のある暮らし のように「自分の好みを表現できるタグ」にする
・メンションで「必ず見てもらえる」安心感を与える
● 参加を迷わせない“テンプレート”を添える
・写真1枚だけでも良い/作りかけでも良い/パッケージのままでも良い
・キャプション例や構成を具体的に提示しておく
● 投稿後の回収と紹介まで含めてキャンペーンと捉える
・ストーリーズでの紹介リレーを行う
・まとめ投稿やピックアップ動画で二次拡散を設計する
UGCは「やってください」とお願いして集めるものではなく、「やりたくなる構造」を事前に組み込むことで生まれます。食品カテゴリだからこそ、“食べる人の生活に溶け込む導線”を丁寧につくることで、フォロワー数に依存しない広がりが期待できます。
次回のキャンペーン設計に取り組む際は、「投稿してもらう方法」ではなく「投稿したくなる状況とは何か」から逆算して設計することが、UGCを継続的に育てる第一歩になります。
:関連記事
https://gaiax-socialmedialab.jp/post-52887/?utm_source=chatgpt.com
https://www.cubic-corp.co.jp/rakusta/column/sns-campaign-ugg-case?utm_source=chatgpt.com