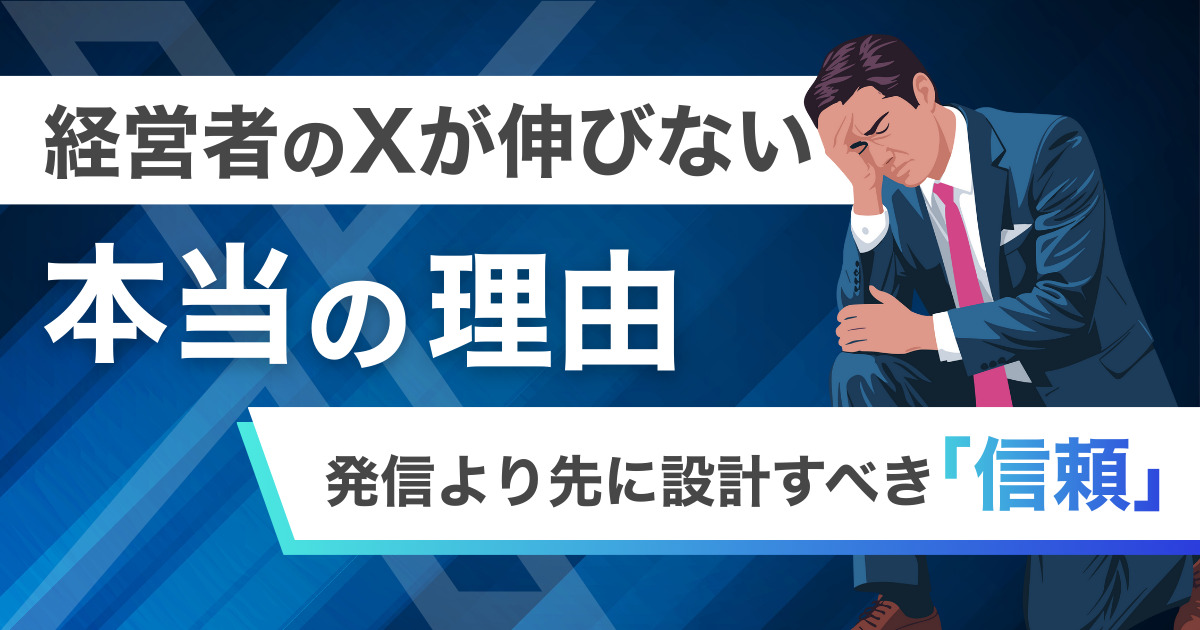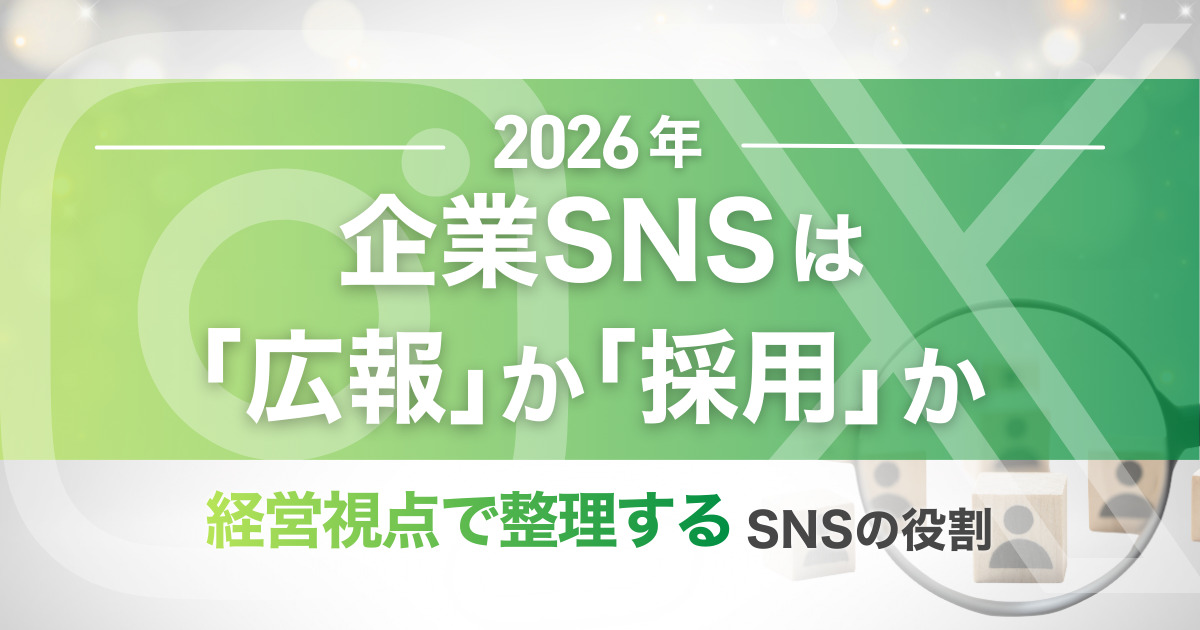2025.10.22
「〇〇を投稿するだけでは遅い」飲食店が伸びるのは“ストーリーズを動かしている店”だった

飲食店でInstagramを活用しているものの、「新メニューを投稿しても反応が伸びない」「スタッフが頑張って撮影しても、フォロワーがなかなか増えない」と感じている方は少なくありません。フィードに写真を投稿しても、更新頻度が月に数回だけになってしまい、「もっと投稿した方が良いのは分かっているが、手が回らない」という声もよく聞かれます。
しかし実際に来店につながっている飲食店の多くは、フィード投稿よりも“ストーリーズの更新”を優先しています。新メニューやイベントの告知を丁寧に作るよりも、「今日の仕込み」「開店前の一枚」「一番乗りのお客さんが来た瞬間」など、リアルタイム性のある発信を短く出し続けることで、日常的に“今この店は動いている”という空気を届けています。
ストーリーズは24時間で消える一時的な投稿ですが、その“消える”という特性こそが飲食店にとって大きな武器になります。本記事では、ストーリーズを「劣化版の投稿」として扱うのではなく、「24時間限定の営業ツール」として活用するための考え方と更新設計を整理していきます。
目次
第1章 ストーリーズが飲食店と相性が良い「3つの理由」

飲食店におけるストーリーズ運用は、単なる補助的な投稿ではなく「最もリアルタイムの反応が返ってくる発信手段」として位置づけるべきです。フィード投稿とは異なる性質を理解することで、ストーリーズを「更新した方がいいもの」ではなく「更新しない方が機会損失になるもの」として捉え直すことができます。
① 「今行きたい」を喚起できる“距離感の近い投稿”になる
ストーリーズはスクロールされるフィードとは違い、ユーザーの画面の最上部に表示されます。しかもタップし続ければ次々と投稿が流れる仕様のため、「タイムラインで見つけてもらう」のではなく「見に行ってもらえる」形式です。
飲食店の場合、「今この瞬間の空気」を伝えるだけで来店動機につながることがあります。
- 「焼き上がりました」という10秒動画
- 「本日最初の一杯入りました」という写真
- 「今日はいつもより〇〇多めに仕込んでいます」
こうした“今の様子”は、フィードの整った写真よりも来店前のユーザーに届きやすくなります。
② 「24時間で消える=その時だけの情報」になる
フィード投稿は「いつ見ても良い情報」を載せる場所ですが、ストーリーズは「今しか見られない情報」を届けるのに適しています。限定性があるだけで、情報の価値が変わります。
- 「10食限定ランチ」
- 「あと1席だけ空いています」
- 「このあと雨が降りそうなのでテラス席の方はお早めに」
こうした情報は、フィードで投稿しても手遅れになるケースが多く、ストーリーズでこそ機能する内容です。「消えるからこそ信頼される情報」として成立します。
③ “更新している店”という安心感そのものが来店動機になる
飲食店のSNSを見たときに、多くのユーザーは「どんな料理か」だけでなく「最近も営業しているか」「今日は行っても混んでいないか」などを確認しています。フィードに数週間投稿がないと、実際には営業していても「やっているのかな?」と不安に思われることがあります。
しかしストーリーズが毎日更新されていれば、それだけで“今日も元気に動いている店”という印象になります。内容が簡単な一枚でも、見ている側にとっては「この店はいつでも覗ける距離にある」という安心材料になります。
これら3つの理由から、飲食店におけるストーリーズは「頻度ではなく、呼吸に近い更新リズム」で運用することが重要になります。次の章では、どのような内容をどのくらいのペースで更新すれば良いのかを具体的に整理していきます。
関連記事→外食・飲食店のX活用|リアルタイム投稿で集客につなげる具体戦略
第2章 ストーリーズ更新の最適な“頻度”と“内容バランス”

ストーリーズを効果的に活用するためには、「どのくらいの頻度で、どんな内容を出せば良いのか」を明確にしておく必要があります。更新の目的は「すべての投稿で反応を取ること」ではなく、「常に誰かの視界に入っている状態を保つこと」です。そのため、1本ごとの完成度よりも、日々の更新リズムを整えることが優先されます。
① 理想は“毎日1〜3本”。少なくても“週5日以上”が目安
飲食店のストーリーズは、月数回の投稿では認知の循環が起きません。常連客に近いフォロワーであっても、ストーリーズを見ない日が普通にあります。そこで、最低限の更新目安として以下のように設定しておくと運用しやすくなります。
| 更新頻度の基準 | 状態 |
|---|---|
| 毎日1〜3本 | ベスト。日常的に「動いている店」と認識される |
| 週5日以上 | 実用ライン。来店前のチェック対象として維持できる |
| 週3日以下 | 認知が断続的になり、存在が忘れられやすくなる |
投稿時間は「営業開始前」「ランチタイム」「閉店後」のどれかに固定すると習慣化させやすくなります。
② ストーリーズの内容は“3種類のバランス”で考える
更新ネタが続かない原因は、「何を出すべきかを毎回悩むこと」にあります。そこで、あらかじめ以下の3カテゴリーに分けておくことで、迷わず更新できるようになります。
| カテゴリー | 内容例 | 投稿比率の目安 |
|---|---|---|
| 日常・仕込み | 仕込み中の様子 / 焼き上がり / 今日の温度感 | 50% |
| お客様・空席状況 | 一番乗りのお客様 / 満席告知 / あと1席だけ | 30% |
| メニュー・告知 | 限定メニュー / 明日の予告 / テイクアウト案内 | 20% |
すべてを完璧に作り込む必要はありません。もっとも反応が大きいのは、むしろ“少し雑なくらいの投稿”です。厨房での音や湯気が入っている動画などは「本当にこの店でしか見られない」リアリティを生みます。
③ 「今日も元気に営業中です」の一文だけでも価値がある
内容が薄く感じられる日でも、「本日も11時から営業しています」「今日はいつもより静かなスタートです」の一文と外観の写真だけで、十分な役割を果たします。ユーザーが見ているのは「どんな投稿か」ではなく、「いまこの店は動いているかどうか」です。
「更新できなかった日」は空白として残りますが、「軽く一枚でも出した日」は記憶として残ります。ストーリーズ運用は、発信のクオリティではなく、“呼吸のような更新習慣”で評価されます。
次の章では、「ストーリーズの中身をどう工夫すれば反応が高まるか」という演出面の設計について整理します。
第3章 反応が高まるストーリーズ演出──「文字・リアクション・動き」を加えるだけで変わる

ストーリーズは写真や動画を載せるだけでも機能しますが、少しの工夫を加えることで「見られるだけの投稿」から「行動を促す投稿」に変えることができます。演出と言っても、デザイン性の高い編集や装飾を行う必要はありません。日常投稿に“視線を止める要素”を一つ加えるだけで十分です。
① テキストを加えるだけで“実況性”が生まれる
ストーリーズで最も簡単にできる演出が、写真や動画の上に短いテキストを載せる方法です。実況するような一言を添えるだけで、情報が「見るもの」から「感じるもの」に変わります。
使えるテキスト例:
- 「今焼いています」
- 「あと5分で完成」
- 「今日の仕込みはここまで」
- 「あと1席だけ空いています」
- 「雨の日はゆっくりめです」
このような言葉は、情報として正確である必要はなく、「その瞬間の空気を共有する」役割を果たすだけで十分です。
② スタンプ・リアクションを入れると“参加したくなる心理”が働く
ストーリーズでは、スタンプやリアクション機能を入れるだけで閲覧者の行動が大きく変わります。
よく使われるスタンプ例:
| スタンプ | 使い方の例 |
|---|---|
| 質問スタンプ | 「今日のおすすめ聞きたい方いますか?」 |
| 投票スタンプ | 「どちらのメニューを先に売り切れそう?」 |
| 絵文字スライダー | 「この焼き加減どうですか?」 |
こうしたスタンプは、回答の有無に関わらず、“反応を促す”という役割を果たします。見るだけの投稿ではなく、「参加したくなる投稿」になります。
③ 動きのある動画は長さ5〜10秒で十分
調理中の湯気や、揚げ物の音、水を注ぐシーンなど、たとえ1カットでも“動き”が加わるだけで視線が止まります。編集する必要はなく、スマートフォンで撮影したままの動画で構いません。飲食店のストーリーズにおいては、「綺麗な動画」よりも「音と温度感が伝わる動画」の方が保存・反応率が高くなる傾向があります。
このように、ストーリーズの演出は「作り込む」ことではなく、「空気を伝える要素を1つ加える」ことです。視覚・文字・音のいずれかが加わるだけで、単なる報告型の投稿から、見る人の記憶に残る投稿に変わります。
次の章では、ストーリーズの運用を“集客導線”として成立させるための活用方法を整理します。
第4章 ストーリーズを“集客導線”として機能させる方法

ストーリーズは「更新しておけば良いもの」ではなく、「見た人を行動に繋げる導線」として活かすことができます。特に飲食店の場合、ストーリーズは“予約前の下見”や“入店前の判断材料”として使われていることが多く、フォロワーが抱えている不安や疑問を解消するだけで来店意欲が高まります。
ここでは、ストーリーズを単なる「情報発信」ではなく「来店・予約への橋渡し」として使うためのポイントを整理します。
① ストーリーズに「行動のきっかけ」を埋め込む
情報を見ただけでは行動に繋がりません。そこに「具体的な次の一歩」を示すだけで、来店や予約を想起させる力が高まります。
例:
| 表現の違い | 印象の違い |
|---|---|
| 「今日も営業しています」 | 状況報告で終わる |
| 「今日は比較的ゆったりしています(今すぐ入れます)」 | 今から行っても大丈夫、という許可になる |
| 「このあと◯時〜は混み合いそうです」 | 来店タイミングの判断材料になる |
| 「テイクアウトだけでも大歓迎です」 | 迷っている人の背中を押す言葉になる |
「行動を促す言葉」ではなく、「判断しやすくする言葉」として添えるのがポイントです。
② 自然な形で“予約導線”を添える
ストーリーズにはリンク機能(予約サイト・Googleマップ・公式LINEなど)を挿入できます。飲食店の場合、「予約はこちら」ではなく、「◯時以降は◯席空きます → 予約リンク」など、“ストーリーの流れの中で自然に出す”方がクリック率が高くなります。
例:
- 「このテーブルが19時から空きます(ご予約はこちら)」
- 「雨の日限定のテイクアウト割、LINEから受付中です」
- 「今日中にDMいただければ明日分キープします」
「行動をお願いする」のではなく、「ここから進めば楽ですよ」という導き方にするのが自然です。
③ “後から見返せる導線”としてハイライトを設定する
ストーリーズは24時間で消えますが、ハイライトに残すことで「安心して見返せるメニュー表」や「来店前のガイド」になります。飲食店の場合、以下のようなハイライトが特に効果的です。
| ハイライト名 | 内容 |
|---|---|
| 「初めての方へ」 | 店内の様子・席数・予約方法など |
| 「今日の仕込み」 | 毎日投稿しているストーリーズから印象的なものをまとめる |
| 「空席情報」 | 過去投稿を残しておくことで“更新している店”感を出せる |
| 「お客様の声」 | メンションされた投稿の紹介 |
ストーリーズは“流れる情報”。ハイライトに残すことで“蓄積される資産”に変わります。
次の章では、このストーリーズ運用を習慣化するための“分業・テンプレ化の方法”を紹介します。
第5章 ストーリーズ運用を“続けられる形”にするための仕組み化

ストーリーズ運用は「きれいな投稿を作ること」よりも「止めないこと」が重要です。しかし、店舗運営と並行して毎日投稿を考えるのは負担が大きく、途中で更新が止まってしまう原因にもなります。そこで、ストーリーズを無理なく継続するためには、「誰が・いつ・何を出すか」という仕組みをあらかじめ決めておくことが大切です。
① ネタを“その場で考えない”ためのテンプレ化
毎日更新が止まる理由の多くは、「何を撮るかを考えること」に時間がかかるためです。そこで、以下のように“撮影するものをあらかじめ固定”しておくことで、迷いをなくすことができます。
| 曜日 / タイミング | 投稿内容例 | 担当の決め方 |
|---|---|---|
| 開店前(毎日) | 仕込みの様子1枚 | 厨房担当の誰かが撮影 |
| ランチ前(平日) | 空席・本日の予約状況 | ホールスタッフ |
| 閉店後(週2) | 今日の一皿紹介 or 仕込み予告 | 店主 or SNS担当 |
“誰が”、“いつ”、“どこで撮るか”を決めてしまえば、内容は日常の延長で自然に集まります。
② 店舗全員で“スマホ1枚ずつ”を持ち寄る仕組み
SNS担当を一人に任せる形にすると、その人の負担が増え、更新のリズムが偏ります。むしろ、“スタッフ全員が1週間に1枚ずつ撮る”くらいの分担にした方が、自然でリアルな投稿が揃います。
スタッフにお願いするときの一言例:
- 「きれいじゃなくて大丈夫。湯気が写ってればOK」
- 「忙しい時こそ撮った方がリアルで良いです」
- 「動画は3秒でも構いません。音だけでも大丈夫です」
“撮ろうと思った瞬間に撮れる環境にする”だけで、投稿ネタは自然と増えます。
③ 更新ルールを「成果」ではなく「行動」で評価する
ストーリーズは、1本1本の反応を細かく分析する必要はありません。むしろ「毎日更新できているかどうか」「空白の日が減っているかどうか」といった“行動ベースの振り返り”にすることで、運用が止まりにくくなります。
管理しやすいチェック形式の例:
| 日付 | 更新できた? | 本数 | メモ |
|---|---|---|---|
| 10/1 | ✅ | 2本 | 仕込み / 空席情報 |
| 10/2 | ✅ | 1本 | 常連さんの来店 |
| 10/3 | ❌ | – | 忙しくて忘れた |
数値を見るのではなく「穴が空いた日を減らす」という感覚で振り返る方が習慣化しやすくなります。
ストーリーズは「クオリティで勝負する場所」ではなく、「動き続けることで信頼を蓄積する場所」です。継続するほど、その店は“いつでも覗ける存在”になります。
関連記事→EC食品企業のX運用|キャンペーンと口コミ拡散を両立させる戦略と事例
まとめ “動いている店”はそれだけで選ばれる
飲食店のInstagram運用では、フィード投稿のクオリティやフォロワー数よりも、「いまこの店が動いているかどうか」が来店判断に直結します。ストーリーズは、その“いま”を伝えるための最も手軽で効果的な手段です。
ストーリーズは消える投稿ですが、更新され続けている店には「いつでも行ける安心感」と「覗きたくなる距離感」が生まれます。内容は完璧である必要はありません。湯気の上がる一皿、開店前の厨房、空席が1席だけ残っている様子――その一瞬が、宣伝よりも強い来店動機になります。
飲食店のInstagram運用で大切なのは、“発信の質”ではなく“動き続けていること”。
- きれいな写真より、「今日もやっています」の一枚
- 特別なイベントより、「普通の仕込み」の10秒動画
- 丁寧な告知より、「あと1席空いています」の一言
これらを毎日積み重ねることで、フォロワーの中に“いつでも行けるお店”という記憶が定着します。
ストーリーズは「24時間で消える投稿」ではなく、「24時間以内に誰かの記憶に残る投稿」です。今日から「動いていること自体が価値になる運用」を意識し、ストーリーズを店舗の“呼吸”として続けていくことが、ファンづくりと集客の土台になります。
・関連記事
:https://ppr-do.co.jp/instagram-marketing-restaurants/?utm_source=chatgpt.com