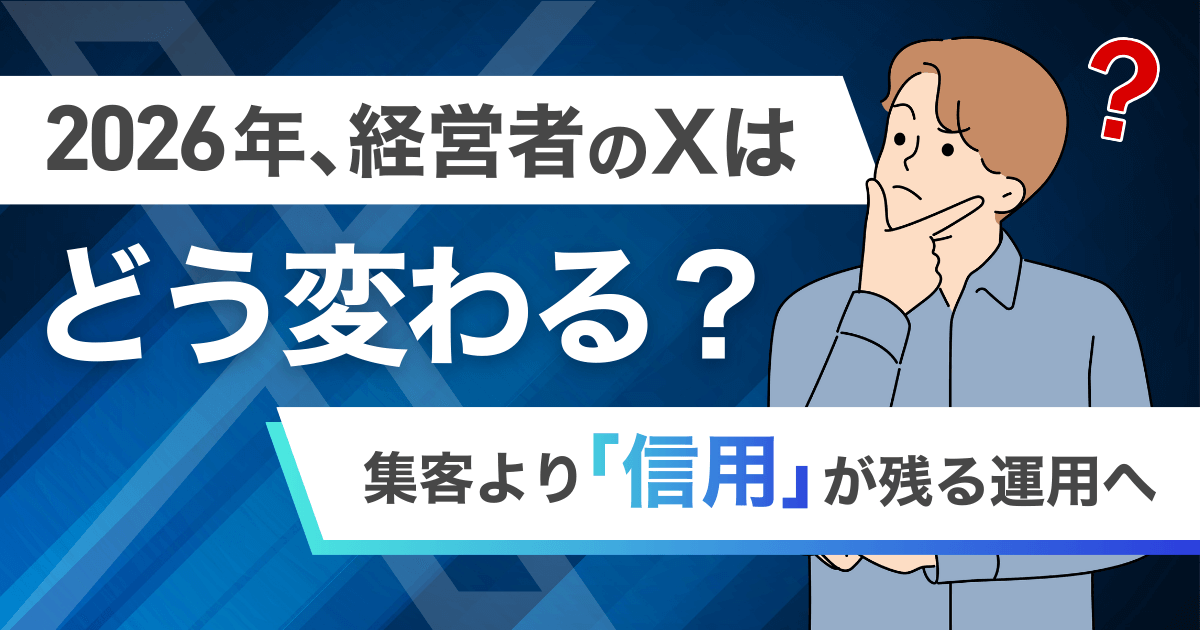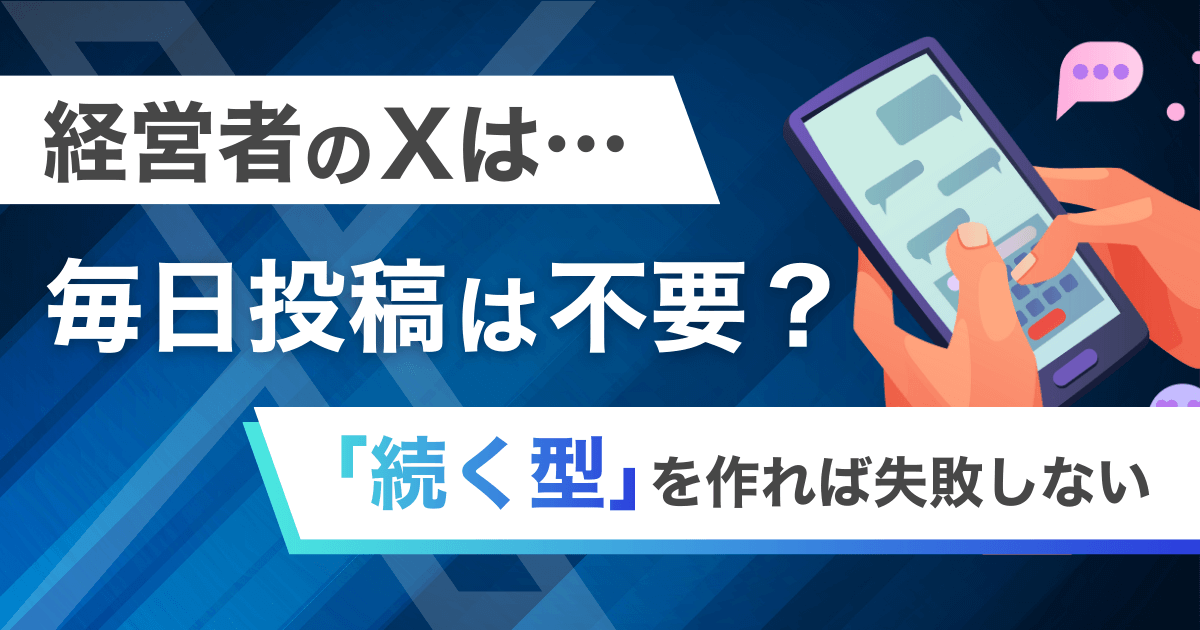2025.10.29
Instagramのプレゼント企画は“リール×メンション”が最強|UGCを横展開させる参加型キャンペーン術

Instagramのキャンペーン運用といえば、かつては「#ハッシュタグ投稿で応募」という形が主流でした。
しかし最近では、ハッシュタグ投稿だけでは拡散が伸びにくく、フォロワー外にリーチしづらい傾向が顕著になっています。
その一方で、注目を集めているのが“リール×メンション”を活用した参加型プレゼント企画です。
ユーザーが自分のリールでブランドをメンションし、公式アカウントがその投稿をリールで紹介する。
この「相互発信の仕組み」によって、UGC(ユーザー生成コンテンツ)が自然に横展開していく流れが生まれています。
特に美容・コスメ・食品など、“体験価値”を伝えやすい業界では、リール上でのUGC活用が一気に加速中です。
リールで紹介されたユーザーは“ブランドに認められた”という喜びから、さらに投稿を拡散。
ブランド側はそのUGCをストーリーズやリールで再編集して、長期的なエンゲージメントへとつなげています。
この記事では、
・なぜハッシュタグ投稿では拡散しにくくなったのか
・リール×メンションを活用したUGC拡散の仕組み
・実際に成果を出している企業のキャンペーン設計法
を整理しながら、“UGCを資産化するInstagramキャンペーン運用術”を詳しく解説します。
目次
第1章:ハッシュタグ投稿だけでは拡散しにくくなった理由

かつてのInstagramキャンペーンでは、「#〇〇キャンペーン」や「#プレゼント企画」といったハッシュタグ投稿が拡散の中心でした。
しかし2024年以降、Instagramのアルゴリズムとユーザー行動が大きく変化し、ハッシュタグ経由での発見・拡散は著しく減少しています。
1.1 “発見タブ”と“リールフィード”が拡散の主戦場に
Instagramのトラフィックの多くは、いまやハッシュタグ検索ではなく「おすすめタブ(発見タブ)」と「リールフィード」から生まれています。
ユーザーが新しい投稿を見るきっかけの約7割以上が、アルゴリズムによるおすすめ表示経由とも言われています。
そのため、どれだけハッシュタグを工夫しても、
・検索するユーザー数が減っている
・同じタグで投稿が溢れて埋もれる
・アルゴリズム評価に直接影響しない
といった理由から、拡散効率が下がっているのです。
1.2 「参加投稿」が分散し、UGCを拾いきれない課題
プレゼントキャンペーンで「#〇〇投稿で応募!」と呼びかけても、UGCが複数タグ・類似ハッシュタグに分散し、企業側が集約・再利用しにくい状況が起きています。
さらに、ユーザーは「自分の投稿が見てもらえるか分からない」と感じやすく、参加意欲も低下しがちです。
結果として、UGCの量は集まっても、“活用できるUGC”が増えないという問題が生まれています。
1.3 アルゴリズムが「関係性の深い投稿」を優先表示
Instagramの表示ロジックは、近年“関係性”を重視する傾向が強まっています。
つまり、ブランドとユーザーの「相互関係」が明確な投稿ほど表示されやすい構造です。
この点で、「@メンション」を含む投稿は、ハッシュタグ投稿よりもはるかに評価されやすい。
アルゴリズム上も「企業とユーザーの関係性がある」と判断され、リールやおすすめタブで上位表示されやすくなります。
関連記事:Instagramのアルゴリズムに好かれる美容アカウントとは?|#タグより重要な投稿構成の作り方
第2章:“リール×メンション”でUGCを横展開させる仕組み

いまのInstagramで、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を拡散させる最も効果的な方法が、「リール×メンション」構成です。
ハッシュタグ投稿が“静的なUGC”だとすれば、リール×メンションは“動的で広がるUGC”。
ユーザーの投稿を起点に、ブランド公式がリールで紹介・再編集することで、拡散が多層的に発生します。
2.1 「#投稿」から「@メンション」へ──UGCの主戦場が移行
従来は、ユーザーが「#ブランド名」で投稿し、企業がその投稿を探して紹介する形が主流でした。
しかし現在は、ユーザーがブランドをメンション(@アカウント名を記載)することで、公式アカウントに直接通知が届き、再利用のスピードが圧倒的に上がっています。
さらにアルゴリズム上、メンションを含む投稿は「つながりのあるアカウントの投稿」として扱われやすく、おすすめタブ・リール面での露出が増えやすい特徴があります。
2.2 “紹介されるかも”が参加意欲を高める心理設計
メンション型のキャンペーンでは、「投稿したらブランドに紹介してもらえるかもしれない」という期待がユーザーのモチベーションになります。
この“期待値設計”が、従来のハッシュタグ投稿との大きな違いです。
たとえば、
- 「#〇〇キャンペーン」よりも「@〇〇をメンションして投稿すると、公式リールで紹介されるかも!」
この一文を入れるだけで、UGCの質と参加率が大きく変わります。
ユーザーは「ブランドとつながる」「自分の投稿が公式に採用される」という体験を得られるため、単なる応募ではなく“参加”に変わるのです。
2.3 公式リールでの“再編集紹介”がUGCを拡散させる
メンション投稿を公式アカウントがリールで再編集して紹介すると、以下のような多層的拡散構造が生まれます。
- ユーザー投稿(UGC) → メンション通知で公式が発見
- 公式アカウントがリールで紹介 → フォロワー外に拡散
- 紹介されたユーザーが再シェア → 新しいUGCが発生
つまり、「UGC→公式→UGC再発生」という循環型の拡散ループが形成されます。
これにより、キャンペーン終了後もUGCが自走的に増え続けるケースもあります。
2.4 リール×メンション施策が向いている業界
特に成果が出やすいのは、以下のような“体験共有型”の業界です。
- コスメ・美容ブランド:使い方や仕上がりをリールで紹介
- 食品・飲料ブランド:レシピ投稿や「食べてみた」動画のUGC化
- ファッションブランド:着こなし投稿をリールで再編集して紹介
- 外食・サロン業界:来店・施術体験を「お客様投稿」として紹介
どの業界にも共通するのは、「ブランドがユーザーの体験を拾い上げて紹介する」ことで、信頼と拡散を両立できる点です。
第3章:参加型プレゼント企画の設計ステップ

「リール×メンション」を使ったキャンペーンは、単なるプレゼント企画ではなく、UGCを量産し、横展開できる仕組みづくりです。
そのためには、参加条件・投稿導線・紹介フローを明確に設計しておくことがポイントになります。
ここでは、実際に成果を出しているアカウントが実践している“5ステップ設計”を紹介します。
3.1 STEP1:テーマ設定|「誰でも参加できる一言テーマ」を決める
キャンペーンテーマは“専門性”よりも“共感性”を重視します。
ユーザーが「自分も投稿できそう」と感じる一言フックが重要です。
例:美容ブランドの場合
- 「私の毎朝メイクルーティン」
- 「推しコスメ見せて」
- 「#ツヤ肌チャレンジ」
例:食品ブランドの場合
- 「おうちカフェ時間」
- 「朝ごはんにこれ食べた」
ポイント: テーマは“ブランドとの自然な接点”を意識する。ブランド名を含めなくても、体験と商品が自然につながるテーマが理想。
3.2 STEP2:投稿条件|「#タグ+@メンション」をセットで必須化
ハッシュタグだけでなく、「@ブランド名」を必須条件にすることで、投稿の発見性と関係性評価の両立ができます。
例文テンプレート
「#ツヤ肌チャレンジ と @〇〇 をメンションして投稿!」
→ 投稿通知がブランド側に届き、UGCを確実に収集できる。
また、応募条件として「リール投稿限定」にすることで、動画での体験表現(=リール拡散アルゴリズム)も活かせます。
3.3 STEP3:紹介ルール|「リールで紹介されるチャンス」を明示する
参加率を上げる最大のポイントは、“投稿が採用される仕組み”を明示することです。
例文テンプレート
「参加者の中から素敵な投稿を公式リールで紹介します!」
→ 投稿意欲+拡散意欲が同時に高まる。
また、「週ごと・テーマごと」に紹介するなど、定期的にUGCを拾い上げるフローを作ると、投稿の継続率も上がります。
3.4 STEP4:プレゼント設計|“共感軸”で賞品を決める
プレゼント内容は「豪華さ」よりも「共感・再現性」を重視します。
UGCを横展開させるためには、**“体験を共有したくなる賞品”**が効果的です。
例:
- 美容ブランド → 新作コスメの先行体験セット
- 飲料ブランド → ブランドオリジナルマグ+ドリンクチケット
- 飲食チェーン → 店舗クーポン+体験投稿を紹介
「プレゼント=次のUGCのきっかけ」にすることで、キャンペーンが“点”ではなく“線”として続きます。
3.5 STEP5:UGC拡散設計|「紹介→再シェア→拡散」を仕組み化
最後のポイントは、UGCを「紹介して終わり」にしないこと。
リールで紹介したユーザーが、自分のストーリーズで再シェアする導線をつくると、参加者全体が発信者化します。
例:
- 公式リールで「@〇〇さんの素敵な投稿をご紹介!」と明記
- 紹介されたユーザーがストーリーズで再シェア
- その投稿を見た別ユーザーが新規参加
この「紹介→再シェア→再参加」の流れが生まれると、キャンペーンは自然にUGCが増えていきます。
第4章:実際に成果を出している企業アカウント事例

“リール×メンション”型キャンペーンは、美容・食品・アパレルなど多くの業界で広がっています。
ここでは、UGCを自然に拡散させ、ファンとの関係性を深めている代表的な3つの企業事例を紹介します。
4.1 コスメブランドA社|リールで「ユーザーの使用シーン」を再編集紹介
A社では、自社の新作コスメ発売に合わせて「#推しコスメチャレンジ」キャンペーンを開催。
参加条件は「#推しコスメチャレンジ+@ブランド名をメンション」。
ユーザーが自分のリールで使用感を紹介すると、A社がそのリールを**“紹介リール”として再編集・再投稿**しました。
投稿構成は、
- 冒頭に「今週のおすすめユーザー投稿」
- 中盤にメンション投稿の抜粋映像
- 最後に「来週も紹介予定!」という予告
という形で、“ユーザーを主役にした発信”に。
結果、通常のブランド投稿と比べてリーチが約2.4倍に伸び、UGC投稿数も前月比**+180%**を達成しました。
4.2 飲料ブランドB社|「@メンション+朝の一杯」で生活シーンを共創
B社では、「#朝の一杯キャンペーン」と題して、ユーザーが朝食時のドリンクシーンをリールで投稿。
条件は「#朝の一杯+@ブランド名」で、優秀投稿を公式リールで日替わり紹介する形式を採用しました。
ここでポイントになったのは、「ユーザーが紹介される仕組みを可視化したこと」。
毎日1件ずつ公式アカウントでリールをアップすることで、参加者が「明日は自分が選ばれるかも」と期待を持続。
キャンペーン終了後も、参加者の約30%が自主的にブランドタグを継続使用する結果に。
4.3 美容サロンC社|来店者のUGCを“二次利用”せず“二次編集”で紹介
C社では、来店した顧客のリール投稿をそのままリポストするのではなく、
スタッフコメント+施術映像を組み合わせた“紹介リール”として再編集。
- 「この投稿をしてくれた〇〇さん、ありがとうございます!」
- 「こんな素敵な仕上がりになりました」
といったナレーションとともに紹介し、ユーザーとの関係性をストーリー化。
この形式は“転載”ではなく“共創”にあたるため、ユーザー側も気持ちよくシェアでき、
「紹介リールがきっかけで新規予約が増えた」という実例も出ています。
4.4 共通点:紹介がUGCの“再生産”を生む
これら3つの事例に共通するのは、
「紹介=終了」ではなく「紹介=次のUGCの起点」になっていること。
紹介されたユーザーは拡散者に変わり、
その投稿を見たフォロワーが次のキャンペーンに参加する。
この“参加→紹介→再参加”の循環が、UGCの横展開を自然に生み出しているのです。
関連記事:美容ブランドが成果を出すXキャンペーン|リポストとプレゼント企画でUGC拡散を加速する方法
第5章:UGCを長期的な資産に変える運用術
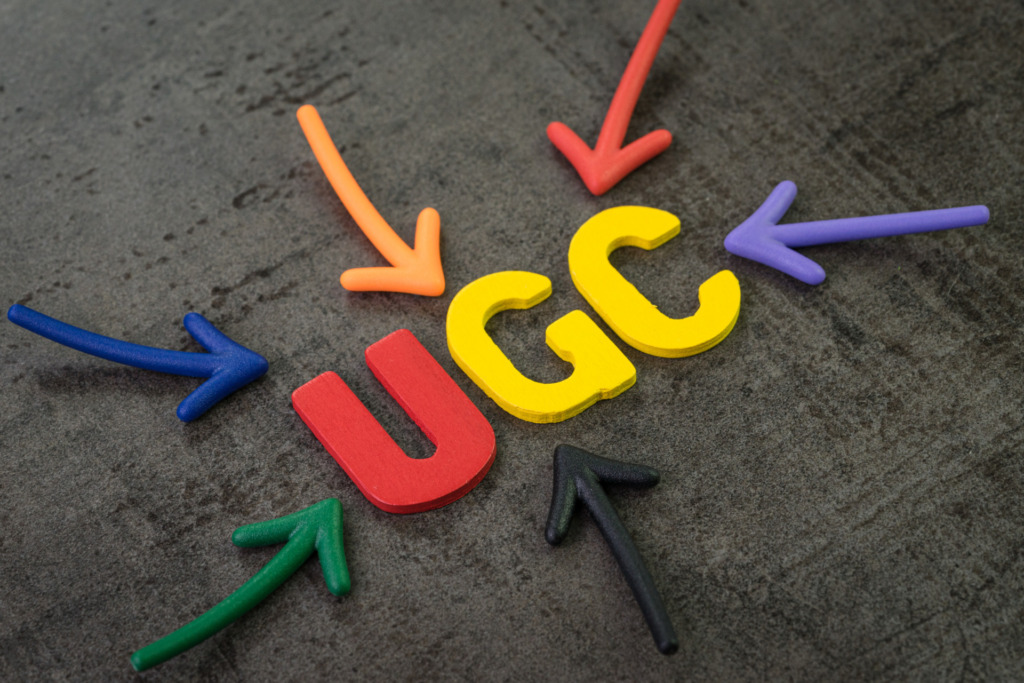
リール×メンション施策の本当の価値は、「一度きりのキャンペーンで終わらせないこと」にあります。
UGCを“流れていく投稿”ではなく、“ブランドの資産”として蓄積できるかどうかが、SNS運用の成否を分けます。
ここでは、キャンペーン終了後も成果を持続させるための3つの運用ポイントを紹介します。
5.1 ハイライト活用で「UGCのショーケース」を作る
UGCを紹介したリールは、キャンペーン終了後にハイライトへ整理・保存します。
テーマごとにまとめることで、後から見に来たユーザーにも「ファンが実際に参加しているブランド」という印象を与えられます。
おすすめのまとめ方
- 「#ツヤ肌チャレンジ投稿集」
- 「お客様の朝ルーティン」
- 「紹介された投稿まとめ」
リールが“ショーケース”として機能することで、新規ユーザーへの信頼導線にもつながります。
5.2 ストーリーズ再掲で「UGCの循環」を維持する
リール紹介後に、該当ユーザーの投稿をストーリーズで再掲すると、UGCが自然に循環します。
再掲の際に「この投稿も紹介しました!」とひとこと添えるだけで、
紹介されたユーザーがストーリーズで再シェアし、再び新しい視聴者へ広がります。
ポイント:
ストーリーズはリールよりもリアルタイム性が高いため、“継続的に動いているブランド”の印象を保ちやすい。
5.3 「UGCアーカイブ」を運用レポートとして活用
UGCを蓄積する目的は拡散だけではありません。
次回キャンペーンの改善・資料化にも活かせます。
- 投稿テーマ別の反応率(保存・コメント)
- どんなメンション投稿が採用されやすかったか
- 再シェア率が高いユーザー層
これらを毎回集計しておくと、「どの構成が最も伸びたか」をデータで把握でき、次の企画で再現できます。
つまり、UGCは“広報素材”であると同時に、“分析素材”でもあるということです。
5.4 “紹介して終わり”ではなく“参加を続けたくなる構造”へ
リール×メンション施策の本質は、ユーザーを発信者に変えること。
紹介を通してファンを巻き込み、「また投稿したい」と思わせる仕組みを継続的に作ることが重要です。
- 定期的なテーマ更新(例:「季節ごとのチャレンジ」)
- 投稿者の声をストーリーズで紹介
- リール内でユーザー名をタグ付けして“登場体験”を演出
このようにUGCを「流れ」で設計することで、ブランド発信がコミュニティ化し、
フォロワーが“関わるブランド”として定着していきます。
まとめ
Instagramのプレゼント企画は、もはや「#キャンペーン投稿で応募」だけでは成果が出にくい時代になりました。
現在のトレンドは、ユーザーが自分のリールで体験を発信し、ブランドがそれを紹介・再編集して拡散させる“リール×メンション型UGC”の仕組みづくりです。
この形式では、ハッシュタグでは届きにくかったフォロワー外にも自然に広がり、
「自分の投稿が紹介されるかも」という参加意欲が継続的に生まれます。
結果として、キャンペーン後もUGCが自走し、ブランドの信頼と認知が同時に拡大していきます。
大切なのは、“投稿を集める”ことではなく、“UGCを広げる仕組み”をデザインすること。
・メンションで関係性を作り
・リールで拡散導線を設計し
・ハイライトとストーリーズで継続的に循環させる
この流れを整えることで、Instagramのアルゴリズムにも評価されやすく、ブランドの発信がコミュニティとして成熟していきます。
関連記事:
・https://www.comnico.jp/we-love-social/ig_campaign?utm_source=chatgpt.com