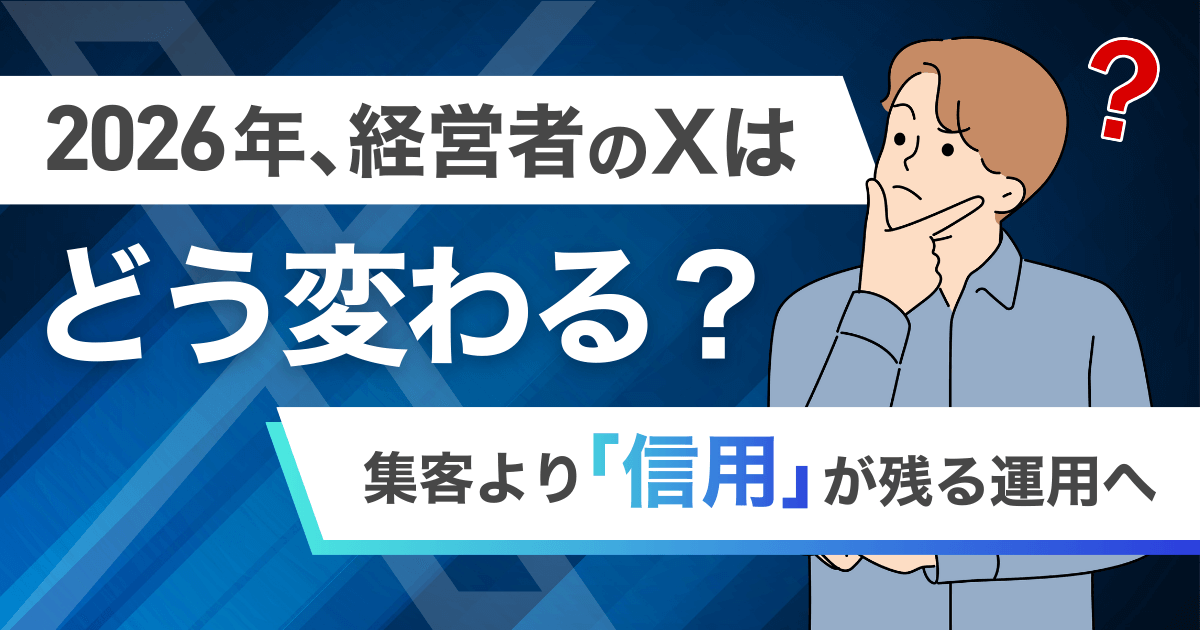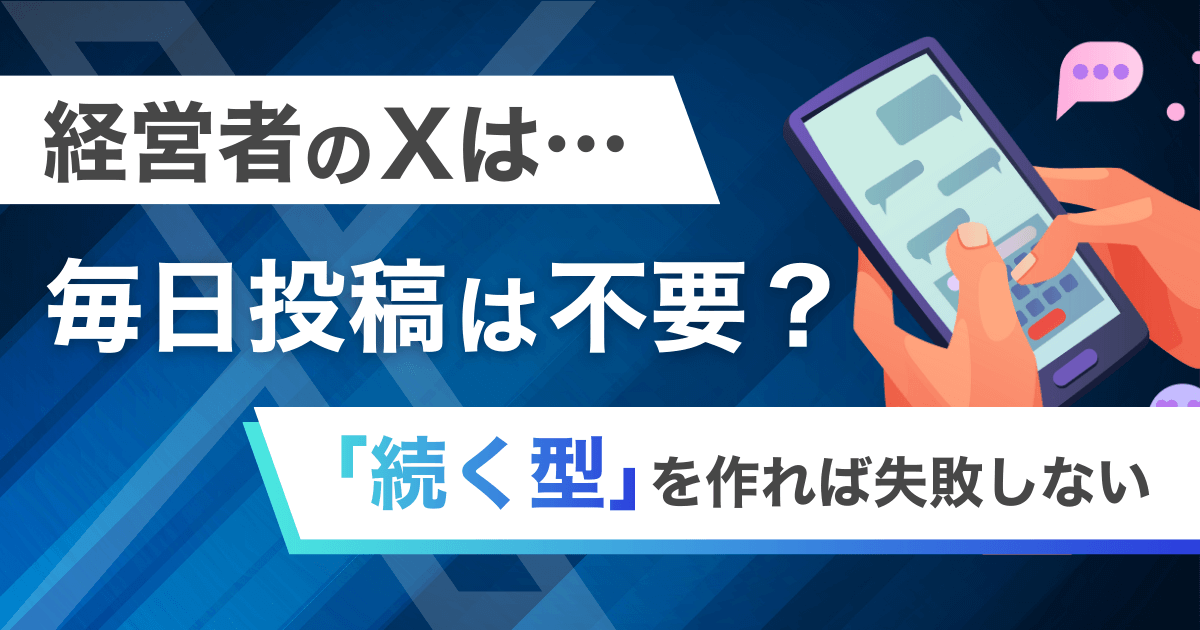2025.11.15
来場予約が増える住宅Instagram運用|ストーリーズで作る“体験型導線”

住宅業界では、モデルハウスや完成見学会など「実際に足を運んでもらうこと」が成約に直結します。しかしSNSの普及以降、チラシやWeb広告だけでは来場数の伸びが頭打ちになっているという声も多く聞かれます。ユーザーが複数の住宅ブランドをオンライン上で比較・検討できるようになった今、どれだけ来場意欲を高める“体験”をSNS上で伝えられるかが鍵となっています。
その中で注目されているのが、Instagramのストーリーズを活用した「来場導線設計」です。ストーリーズは24時間で消えるという特性から、限定感やリアルタイム性を演出しやすく、「今だけ」「今日だけ」という行動のきっかけを作りやすい媒体です。また、動画・写真・テキスト・アンケートなどを組み合わせることで、実際の見学体験に近い形で住宅の魅力を伝えることができます。
本記事では、住宅業界のSNS担当者に向けて、ストーリーズを活用した来場促進の仕組みづくりを解説します。単なる投稿ではなく「体験導線」として設計するポイントを整理し、来場予約や問い合わせにつながる運用のヒントを紹介します。
目次
第1章 住宅業界でストーリーズが集客導線として機能する理由

住宅・不動産業界において、Instagramのストーリーズは「認知から来場予約までをつなぐ中間接点」として非常に有効です。投稿やリールで住宅の魅力を伝えることはもちろん重要ですが、実際に行動を促すためのきっかけとしては、ストーリーズが最もリアルタイムに機能します。
1. 来場検討層が「今見たい情報」を求めている
住宅購入を検討しているユーザーは、単に施工事例を眺めるだけではなく、今どんな家が見られるのか、どんなスタッフが対応しているのかなど、具体的な“来場前の空気感”を知りたがっています。ストーリーズでは、モデルハウスの雰囲気、天気、スタッフの様子といった一瞬の情報をリアルに伝えられるため、静的な投稿よりも信頼感を生みやすい特性があります。
特に、「本日開催」「週末限定」「〇日まで受付」といった時間軸のある情報と相性が良く、ユーザーが閲覧したそのタイミングで来場行動につながりやすいのが特徴です。
2. ストーリーズは“広告”ではなく“日常”として受け取られる
ユーザーのフィード投稿は慎重に見られやすいのに対し、ストーリーズはより気軽にタップして見られる傾向があります。そのため、宣伝的な印象を与えにくく、スタッフの日常や建築風景などを自然に紹介しながら、結果的に来場意欲を高めることができます。
住宅業界では「広告らしくない発信」が信頼につながる傾向が強いため、ストーリーズを活用した“自然な導線づくり”は、他媒体では代替できない強みになります。
3. 24時間という制限が「今行動しよう」という心理を生む
ストーリーズが持つ“消える”という特性は、心理的な行動促進に直結します。ユーザーは「今見ないと消える」「次に見られるかわからない」という限定感に動かされやすく、結果としてリンククリックやメッセージ送信といったアクション率が高まります。これは住宅業界のように“検討期間が長い業種”ほど重要で、日常の中に小さな行動トリガーを積み重ねる効果が期待できます。
第2章 来場につながるストーリーズ構成術(導線の設計)

住宅業界でストーリーズを活用するうえで重要なのは、「どう見せるか」よりも「どこに誘導するか」です。ユーザーは住宅アカウントを眺めながら“興味のきっかけ”を探しており、構成を意識するだけで来場や問い合わせへの導線を作ることができます。
1. 「認知→体験→行動」を3ステップで設計する
ストーリーズは1枚の写真では完結しません。複数枚を組み合わせて流れを作ることで、ユーザーを自然に行動へ導くことができます。住宅業界の場合、次の3ステップ構成が効果的です。
- 認知パート:開催情報や日付を明確に伝える(例:「今週末のモデルハウス公開中」)
- 体験パート:現場やスタッフの雰囲気を伝える(例:「リビングの吹き抜けが人気です」「スタッフが準備中」)
- 行動パート:来場予約やDM誘導を提示する(例:「詳しくはこちら」「ストーリーズから予約できます」)
この3段構成を意識することで、広告的な印象を避けながらも来場への自然な流れを作ることができます。
2. 「人」「空間」「動き」をセットで見せる
住宅アカウントのストーリーズで最も反応が得られるのは、“建物だけでなく人の存在を感じられる映像”です。無人の室内だけでは温度感が伝わらないため、スタッフがドアを開ける、モデルルームを案内するなど、動きのあるカットを取り入れると印象が大きく変わります。
特に効果的なのは以下のような組み合わせです。
- スタッフが笑顔で玄関を開ける → 室内の明るさや空気感が伝わる
- 家具の配置を映した後に「この位置から見える景色が人気です」とコメントを添える
- 外観から室内へ移動する“流れのある映像”で臨場感を出す
こうした「リアルな体験を再現する映像」は、写真中心の投稿では伝えきれない“空気感”を補完します。
3. 導線の終点を「ストーリーズリンク」または「DM」に固定する
どれだけ良い構成を作っても、最終的な行動先が分かりづらいと成果にはつながりません。特に住宅業界では、複数の資料請求・来場予約フォームがあることが多いため、リンク先を1つに統一することが重要です。
- 「詳細を見る」リンク → モデルハウス詳細ページ
- 「DMで相談する」誘導 → スタッフとの直接コミュニケーション導線
- 「来場予約はこちら」 → 外部フォームまたは公式サイト
ユーザーはストーリーズから離脱しやすいため、最も行動してほしい導線を1つだけ明確に置くのが基本です。複数の選択肢を与えるよりも、「これをすれば次に進める」と一目で理解できる形が成果に直結します。
第3章 24時間の限定感を活かす「見せ方と更新頻度」

Instagramストーリーズの最大の特徴は「24時間で消えること」です。
この一時的な特性をどう活かすかによって、来場や問い合わせへの反応率は大きく変わります。住宅業界のように検討期間が長い商材では、日常的な更新の中で“小さな行動トリガー”を積み重ねることが成果を左右します。
1. 「今日しか見られない情報」を入れる
ユーザーがストーリーズを見る理由の多くは、「今見ないと消えるから」です。
この心理を活かし、「今日だけの情報」「現地でのリアルな様子」を盛り込むと、行動意欲が高まります。
たとえば次のような構成が有効です。
- 「今日のモデルハウスの天気が良く、窓から光がきれいに入っています」
- 「この時間帯が一番明るいリビングです」
- 「夕方限定で照明の雰囲気を紹介します」
こうしたリアルタイムな要素は、“今見ている情報”という感覚を生み、ユーザーが現地を訪れるきっかけを作ります。
2. ストーリーズは「頻度」より「リズム」で更新する
多くの住宅アカウントでは、更新頻度を上げようとするあまり、似た内容を繰り返すケースがあります。しかし、ユーザーが求めているのは量ではなく「流れのある情報」です。
たとえば、週ごとにテーマを分けて更新する方法が効果的です。
- 月曜:「今週末の見学会情報」
- 水曜:「現地の準備や天気の様子」
- 土曜:「当日の見どころ」
- 日曜:「ご来場ありがとうございました」の投稿
このように、1週間を1つのリズムとして更新すると、ユーザーに“継続的に動いているモデルハウス”という印象を与えられます。更新内容が連動しているため、見ている側もストレスなく理解できます。
3. スタッフ視点の「一言実況」が信頼を生む
住宅アカウントでは、綺麗な写真よりも“現場感”が伝わる投稿の方が反応されやすい傾向にあります。
「今日は雨ですが屋根の断熱を紹介します」「お客様が一番驚かれるポイントはこちらです」など、スタッフの声を添えるだけで印象が変わります。
単なる写真投稿ではなく、“現場のリアルな声”を組み合わせることで、企業らしさと親しみの両方を持ったアカウントに見せることができます。これは広告的な表現を避けたい住宅ブランドにとって特に効果的です。
関連記事→https://coco-and.jp/blog/instagram-restaurant-stories-strategy/
第4章 来場促進に効果的なコンテンツ(アンケート・Q&Aなど)

ストーリーズの目的は、単に情報を見せることではなく「行動を促すこと」です。住宅業界では特に、見込み顧客との“心理的な距離”を縮めることが来場率を左右します。アンケートやQ&A機能を使って、ユーザーが気軽に関われる形をつくることが有効です。
1. アンケートは「回答のしやすさ」が最優先
アンケート機能は、来場意欲を測るだけでなく“参加のきっかけ”としても活用できます。
ただし、質問内容が重いと回答率が下がるため、最初は軽いテーマから始めることがポイントです。
- 「理想のキッチンはオープン派?クローズ派?」
- 「今気になっているおうちのテーマは?」
- 「今週末の見学会、どの時間帯が気になりますか?」
こうした質問は、「自分の好みを伝えるだけ」という気軽さがあり、ストーリーズの中でスムーズにタップできます。回答結果を後日紹介すれば、ユーザーが再訪するきっかけにもなります。
2. Q&Aで「リアルな疑問」を可視化する
住宅購入やリフォームに関しては、ユーザーが抱える小さな疑問が非常に多くあります。
「見学会って予約が必要ですか?」「子ども連れでも大丈夫ですか?」など、問い合わせるほどではない質問が行動を止めてしまうこともあります。
この“聞きにくい疑問”を解消する手段として、Q&A機能を活用するのが効果的です。
ストーリーズで寄せられた質問を、スタッフが回答付きで再投稿することで、信頼性と親近感の両方を生み出すことができます。さらに、「この質問をしたのは自分かもしれない」と感じるユーザーの行動率も上がります。
3. 「反応をもらう→次の導線に繋げる」仕組みを意識する
アンケートやQ&Aを実施した後は、結果を紹介するだけで終わらせず、次のアクションに繋げることが大切です。
- アンケートの結果に合わせて「人気の間取りを紹介」
- Q&A回答の後に「詳しく知りたい方はこちら」リンクを配置
- 「回答いただいた方限定で最新の見学会情報をお届けします」とDM誘導
このように、参加→反応→行動の流れを一連の体験として設計することで、ストーリーズが単なるコミュニケーションではなく“来場導線”として機能します。
関連記事→https://coco-and.jp/blog/instagram-food-ugc-campaign/
第5章 ハイライト設計で「来場体験を資産化」する方法

ストーリーズは24時間で消えるため、更新の継続だけでは情報が流れてしまいます。
そこで重要になるのが、過去のストーリーズを整理して常設できる「ハイライト設計」です。
ハイライトを上手く活用すれば、来場体験を長期的な資産として蓄積し、初めてアカウントを訪れたユーザーに“安心感と信頼”を与えることができます。
1. ハイライトは「目的別」に整理する
ハイライトを作成するときは、時系列ではなく「ユーザーの行動目的」に沿って分けることが基本です。
住宅業界のアカウントでよく活用される構成例は以下の通りです。
- 「見学会の様子」:当日の雰囲気や会場の様子をまとめる
- 「スタッフ紹介」:案内担当者や設計者の人柄を伝える
- 「お客様の声」:来場者や施主のインタビューを紹介
- 「施工事例」:完成物件をジャンル別に整理
- 「アクセス・予約」:来場方法やフォームのリンク案内
ユーザーが求めている情報にすぐアクセスできるように、ハイライトの順番も「興味を持つ順」に配置するのが効果的です。
2. 「最初に見る人」を意識した並び替えを行う
アカウントを初めて訪れた人は、投稿よりも先にハイライトを閲覧する傾向があります。
そのため、最初に見られるハイライトは「ブランドや雰囲気が伝わる内容」を置くのが理想です。
たとえば「スタッフ紹介」や「モデルハウス紹介」を最前列に配置すると、ユーザーが安心して他のハイライトにも進みやすくなります。
また、カバー画像のデザインも統一しておくと、アカウント全体が整って見えます。
文字だけのシンプルなデザインでも良いので、ブランドカラーを反映させると印象が残りやすくなります。
3. ハイライトは「営業ツール」として活用できる
ハイライトは、単なるまとめ機能ではなく、スタッフが接客時に使える“営業ツール”にもなります。
来場者に「こちらのハイライトで施工例がご覧いただけます」と案内すれば、実物を見せられない時間帯やオンライン対応時にも役立ちます。
また、DM対応やオンライン見学会の際にも、「質問への回答をハイライトにまとめてあります」と案内できるため、対応負担の軽減にもつながります。
情報を整理して残しておくことで、ストーリーズの発信が「一過性の投稿」から「資産として蓄積される発信」に変わります。
まとめ ストーリーズは「見せる」から「体験をつなぐ」へ
住宅業界のInstagram運用では、ストーリーズを単なるお知らせではなく、ユーザーを来場へ導く「体験型導線」として設計することが重要です。
写真投稿だけでは伝えきれない空気感や臨場感を、リアルタイム更新によって伝えることで、検討中のユーザーが「実際に見てみたい」と思う瞬間を生み出せます。
特に意識したいのは次の三点です。
- ストーリーズを「認知→体験→行動」の流れで構成する
- 24時間の限定性を活かして“今見たい情報”を更新する
- 発信内容をハイライトで整理し、来場体験を長期的な資産に変える
これらを積み重ねていくことで、ストーリーズは「投稿が消える媒体」ではなく「来場を生み続ける導線設計の場」になります。
住宅業界では情報の信頼性と現場感が何よりも大切です。ユーザーが安心して問い合わせや来場を検討できるよう、日々のストーリーズ更新を“体験を伝える場”として磨いていくことが、成果につながる第一歩になります。
:参考記事
https://find-model.jp/insta-lab/instagram-reel-movie-house-real-estate/?utm_source=chatgpt.com
https://n-builders.jp/staffcolumn/9838/?utm_source=chatgpt.com