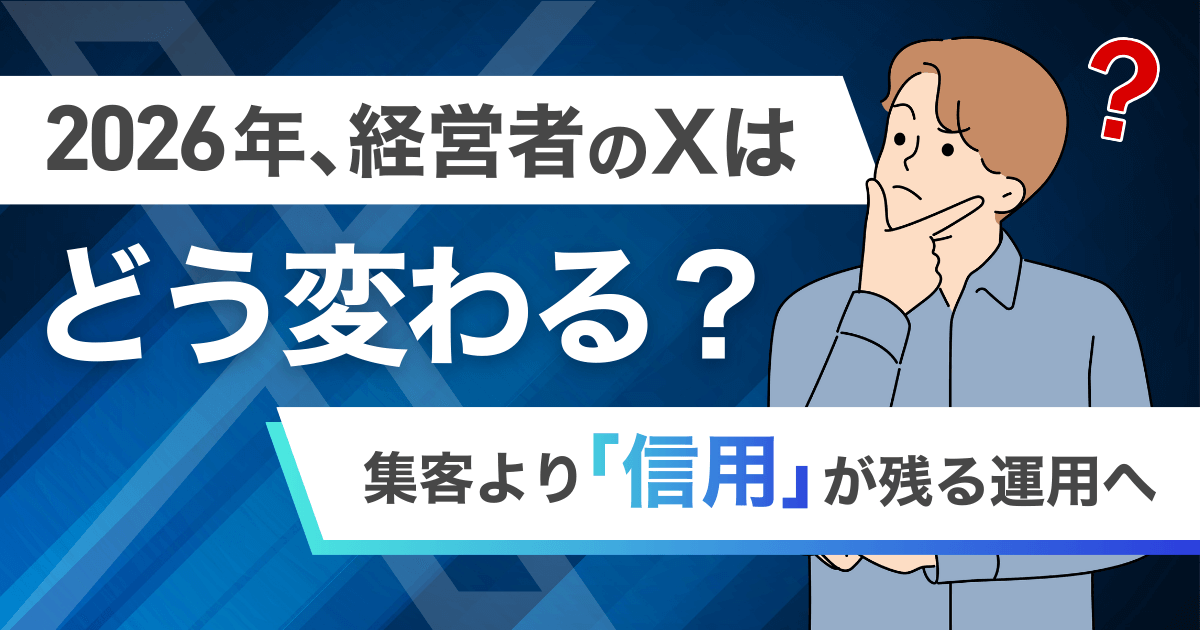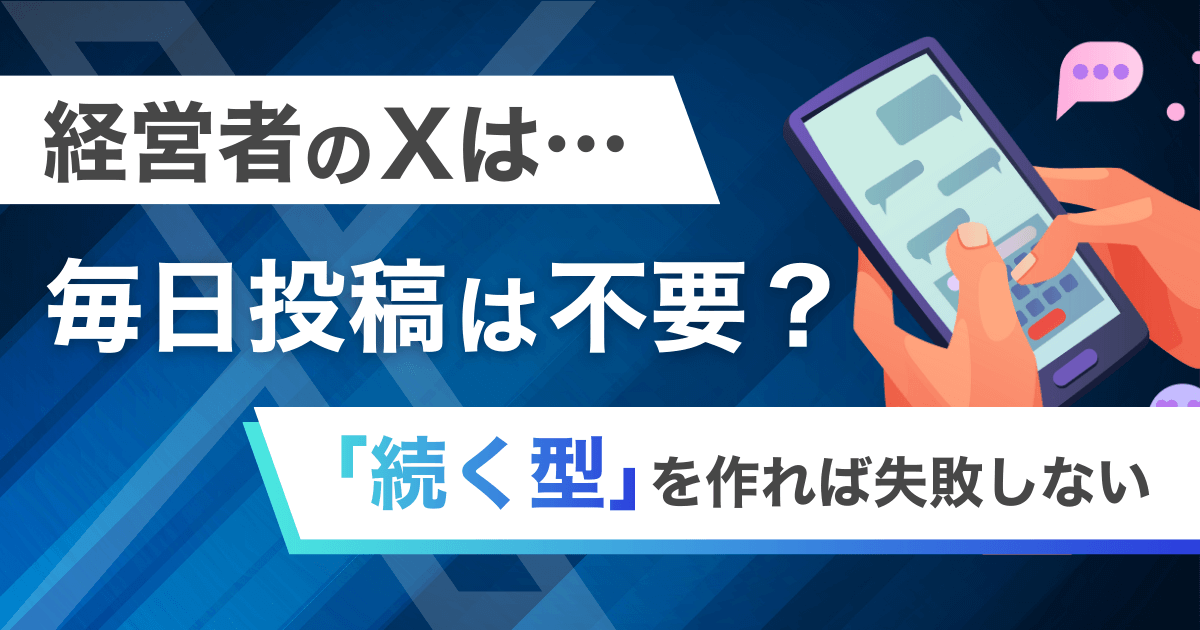2025.11.16
担当者の見える投稿で信頼をつくる|住宅業界Instagramの“中の人”活用法
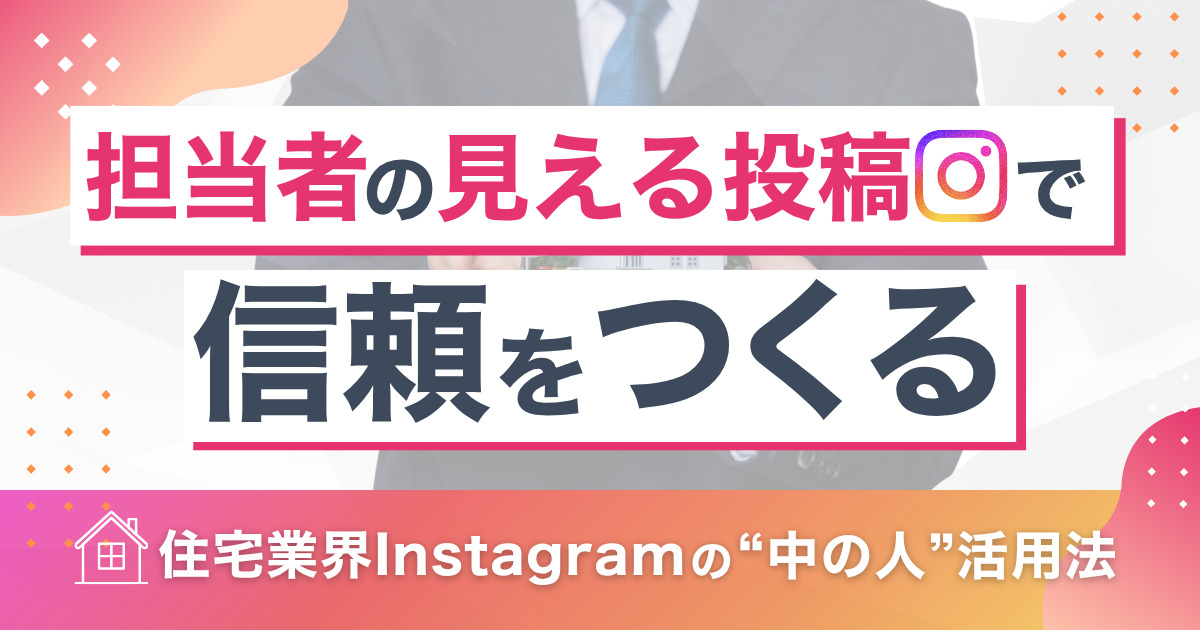
住宅業界のInstagram運用では、「どんな家を建てている会社なのか」を伝えることが基本になります。しかし、企業アカウントだけの投稿では、写真や施工実績を丁寧に発信していても、ユーザーが感じる“距離”を埋めにくいという課題があります。
家づくりは高額で、検討期間が長く、比較するブランドが多い分、「この会社は信頼できるか」を判断する材料が求められます。そこで近年増えているのが、企業アカウントと社員個人の発信を組み合わせた「中の人」活用です。
実際、住宅検討者が気にするポイントの多くは、設備や間取りだけではありません。
「担当者と話しやすいか」「相談しやすい雰囲気か」「どんな考え方で家づくりをサポートしてくれるのか」など、“人”に対する安心感が意思決定を後押しする場面が多くあります。
そのためInstagramでも、社員が登場する投稿や、担当者の視点で語られるストーリーは、企業アカウントだけでは伝わらない信頼や透明性を生み出します。発信者の存在が見えることで、ユーザーはアカウントの裏側に“人の温度”を感じられるようになります。
本記事では、住宅業界のSNS担当者に向けて、社員アカウント連携による信頼構築の方法を解説します。
顔出しが難しい企業でも実践できる“人を感じさせる見せ方”や、企業と個人の役割分担、運用ルールの整え方まで、具体的なポイントを整理していきます。
目次
第1章 住宅業界で「中の人発信」が信頼を生む理由

住宅業界では、ブランドそのものよりも「誰に相談できるのか」が信頼の決め手になります。家づくりは長期にわたるプロジェクトであり、担当者との関係性が安心感につながるためです。Instagramでも同様に、企業アカウントの投稿だけでは伝えきれない“人の存在”が、ユーザーの検討意欲を高める役割を果たします。
1. 高額商材ほど「誰が発信しているか」が重要になる
住宅は、ユーザーにとって最も大きな買い物のひとつです。
そのため、企業イメージだけで判断するのではなく、「この会社は信頼できるか」「担当者は話しやすそうか」という、人に対する印象が意思決定に強く影響します。
企業アカウントはブランドの世界観や施工品質を伝えるのに適していますが、ユーザーが本当に確認したいのは、
- 実際に相談に乗ってくれる人
- 現場で働くスタッフの雰囲気
- どのような考え方で家をつくっているか
といった“人の情報”です。
担当者の姿が見えると、企業に対する心理的なハードルが下がり、問い合わせや来場につながる流れが作れます。
2. 「担当者の人柄」は、写真以上の安心材料になる
施工事例やモデルハウスの写真は、家そのものの魅力を伝えますが、「誰が関わっているのか」までは伝えられません。
そこで効果を発揮するのが、担当者の写真やコメントを含めた“中の人発信”です。
ユーザーは、
- 笑顔で対応するスタッフの姿
- 現場で作業している大工や職人の様子
- 設計者が図面を説明するシーン
といった、人の存在が見える投稿に強い関心を持ちます。
住宅ブランドが大切にしている価値観や雰囲気が伝わり、安心して相談できる企業という印象を与えることができます。
3. 顔出しが難しい企業でも「中の人発信」は可能
すべての企業が社員の顔出しを許可しているわけではありません。
しかし、顔を出さなくても“人の気配”を感じさせる方法はたくさんあります。
例:
- 手元や後ろ姿など、顔が映らないカット
- 設計者のコメントカードや手書きメモの写真
- スタッフの“声”をテキストで紹介する投稿
- ストーリーズで「今日の現場レポート」を担当者目線で発信
このように、顔が出ない形でも十分に“人が運営しているアカウント”を表現できます。
大切なのは、企業の発信を「誰かが担当している」ことがユーザーに伝わるかどうかです。
第2章 社員アカウント連携で透明性と親近感を作る仕組み

住宅業界のInstagram運用では、企業アカウントだけで発信するよりも、担当者や現場スタッフの存在が見えることで、ユーザーが企業に感じる“距離”が大きく変わります。そのために効果的なのが、社員アカウントとの連携です。
ここでは、企業アカウントと個人アカウントを組み合わせる際の具体的なポイントを整理します。
1. 企業アカウントと個人アカウントを「役割」で分ける
まず大切なのは、企業アカウントと社員の発信が“同じことをやらない”ことです。両者が役割を分けることで、それぞれの投稿に価値が生まれます。
企業アカウントの役割
- 施工事例
- モデルハウスの案内
- キャンペーン情報
- 公式なブランドメッセージ
社員アカウントの役割
- 日常の業務風景
- 家づくりの裏側
- 現場のリアルな声
- 担当者の価値観やこだわり
これにより、ユーザーは企業アカウントで“安心”を、社員アカウントで“親近感”を感じることができます。
2. 社員アカウントから企業アカウントへの自然な誘導を作る
社員アカウントは、企業と違って「人が話している感」が強く、フォローされやすい傾向があります。
そこで、社員アカウントの投稿やストーリーズの中に、自然な形で企業アカウントへの導線を組み込むと効果が大きくなります。
例:
- 「今日の現場は会社公式でも紹介しています」
- 「施工例の詳細は企業アカウントでまとめています」
- 「見学会情報は公式で確認できます」
宣伝にならない形で案内できるため、ユーザーも抵抗なく公式アカウントへ移動しやすくなります。
3. 社内全体が「顔の見える接客」を意識する体制をつくる
社員アカウント連携を成功させるには、一部の人だけが頑張るのではなく、社内全体が“ユーザーに見られている”ことを前提に動くことが重要です。
取り入れられる工夫:
- 社内ミーティングでSNS運用の目的を共有する
- 投稿に使える写真をスタッフ間で共有する仕組みをつくる
- 現場スタッフにも「短いコメント」をもらい、投稿に活かす
住宅業界は「顔の見える接客」が求められるため、SNSでもその空気感をつくることで、初回の問い合わせ時点から信頼が高まりやすくなります。
4. 個人アカウントを“宣伝枠”にしない
社員アカウントは、企業の宣伝専用になるとユーザーが離れてしまいます。
大切なのは「人としての発信」と「会社の顔としての発信」を自然に混ぜることです。
NG例:
- 投稿のほとんどが宣伝
- キャプションがいつも営業トーク
- ハッシュタグが「#資料請求はこちら」ばかり
OK例:
- 普段の仕事の気づき
- 現場での出来事
- 家づくりに対する考え方
- 施工主とのコミュニケーションの裏側
“中の人”発信の魅力は、営業色ではなく“人の温度”なので、それを失わないことが重要です。
第3章 「顔を出す」以外で“人を感じさせる”発信方法

住宅業界では、企業規模や方針によって「顔出しできる」「顔出しできない」が分かれることがあります。しかし、顔を出さなくても、ユーザーに“中の人の存在”を感じてもらう方法は十分にあります。
ここでは、信頼や親近感を生みやすい「顔非公開の発信手法」を整理します。
1. 手元・後ろ姿・道具など“仕事の気配”を映す
顔を映さなくても、人格や雰囲気は伝えられます。
住宅業界だからこそ、現場の温度感や職人の技術が伝わるカットは非常に効果的です。
例:
- 図面に書き込みをする手元
- 現場で道具を手にした後ろ姿
- 施工中の住宅を確認している様子
- パソコンで打ち合わせ資料をつくる瞬間
こうしたカットは「仕事に向き合う人」の真剣さや誠実さが伝わり、顔出し以上に好印象を与えることがあります。
2. 一言コメントカードで“人の声”を伝える
文字だけでも、誰が話しているかは十分に伝えることができます。
特に住宅検討者は“担当者の考え方”を重視するため、短い言葉でも大きな価値を持ちます。
例:
- 設計士が大切にしたポイント
- 現場監督のこだわり
- 営業担当が意識したこと
- 大工の技術面での工夫
これをカード形式で投稿に入れると、ユーザーに「人の声」が伝わるため、親近感が生まれます。
3. ストーリーズで「担当者の視点」を補足する
フィード投稿では写真の構成が優先されますが、ストーリーズでは“人の視点”を気軽に入れられます。
例:
- 「この窓の位置には理由があります」
- 「実はこの素材、メンテナンス性が高いんです」
- 「ここは施主様が一番こだわったポイントです」
こうした一言解説は、施工事例の価値を深めるだけでなく、担当者が誠実に家づくりをしている印象を与えます。
4. スタッフの「日常」や「仕事中の小話」を発信する
顔を出さなくても、日常の一コマを共有することで、人柄が自然に伝わります。
例:
- 事務所での打ち合わせの様子
- モデルハウスへ向かう移動中のワンシーン
- 完成検査の日の裏側
- 資料づくりの工夫や苦労
住宅の検討者は、「この会社はどんな雰囲気だろう?」と常に気にしています。
その疑問に自然に答えるのが、こうした“日常のシェア”です。
5. キャプションに「担当者の言葉」を入れる
キャプションの書き方ひとつでも、人柄は伝わります。
例:
- 「この家を担当しながら感じていたこと」
- 「住まい手と一緒に考えた設計の工夫」
- 「この瞬間が一番うれしいと感じた理由」
テキストでの“温度”は顔出し以上に伝わることがあります。
住宅業界のInstagramでは、専門性よりも“考え方”に共感される場面が多いため、この手法は非常に有効です。
関連記事→「〇〇を投稿するだけでは遅い」飲食店が伸びるのは“ストーリーズを動かしている店”だった
第4章 個人と企業のバランスを保つ運用ルール設計

社員アカウントや「中の人発信」を取り入れる際に重要なのが、企業としての統一感を保ちながら、個人の魅力も生かす仕組みを整えることです。
バランスが取れていないと、個人アカウントが独立しすぎたり、企業アカウントが宣伝色の強い発信ばかりになったりと、ブランド全体の印象が乱れてしまいます。ここでは、住宅業界に適した運用ルールの考え方を整理します。
1. 「企業の役割」と「個人の役割」を明確にしておく
まず最も重要なのは、役割の境界線を決めることです。
企業アカウントが担うもの
- 施工事例
- モデルハウス案内
- 公式情報(キャンペーン、イベント)
- ブランドメッセージ
社員アカウントが担うもの
- 日常業務の裏側
- 現場の小話や担当者の気づき
- 家づくりに対する個人の考え方
- スタッフ同士のやり取りや雰囲気
役割を分けることで、「企業=安心感」「社員=親近感」と自然にブランドイメージが形成されます。
2. 投稿トーンは“個人の言葉”を軸に整える
住宅業界のユーザーは、「担当者がどんな人なのか」を知りたい気持ちが強い傾向にあります。そのため、個人アカウントでは“本人の言葉”で発信することが大切です。
ただし、企業として不適切な表現や誤解を生む書き方は避けなければなりません。
そこで企業側は、
- 禁止ワード
- 推奨トーン
- 写り込みや著作権の注意点
などの最低限のガイドラインだけ整えておくと、社員は安心して発信できます。
3. 個人アカウントを「営業専用」にしない
発信が宣伝ばかりになると、ユーザーはすぐに離れてしまいます。
住宅業界では、営業色の強いアカウントはかえって信頼を落とすことがあります。
避けたい例:
- 毎回資料請求リンクを入れる
- 投稿のほとんどがイベント告知
- キャプションが営業文章中心
望ましい例:
- 家づくりの裏側
- 現場で感じたこと
- 施主とのエピソード
- 自分が大切にしている価値観
“人の視点”を中心に構成すると、結果的にユーザーから自然に相談が生まれやすくなります。
4. 社員と企業アカウントを相互に育てる仕組みをつくる
個人の発信が強くなりすぎると、ブランドと切り離されてしまうことがあります。
そこで、企業アカウントとの相互連携をルールとして設けると効果が高まります。
例:
- 企業アカウントの投稿を、社員アカウントが自然な形でシェアする
- 施工事例は企業アカウント、裏側は社員アカウントで紹介する
- ストーリーズで双方を補完し合う構成にする
企業と個人が役割を組み合わせることで、ブランド全体のファンを増やすことができます。
関連記事→SNS運用担当者が絶対に押さえるべき「Instagramの炎上回避マニュアル」|人物写り込み・著作権・広告表記の注意点
第5章 社員を“ブランドの語り手”に育てる社内設計

社員アカウント連携を長く続け、住宅ブランドの強みに変えていくためには、“担当者が自然に語りたくなる仕組み”をつくることが大切です。
個人の発信力を伸ばすのは、企業や部署の雰囲気、情報共有の仕組み、そして本人が感じる「伝えたい」というモチベーションです。
ここでは、社員が“ブランドの語り手”として活躍できる社内設計を整理します。
1. 社員が「発信したくなる理由」をつくる
発信を負担ではなく、自分の価値を伝えられる場だと思える環境が大切です。
住宅業界は担当者の存在がブランドの印象を左右するため、「語り手であること」が自然と役割になります。
取り入れられる工夫:
- 自分の投稿が問い合わせにつながった事例を共有する
- 投稿を褒め合う文化をつくる
- チームでテーマを出し合いながら発信する
「自分の言葉が誰かの家づくりを後押ししている」と感じられれば、発信への意欲は自然に高まります。
2. 投稿に使える素材を社内で共有する仕組みをつくる
発信が続かない理由の多くは「素材がない」という悩みです。
そこで、写真や動画、テキストのひな型を社内で共有できる状態にしておくと、個人アカウントの発信が安定します。
例:
- 現場写真を共有するフォルダを作る
- ストーリーズで使えるテンプレートを用意する
- 投稿の構成案をチームで作り、必要に応じてアレンジする
これらを整えておくと、発信への心理的ハードルが下がり、担当者の負担を軽減できます。
3. 社員の個性を“ブランド価値”として扱う
担当者によって伝え方や言葉の温度は異なります。
それは企業にとってリスクではなく、“多様な魅力”として価値になります。
たとえば:
- 設計士は空間の意図をわかりやすく説明する
- 営業スタッフは家づくりのストーリーを伝える
- 現場監督は施工の裏側や安全管理を紹介する
それぞれが得意な視点で発信することで、ブランドの世界観がより立体的になります。
4. 企業アカウントと個人アカウントを「チーム」として運用する
企業と個人を切り離さず、一つのチームとしてアカウントを育てることが最も重要です。
実践例:
- 企業アカウントの投稿に社員アカウントがコメントを入れる
- 社員アカウントの投稿を企業側がストーリーズで紹介する
- 新しい取り組みは社内で共有し、投稿内容を互いにフィードバックする
このように企業と個人が連動すると、ユーザーは「人の気配があるブランド」と感じ、信頼が高まります。
まとめ 企業発信に“人の温度”を加えることで生まれる信頼
住宅業界では、担当者との関係性が家づくりの満足度を大きく左右します。
Instagramでも同じように、施工事例やモデルハウスの写真だけでは伝わらない“安心感”や“企業の誠実さ”を、担当者の存在を通じて補うことができます。
そのため、企業アカウントと社員アカウントを組み合わせた「中の人発信」は、住宅業界に特に相性のよい運用手法です。
本記事で紹介したように、
- 社員の存在が見えるだけでブランドの透明性が高まる
- 顔出しなしでも“人の気配”を発信できる
- 企業と個人が役割を分けて発信すれば、一貫した世界観が生まれる
- 社員が“語り手”になることで信頼と問い合わせにつながる
といった効果が期待できます。
今後の住宅SNS運用では、施工事例やデザインだけで競合と差別化するのが難しくなります。
だからこそ、企業の価値を“人の言葉”で伝える発信が、問い合わせや来場予約へとつながる大きな力になります。
担当者とブランドが一緒にアカウントを育てていくことで、ユーザーが安心して相談できる関係をつくり、結果として住宅ブランド全体の信頼価値が高まっていきます。
:参考記事
・https://housing-dx.com/housing-column/2314/?utm_source=chatgpt.com
・https://zen-web.co.jp/column/20250720-column-housing-insta/?utm_source=chatgpt.com