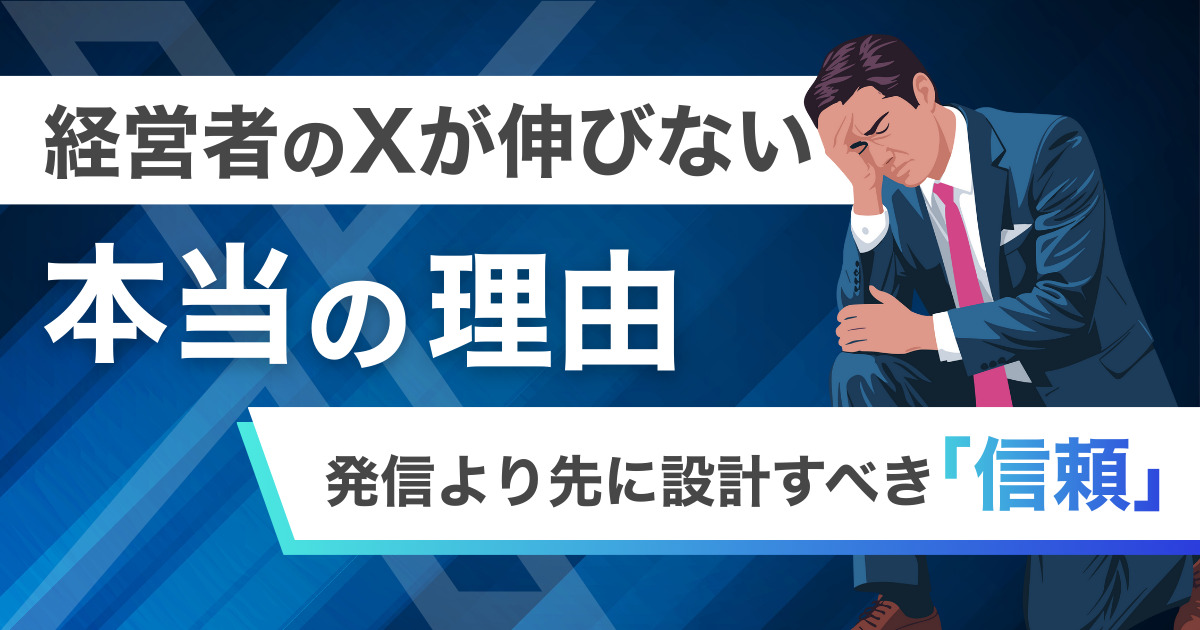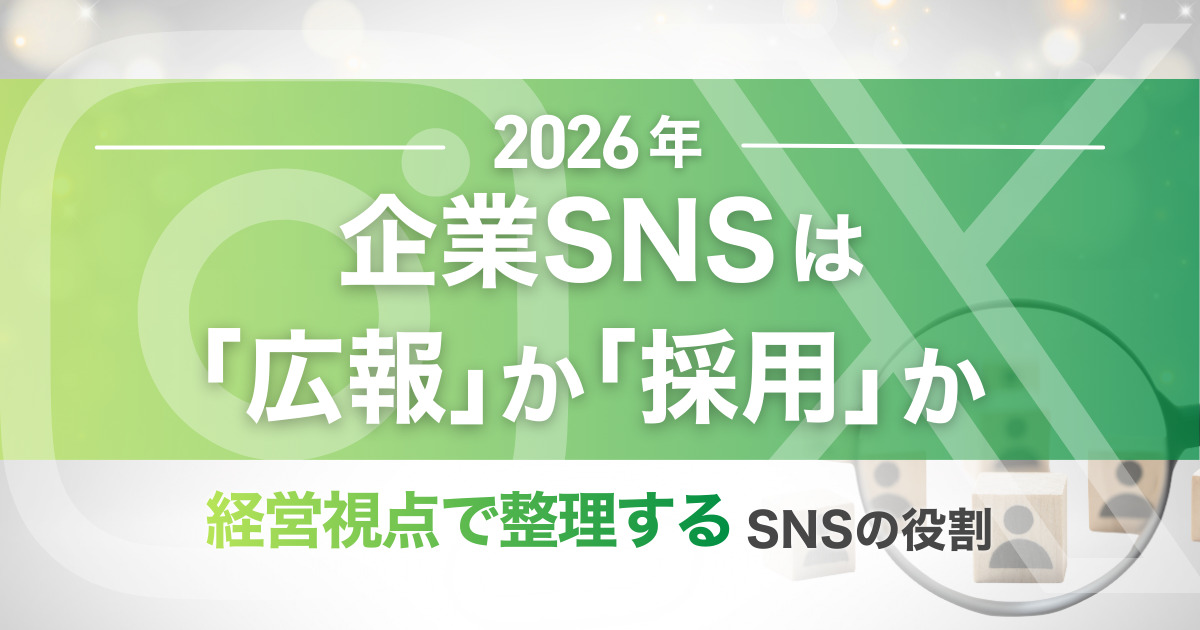2025.11.23
Xで広がる“家づくりあるある”|住宅アカウントが共感で拡散される投稿設計
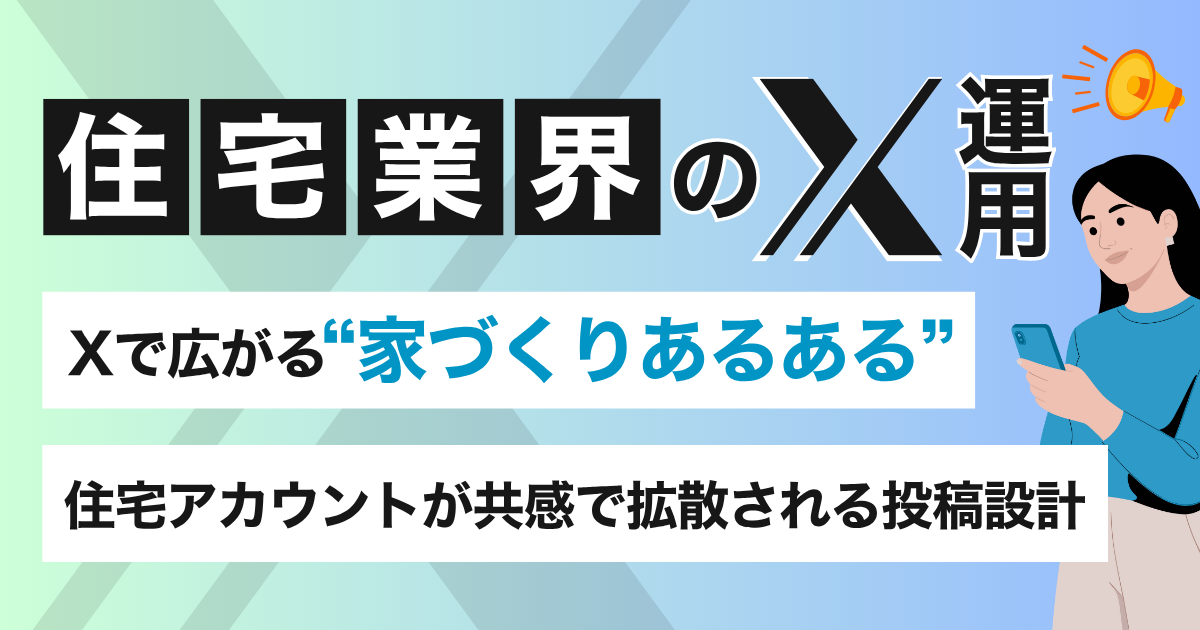
住宅業界のX(旧Twitter)運用では、
「どんな投稿なら伸びるのか」「どんな切り口で共感を得られるのか」
という悩みを抱える運用担当者が非常に多いです。
施工事例、完成写真、イベント告知などの“宣伝型投稿”は、
必要ではあるものの、拡散されにくくタイムラインで埋もれやすいという課題があります。
その一方で、住宅アカウントが大きな反応を得ているのが “家づくりあるある”投稿 です。
・打ち合わせでよくある出来事
・家族の反応
・間取り検討の葛藤
・予算に関する素朴な悩み
・引き渡し前後のリアルな気持ち
こうした小さな“あるある”が、住宅検討者・施主・リフォーム希望者などの幅広い層に刺さり、自然にリポストやいいねが増えていきます。
住宅は高額で、心理的な敷居が高く、検討期間も長い商材です。
だからこそ、同じ悩みや体験を共有できる“日常の共感”が、大きな信頼につながります。
共感投稿は、宣伝とはまったく違う導線でユーザーの心を動かし、
「この会社は分かってくれる」
「このアカウントをフォローしておきたい」
という気持ちを自然に生み出します。
この記事では、住宅業界のXで共感を広げる“あるある投稿”の具体的な作り方を解説します。
バズりやすい切り口、共感される構成、生活者目線のネタ、そして企業の価値観へ自然につなげる方法まで、運用担当者が今日から実践できる内容にまとめています。
目次
第1章 なぜ住宅アカウントは“共感投稿”と相性が良いのか

住宅業界は、他の業種と比べても圧倒的に「共感が生まれやすい」特性があります。
理由はシンプルで、家づくりにはユーザーが“共通して抱えやすい悩みや体験”が多く存在するからです。
1. 家づくりは「誰もが初心者」である
住宅検討者の多くは、家づくりに不慣れです。
専門用語も多く、工程も複雑で、どんな選択が正しいのか分からない状態からスタートします。
・間取りが正しいのか分からない
・収納量に不安を感じる
・予算オーバーを恐れる
・動線について何が正解か分からない
・モデルハウスを見ても比較ポイントが分からない
こうした共通の“迷い”があるからこそ、
「それ分かる!」という共感が起きやすいのです。
2. 家づくりは“家族全員のイベント”だから共通言語が多い
住宅検討は、夫婦・子ども・親など複数人で進めることが多いです。
そのため、家族間でよくあるシーンが共感の材料になります。
・夫婦で意見が割れる
・収納の優先順位が違う
・子どもがはしゃいで打ち合わせが進まない
・親世代からアドバイスが飛んでくる
これらは多くの家庭で共通する経験であり、
住宅アカウントが発信すると“日常のリアル”として反応が集まりやすい内容です。
3. 家づくりには“感情の揺れ”が必ずある
住宅検討は、ワクワクと不安が同時に存在するプロセスです。
・間取りが決まったときの安心
・予算が膨らみそうになったときの焦り
・上棟日の感動
・引き渡し前のそわそわ
・家具選びの楽しさと迷い
こうした 感情のアップダウン があるからこそ、
“あるある投稿”は強い共感を生むのです。
4. 住宅は「長期検討型」のため、ユーザーが連続して見てくれる
住宅検討者は、数ヶ月〜1年以上の期間にわたって情報を集め続けます。
そのため、共感投稿に触れたユーザーがアカウントを継続フォローしやすい特徴があります。
・いつか役に立ちそう
・しばらく家づくり情報を追いたい
・このアカウントの視点が分かりやすい
共感投稿は、長期的にユーザーをつなぎとめ、アカウント価値を高める働きがあります。
5. 「営業っぽさ」が強い業界だからこそ、共感投稿が効く
住宅業界のSNS投稿は、どうしても
・施工事例
・イベント告知
・キャンペーン
など宣伝型に寄りやすい傾向があります。
しかしユーザーは“押し売り感”を嫌うため、宣伝投稿ばかりでは離脱が増えてしまいます。
その点、共感投稿は
「営業ではなく、情報として欲しい」「思わずリポストしたくなる」
という性質を持っているため、住宅業界との相性が非常に良いのです。
6. “あるある投稿”は住宅検討者だけでなく、OB施主にも刺さる
住宅アカウントにおいて大事なのは、OB施主の存在です。
引き渡し後の生活者も共感投稿の大きな反応母体になります。
・間取りの決定あるある
・コンセント位置の後悔ネタ
・収納に関する悩み
・入居後に気づいたこと
・引き渡し後の“良かった、後悔”
こうしたネタはOB施主にも刺さります。
そのため、住宅アカウント全体のエンゲージメントを底上げする効果があります。
住宅アカウントが共感投稿と相性が良いのは、
家づくりが“誰もが悩みを抱えるプロセス”であり、“感情の揺れが多い体験”だからです。
共感投稿は、ユーザーの感情に寄り添いながら、企業への好意を自然に積み上げていく最適な手法です。
第2章 バズる“家づくりあるある”の特徴

“家づくりあるある”と一言でいっても、拡散されやすい投稿には共通点があります。
住宅業界のXで反応が伸びる投稿は、ただのあるあるネタではなく、家づくり中のユーザーの感情に触れる切り口を持っているのが特徴です。
ここでは、特にバズりやすい“家づくりあるある”の傾向を、説明付きで整理していきます。
1. 「みんな経験するのに、誰も言語化していないこと」
家づくりは、多くの人が同じような悩みを抱えますが、
それを“言語化してくれる存在”は意外と少ないものです。
・間取り決めが終わった後に、急に不安になる
・打ち合わせの帰り道で、夫婦の意見がまた変わる
・「これ本当に必要?」と何度も言ってしまう
・最初に思い描いた家と、途中で変わっていく現実
こうした “言葉にしてほしかったモヤモヤ” を投稿すると、
「それな!」「分かりすぎる」
と一気に共感が集まります。
2. “生活者としての視点”が入っている
住宅会社が発信するあるあるで、反応が伸びるのは
“生活者としての視点が混じっている投稿” です。
例えば:
・収納は「多ければ便利」ではなく「適材適所じゃないと結局散らかる」
・キッチンの高さ、決めるときはそんなに気にしないのに、住み始めるとめちゃくちゃ気になる
・動線は「便利」より「面倒が減るかどうか」が大事
生活者の感覚が入るほど、ユーザーが自分に重ねやすくなります。
3. “ちょっと笑える不便さ”は拡散されやすい
住宅アカウントのあるあるで最も広がりやすいのは、
軽い不便さ・小さなストレスに関する投稿 です。
・「コンセントが足りない問題、家づくりあるあるの代表格」
・「収納、増やせば増やすほど“とりあえずの場所”ができる」
・「打ち合わせで出された“間取りの第12案”」
失敗や愚痴ではなく、**笑えるレベルの“ちょっとの不便”**が拡散の鍵になります。
4. 夫婦・家族のやり取りは強い共感を生む
家づくりは家族イベントのため、家族ネタは共感の中心にあります。
・「夫婦で絶対に意見が割れる場所:キッチン・収納・間取りの優先度」
・「子どもはモデルハウスを遊び場だと思っている説」
・「親からのアドバイスが急に増える時期がある」
「あるある×家族」は最も反応が伸びやすい鉄板ジャンルです。
5. 予算に関するあるあるは、強い“共感の輪”が広がる
住宅検討者の最大の関心ごとのひとつが予算。
そのため、予算系のあるあるは非常に反応がよくなります。
・「オプション、話を聞くと全部欲しくなる」
・「最初の予算と最後の見積もり、だいたい違う」
・「“これも必要ですか?”って聞くの、家づくり中だけで100回くらいある」
予算の話はリアルでありながら、軽く言及することでユーザーを惹きつけます。
6. “入居後のあるある”も非常に強い
入居後の暮らしに関するあるあるは、施主・OBにも届くため強いです。
・「コンセント位置、住んでから気づく本当の便利さ」
・「収納は“増やす”より“使う”ほうが難しい」
・「外構、後から考えようと思ってたら一生後回し」
入居後の生活者も巻き込み、エンゲージメントを底上げしてくれます。
7. “ネガティブにしすぎない”がバズの前提
住宅という高額商材では、ネガティブすぎる投稿は逆効果です。
そのため、あるある投稿は 軽さ・ユーモア・日常感 を大切にする必要があります。
・「こういう時あるよね」の距離感
・「ちょっと笑える困りごと」
・「生活者の目線のズレ」
ユーザーが安心してリポストできる投稿が、結果として広がりやすくなります。
バズる“家づくりあるある”は、ユーザーの感情と日常に深く根ざした内容であることが共通点です。
「みんな感じているのに誰も言っていないこと」をやさしく言語化すると、住宅アカウントは強い共感と拡散を獲得できます。
第3章 宣伝型から“日常共感型”への切り替え方

住宅業界のX運用で成果が出づらい最大の理由は、投稿内容が “宣伝型に寄りすぎている” ことにあります。
もちろん告知や施工事例の発信も必要ですが、それだけではユーザーの反応が伸びず、フォロー・拡散・エンゲージメントにつながりにくいという課題があります。
ここでは、宣伝型から“日常共感型”へ切り替えるための考え方と構成を、具体的に解説します。
1. 「企業 → ユーザー」ではなく、「ユーザー → ユーザー」の世界観へ
宣伝型投稿は、企業が伝えたい情報を一方的に発信します。
しかし共感型投稿は、ユーザー同士が「分かる」「あるある」と反応できる内容が主役になります。
宣伝型:
・施工事例の紹介
・イベント告知
・キャンペーン情報
日常共感型:
・家づくり中の気づき
・夫婦・家族のちょっとしたやりとり
・住まいの小さな“失敗あるある”
・入居後のミニストレス
宣伝ではなく、ユーザーが自分ごと化できるトピックを中心に切り替えます。
2. 「伝えたい情報」ではなく「共感される情報」を基準にする
住宅アカウントは、どうしても
「この施工の良さを伝えたい」
「この設備の魅力を紹介したい」
と考えがちです。
しかし共感型に変えるときの基準はひとつだけです。
ユーザーが「分かる!」と思うかどうか
例えば:
・「収納は多くしたつもりでも、結局“とりあえず置き”の場所ができがち」
・「子どもの学用品、想像以上に場所を取る」
・「予算は“ちょっとだけ”が積み重なっていく」
企業の意図ではなく、生活者の視点を基準にします。
3. 投稿構成を“共感 → 気づき → 価値観”の流れにする
宣伝型は「施工 → 仕様 → 会社案内」の順番ですが、
日常共感型は逆です。
理想的な構成はこれです:
- 共感: 「あるあるの一言」
- 気づき: 「実はこういう理由なんです」
- 価値観: 「だから当社はこう考えています」
例を出します。
投稿例(説明付き)
・【共感】
「家づくり、なぜか“第5案あたりで急に迷いが増える”現象があります。」
・【気づき】
「選択肢が増えると、人は逆に決めにくくなるため、家づくり後半は思考が疲れやすくなります。」
・【価値観】
「だからこそ、打ち合わせでは“優先順位”を一緒に丁寧に確認しています。」
このように、押し売りにならず自然に価値観を伝えられます。
4. 施工事例も“共感視点”に変換できる
宣伝型:
「モダンな外観に仕上がりました!」
共感型:
「外観の色、最後まで悩む方が本当に多いです。
完成すると“この色で良かった”とホッとされる方が多い印象です。」
このように、施工事例も“あるある”と組み合わせれば共感投稿に転換できます。
5. 社名の存在を出しすぎない
企業名やブランド色を強く押し出すと、一気に宣伝っぽくなり共感が落ちます。
共感型投稿は
“企業が自分の哲学を語る場ではなく、生活者の気持ちに寄り添う場”
という意識が重要です。
*アカウント名に企業名が入っているので、投稿本文は控えめで良いです。
6. 目的は「バズ」ではなく「信頼の蓄積」
共感型は拡散されやすいですが、狙いすぎる必要はありません。
目的は、
・生活者の感情に寄り添う
・“理解してくれる会社”という印象を積み上げる
・長期検討ユーザーが見続けてくれる状態をつくる
この3つです。
無理に狙うのではなく、日常の素朴な視点を重ねていくことが成功への近道です。
宣伝型から日常共感型への転換は、
企業目線ではなくユーザー目線の投稿にシフトするということです。
“あるあるの種”に企業の価値観を少しだけ乗せることで、押し売り感のない自然なブランド発信ができます。
第4章 実際に使える“家づくりあるある”ネタリスト

“家づくりあるある”投稿を作るときに重要なのは、
専門家の視点ではなく、“生活者の視点”で言語化すること です。
ここでは、住宅検討者・施主・OB施主のいずれにも刺さりやすい「あるあるネタ」をジャンル別にまとめて紹介します。
それぞれに簡単な説明を添えているので、そのまま投稿設計に活かせます。
1. 打ち合わせ・間取り検討のあるある
・「決めること、多すぎる問題」
説明:
最初はワクワクしていたのに、途中から“決め疲れ”がくるのは誰しも経験する。
・「間取り、決めたあとにまた悩む」
説明:
決定した途端に“本当にこれでいいのか”の不安が押し寄せる心理。
・「家族で“優先順位”が毎回ズレる」
説明:
収納、動線、広さ、キッチン位置など、家族でも価値観が違うから起きるあるある。
2. 収納に関するあるある
・「収納は“多ければいい”ではない」
説明:
多く作っても使わない場所が出る、結局“とりあえず置き場”が増えると言われるあるある。
・「季節ものが想像以上に場所を取る」
説明:
衣替え、レジャー用品、子どものものは、打ち合わせ時より実生活のほうが量が多い。
・「パントリー、広げすぎると使いこなせない」
説明:
大収納は憧れるが、動線や管理が難しくなるため、実は“広すぎ”問題が発生する。
3. 予算に関するあるある
・「“ちょっとだけ”の積み重ねで予算が膨らむ」
説明:
オプションや仕様変更で“数万円単位”が積み重なり、気づくと見積書が増えている状況。
・「説明を聞くと全部ほしくなる」
説明:
担当者の説明が丁寧で、つい追加したくなる心理。
・「外構は“後で考える”と言いつつ後回しになりがち」
説明:
住宅検討の最後に来る外構の優先度が下がりやすいのは定番のあるある。
4. 生活動線・家事動線のあるある
・「動線は“便利”より“面倒が減る”が重要」
説明:
生活者視点で動線を考えると、距離よりも“作業の少なさ”がポイント。
・「脱衣所と洗面所の兼用、生活の中で困るタイミングがある」
説明:
家族構成によって不便が生まれるあるある。
・「回遊動線、作りすぎるとかえって使わない」
説明:
便利そうに見えるが、家族によっては使いにくいケースもあるという日常のリアル。
5. 家族の会話・人間関係のあるある
・「子どもはモデルハウスを遊び場だと思っている」
説明:
多くの家庭で共通する“ありがちシーン”。
・「夫婦でこだわる場所が正反対」
説明:
キッチンと外観、収納とリビングなど、価値観のズレから生まれる“討論あるある”。
・「親からのアドバイスが急に増える時期がある」
説明:
住宅購入が近づくと実家から助言(時にプレッシャー)が増えるケース。
6. 入居後の暮らしのあるある
・「コンセント位置、住んでから気づく便利さ・不便さ」
説明:
家づくり中は軽視しがちだが、入居後に重要度が急上昇するポイント。
・「収納は“作る”より“使う”ほうが難しい」
説明:
整理整頓が習慣化しないと結局散らかるというリアル。
・「ゴミの分別、打ち合わせのときはあまりイメージできない」
説明:
実際に暮らし始めて気づく生活の細部。
7. “モデルハウスあるある”
・「あの広さは自宅では再現できない」
説明:
モデルハウスが広く見えるのは家具・照明配置も含む“演出”があるため。
・「収納の“隠し方”は実生活と違う」
説明:
モデルハウスは生活感が極限まで排除されているため、現実とは距離があるという視点。
“あるある投稿”は、ユーザーが“自分の中にある悩みや感情”を言語化してくれることが最大の価値です。
紹介したネタはすべて、生活者のリアルがベースになっているため、どの投稿も高い共感を得やすい切り口です。
第5章 共感投稿を“企業の価値観”につなげる方法

“家づくりあるある”投稿は、共感を得て拡散される効果がありますが、
ただバズを狙うだけでは住宅会社のブランド構築にはつながりにくいことがあります。
大切なのは、共感投稿を自然に企業の価値観へつなげることです。
ここでは、押し売りにならず、丁寧に会社の姿勢を伝えるための方法を紹介します。
1. 「あるある」→「気づき」→「価値観」の三段構成にする
共感投稿に企業の想いをのせるときは、この順番が効果的です。
- あるある(共感)
ユーザーが「分かる!」と思う入り口を作る。 - 気づき(知識・補足)
そのあるあるが生まれる背景や理由をやさしく説明する。 - 価値観(企業の姿勢)
「当社ではこう考えています」と自然に添える。
例を見てみます。
投稿例
・【あるある】
打ち合わせ終盤、急に決めづらくなる現象。
・【気づき】
選択肢が増えるほど迷いやすくなるのは自然なことです。
・【価値観】
当社では“優先順位の整理”を一緒に行い、迷いの負担が大きくならないようにサポートしています。
こうすることで、
“押し売り感ゼロ”で企業の姿勢が伝わります。
2. 「共感はユーザーのもの、価値観は企業のもの」
共感投稿は、あくまでユーザーの視点で作る必要があります。
企業が主語になると、一気に宣伝色が強くなります。
・「収納の量、住んでから気づくことって多いですよね。」(共感)
・「だからこそ、使い方を一緒に考える打ち合わせを大切にしています。」(価値観)
このように
“ユーザーの気持ち”を素直に受け止めるところから始める
ことが大切です。
3. 価値観パートは“ひとことだけ”で十分
共感から価値観につなげるとき、説明を多く書きすぎると逆効果になります。
・長い説明
・専門用語
・技術アピールの羅列
こうした内容は、共感投稿の良さを失ってしまいます。
価値観は ひとこと で十分に伝わります。
例:
・「だから現場の確認を大切にしています。」
・「住んでからの使いやすさを優先しています。」
・「迷いを減らすサポートを心がけています。」
短いからこそ、読み手の心に自然に入ります。
4. 共感投稿は“営業ではなく、理解の姿勢”を示す場にする
住宅業界のSNSで避けたいのは、
「問い合わせしてください」「イベント開催します」
などのゴリ押しが混ざることです。
共感投稿は“企業の思想を控えめに見せる場”と考えるとちょうどよいです。
・「打ち合わせで迷うのは当たり前。だから一緒に考えたい。」
・「収納の正解は家族ごとに違う。だから丁寧にヒアリングします。」
・「家事動線は暮らし方によって変わる。だから生活者目線で考えます。」
読んだユーザーが
「この会社、寄り添ってくれるな」
と感じる状態が理想です。
5. 製品・仕様のアピールは“共感を入口”にすれば自然につながる
設備、素材、工法などの技術要素は、共感投稿と結びつけることで自然な発信になります。
例:
・【あるある】
「上棟した瞬間、家の広さが一気に実感できる」
・【気づき】
「構造が見えると、住むイメージが湧く方が多いです。」
・【価値観】
「当社では完成後に見えなくなる部分を大切にしています。」
“共感 → 技術” の順にすると読み手は受け入れやすく、
企業の専門性も自然と伝わります。
6. 共感投稿は“ブランドの下地づくり”として長期で効く
共感投稿は、即効性よりも 長期的な信頼蓄積 に優れています。
・このアカウント分かりやすい
・ユーザーの気持ちに寄り添ってくれる
・毎日の投稿に一貫性がある
これを数ヶ月続けることで、
「問い合わせの候補」に入りやすいアカウントになります。
“あるある投稿”で終わらせず、
共感 → 気づき → 価値観
の流れを軽く乗せることで、住宅会社の姿勢が自然に伝わります。
宣伝の雰囲気を出さないこと、短い言葉で価値観を語ることが、共感投稿の成功につながります。
関連記事→担当者の見える投稿で信頼をつくる|住宅業界Instagramの“中の人”活用法
まとめ “家づくりあるある”は住宅アカウントの拡散エンジンになる
住宅業界のX(旧Twitter)運用において、“家づくりあるある”は最も強力な共感装置です。
家づくりには誰もが経験しやすい悩み・不安・迷い・感情の揺れがあり、
それらをやさしく言語化してあげることで、
ユーザーは「分かる」「そうそう」「これ私だ」と反応しやすくなります。
共感投稿が強い理由は大きく5つあります。
・誰もが初心者で不安を抱えている
・家族全員が関わるため、共通言語が多い
・小さなストレスや感情の揺れがたくさんある
・入居前後の生活者も巻き込める
・宣伝ではなく“気持ち”を中心にした投稿だから拡散される
さらに、共感投稿は単なるバズ取りではなく、
「この会社は生活者の気持ちを分かってくれる」
というブランド印象を積み上げる土台にもなります。
特に、
共感 → 気づき → 価値観
を自然につなげることで、押し売り感のない形で企業の姿勢が伝わります。
施工事例やイベント告知とは違い、
“日常の気づき”や“生活者のリアル”を丁寧に言語化した投稿は、
数ヶ月、数年にわたってユーザーとのつながりを育てる強いコンテンツです。
今日から取り入れられる小さな一言でも構いません。
家づくり中の気づき、打ち合わせのあるある、入居後の小さなリアル。
それらをやさしい言葉でまとめるだけで、住宅アカウントの拡散と信頼は大きく変わります。
:関連記事
・https://ielove-creators.co.jp/wp/ハウスメーカーがやってはいけないsns運用ミス10選/?utm_source=chatgpt.com
・https://housing-dx.com/marketing/3218/?utm_source=chatgpt.com