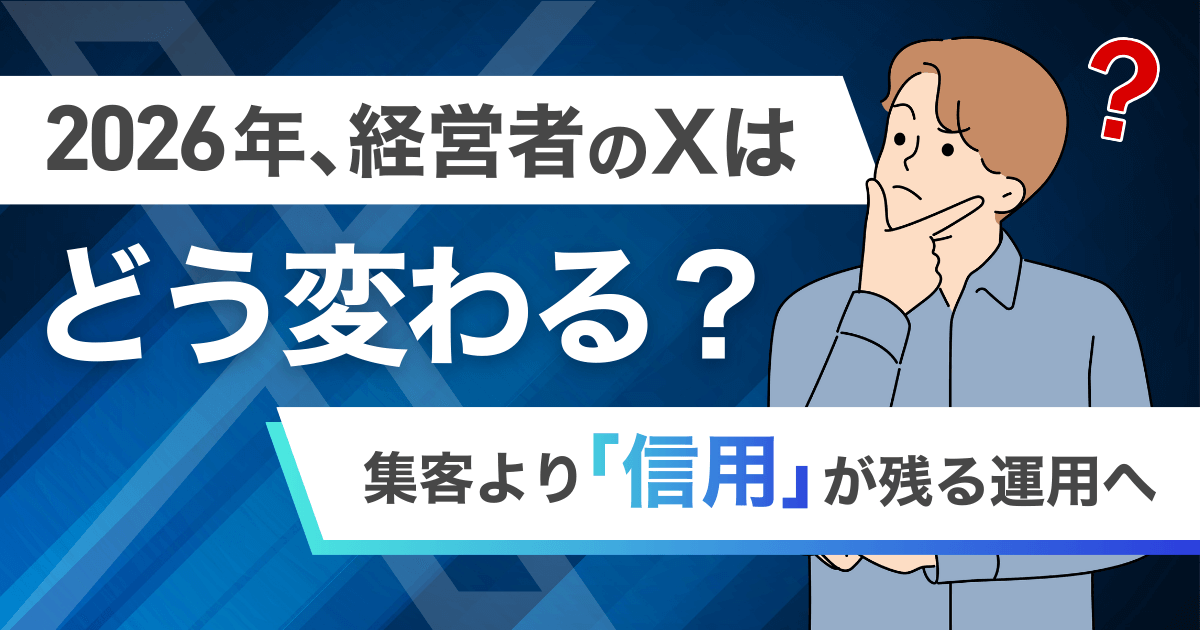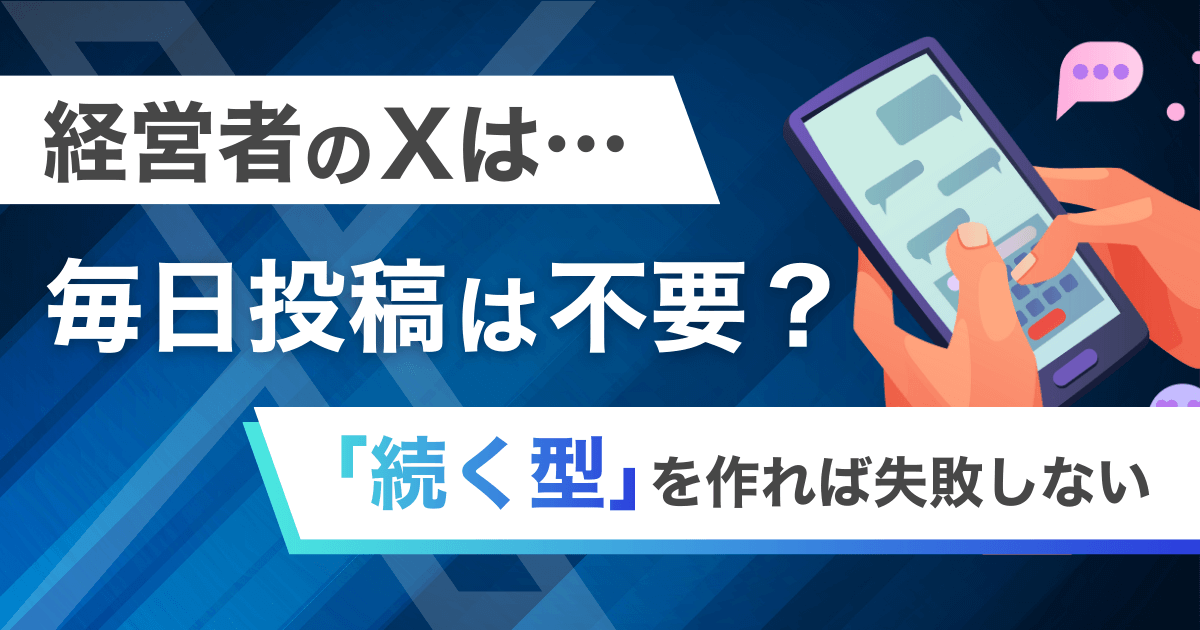2025.10.31
AI音声&流行音源で“中の人感”を作る方法|顔出しせずに親近感を高めるInstagramリール戦略

Instagramのリールでは、いま「中の人」を感じられる投稿が注目を集めています。
けれど実際に、企業アカウントで顔出しを続けるのは現実的に難しい。
撮影体制・人材・社内規定の壁があり、担当者が変わるたびに運用トーンが揺らぐという課題もあります。
そんな中、“声”を使って親近感を作る手法が急速に広がっています。
AI音声や流行音源を使えば、顔を出さなくても「話しかけられているような距離感」を生み出すことが可能です。
リール上では、ユーザーが音をONで視聴している割合が他フォーマットよりも高く、
“音声の印象”がアカウント全体のトーンを決める大きな要素になっています。
だからこそ、「誰が話しているのか分からない」よりも、「人の気配がある」発信が選ばれるようになりました。
この記事では、
・なぜ今“中の人感”が求められているのか
・顔出しせずに親近感を作るAI音声・流行音源の活用法
・企業アカウントでも続けられる“中の人演出”の仕組みづくり
を具体的に解説します。
目次
第1章:いまInstagramで“中の人”が求められている理由

Instagramのアルゴリズムは年々、“人の温度感”を感じる投稿を優先的に表示する傾向が強まっています。
これは単なるエンタメ志向ではなく、ユーザーが「信頼できる情報源」としてフォローするアカウントを求めているからです。
1.1 「誰が話しているのか」が投稿の価値を決める
フォロワーが増えても、コメントやDMの反応が弱いアカウントには共通点があります。
それは、“発信者の存在が見えない”こと。
ブランドロゴや商品画像だけの投稿は、内容が良くても人間味が伝わらず、ユーザーが感情的につながりにくいのです。
逆に、「中の人」が少しでも出ているアカウントは、発言に“人格”が宿ります。
たとえば、語りかけるようなナレーションや、テンポのいい“あるあるリール”など。
顔を出さなくても、声やテンポ、字幕の言い回しから“誰が運用しているのか”の気配が伝わります。
1.2 リールが「ブランドの人格」を見せる舞台に
静止画投稿やカルーセルは“専門性”を伝えるのに向いていますが、
リールは“温度感”と“テンポ感”を伝える場所として機能しています。
企業アカウントでも、担当者が話しているような口調や音声付きのリールを出すことで、
「このブランドは親しみやすい」「担当者の人柄が伝わる」と感じてもらえます。
そしてアルゴリズム上でも、
- 音声付きリール(AI含む)は視聴完了率が高い
- 視聴完了率が高い投稿ほど「おすすめ」に乗りやすい
という好循環が生まれています。
1.3 “情報”より“共感”がフォローを生む時代へ
美容・飲食・教育・不動産など、どの業界でもユーザーは“企業情報”よりも“中の人のリアル”に反応しています。
特にリールでは、「同じ立場の人が話してくれる」ようなトーンが強く支持されています。
そのため、顔を出さずとも「声」「語り」「テンポ」「編集のリズム」で、
中の人らしさ=共感軸を作ることがフォロー動機の中心になりつつあります。
第2章:顔出しできない企業でも“声”で親近感を作れる時代

かつて「中の人感=顔出し」と思われていた時代は終わり、
いまは“声の存在感”だけで親近感を生むリール設計が可能になっています。
AI音声や流行音源を活用すれば、表情を出さずとも“話しかけてくる雰囲気”を作れるのです。
2.1 AI音声で“話しているように見せる”ナレーション活用
AIナレーションは、企業アカウントでも使いやすい“顔出し代替手段”です。
テキストを読み上げるだけで、「中の人が話している」ような印象を自然に再現できます。
おすすめの使い方:
- 商品紹介やTips解説にAIナレーションを挿入
- テロップとナレーションを同期させて“口パク風”に見せる
- トーンを一定に保つことで“ブランドボイス”を確立
これにより、担当者が変わっても一貫した“声のブランド”を維持でき、
「話すブランド」=親しみやすいブランドという印象を作ることができます。
2.2 流行音源で“共感”と“親近感”を演出する
もう一つの有効な手法が、流行音源(トレンドBGMやセリフ音源)を使った共感演出です。
AIナレーションが「説明」に強いのに対し、流行音源は「感情演出」に強い。
活用例:
- トレンドのセリフ音源を使って「あるある」や「担当者の日常」を再現
- 軽いBGMに合わせて「1日の仕事風景」「投稿制作の裏側」などを編集
- リールの中で音声を中心に“動き+字幕”でストーリー化
顔が出ていなくても、音源のリズムとキャプションの間に“人っぽさ”が生まれます。
2.3 “声”はブランドの人格をつくる新しい要素
従来のブランディングは「色」「フォント」「ビジュアル」でしたが、
今はそこに“音のトーン”=ブランドボイスが加わっています。
たとえば:
- 柔らかい女性AI音声 → 親近感・ナチュラル系ブランドに最適
- 少し早口で元気なAI音声 → 活発・スタートアップ系企業に向く
- 落ち着いた低音ナレーション → 高級サロン・美容クリニック系に適応
つまり、音声トーンそのものが“中の人の性格”を演出する要素になるのです。
第3章:流行音源を使った“中の人感”リールの構成法

AI音声が「語る親近感」を作るなら、流行音源は「感じる親近感」を作る要素です。
ここでは、実際のInstagramリールで“中の人感”を自然に演出するための構成パターンと編集ポイントを整理します。
3.1 パターン①:「セリフ音源 × テロップ」で“あるある共感”を作る
トレンド音源の中には、「あ〜それ分かる!」と思わせる短いセリフ音源が数多く存在します。
このタイプを使えば、担当者の日常や仕事の裏側をユーモラスに表現できます。
構成例:
- 冒頭のセリフ音源で“あるある”を提示(例:「やば、またリール出し忘れた」)
- テロップで状況を補足(「SNS担当あるある」など)
- 最後に軽いまとめorリアクションで締め
顔出しなしでも、音声とテロップの掛け合わせで「人がそこにいる」感覚を再現できます。
3.2 パターン②:「BGM × モーションテロップ」で“中の人の日常”を演出
流行のBGM(口笛・ギター・Lo-Fi系など)を活かして、
“日常を切り取っただけ”のような温かみのあるリールを作る構成です。
構成例:
- 1秒目:リズムに合わせてシーンが切り替わる(作業机・PC画面・手元など)
- 3秒目〜:字幕でナチュラルなコメントを挿入(例:「今日も投稿づくり奮闘中」)
- 7秒目〜:BGMのビートに合わせて“中の人のつぶやき”で締める
AI音声を使わずとも、「BGM×字幕×テンポ」で人の温度感を伝えることができます。
3.3 パターン③:「AI音声 × リズム構成」でブランドメッセージを語る
AI音声を“テンポのある音源”と組み合わせることで、
リールに“テンポ+知性”を両立させる構成が可能です。
構成例:
- 冒頭(1〜2秒):「○○って意外と知られていません」など引きの一言
- 中盤(3〜7秒):AI音声で簡潔に解説+関連画像や動画をテンポ良く切り替え
- 終盤(8〜10秒):ブランドの姿勢を一言で締め(例:「毎日をちょっと楽しく」)
ナレーションを入れることで、「声に信頼感がある」=人の存在を感じる流れができます。
3.4 パターン④:「流行音源 × 担当者リアクション構成」
トレンドのセリフ音源に合わせて、担当者のリアクションを文字や手元映像で表現する方法。
たとえば、「わかる〜」などの一言音源に“文字リアクション”を重ねるだけでも、
まるで人が反応しているような自然な温度感を作ることができます。
コツ:
- 手や机の上の動きなど「一部だけ映す」構図が効果的
- キャプションに“中の人のつぶやき”を入れるとより親近感アップ
関連記事:Instagramのプレゼント企画は“リール×メンション”が最強|UGCを横展開させる参加型キャンペーン術
第4章:AI音声リールの制作ステップと編集フロー

AI音声リールは「顔出しをせずに人を感じさせる」投稿として、
企業アカウントでも取り入れやすいフォーマットです。
ここでは、実際に制作する際のステップと編集のコツを整理します。
4.1 ステップ①:ナレーション原稿を短く“話し言葉化”する
まず重要なのは、リール用のナレーション台本を「話し言葉」で書くこと」。
原稿を記事のように作ると硬くなり、AI音声でも“機械的”に聞こえてしまいます。
改善例:
- 悪い例:「秋冬の乾燥による肌荒れには、保湿ケアが必要です。」
- 良い例:「乾燥する季節、肌がピリピリしてませんか?」
1リールにつき、15〜25秒・100文字以内が目安。
ナレーションは1テーマに絞り、「1メッセージ=1リール」にすることでテンポが保てます。
4.2 ステップ②:AI音声生成ツールを選ぶ
AI音声はツールによってトーン・滑らかさ・イントネーションが大きく異なります。
目的に応じて使い分けましょう。
| ツール | 特徴 | 向いている用途 |
|---|---|---|
| HeyGen | ナレーション+口パク動画を同時生成 | 顔なしトーク動画 |
| CapCut | 音声合成機能が手軽、字幕との同期が簡単 | 情報系・Tips動画 |
| CoeFont | 日本語の自然なイントネーションに強い | ブランドボイス制作 |
| ElevenLabs | 英語ベースだが感情表現が豊か | 海外ブランド風トーン |
AI音声を固定化することで、担当者が変わっても「声のブランド」を維持できます。
4.3 ステップ③:動画編集で“テンポ”と“間”を作る
AI音声リールで最も大切なのは、話すテンポと画の切り替えの“呼吸”を合わせること。
音声に間がないと、情報が詰まりすぎて“聞き流される”印象になります。
編集のコツ:
- 音声の一文ごとに映像を切り替える(約1〜2秒ごと)
- “間”に合わせて字幕を少し遅らせる
- BGMを-15〜-20dB程度に下げて音声を前に出す
これで、「人が本当に話しているようなリズム」が再現できます。
4.4 ステップ④:“中の人感”を出すテロップと構成の工夫
ナレーションと同じくらい重要なのが、字幕やキャプションで“感情”を補うこと。
声だけでは伝わらない“担当者っぽさ”を、文字で演出します。
例文テンプレート:
- 「これ、あるあるですよね…!」
- 「正直、私も最初わかりませんでした」
- 「中の人のこだわりポイントはここです」
リール内で1回でも“私”や“うちのチーム”などの言葉を入れると、
“話しかけてくれている”印象が強くなります。
4.5 ステップ⑤:AI音声×リールをシリーズ化する
最後に、AI音声リールをテーマ別シリーズ化するとブランドの人格が育ちます。
シリーズ例:
- 「中の人のSNS運用日記」
- 「今日のひとことリール」
- 「5秒でわかる○○のコツ」
このように継続的にAI音声を使うことで、
ユーザーが“声で覚えるブランド”へと成長していきます。
関連記事:Instagramのアルゴリズムに好かれる美容アカウントとは?|#タグより重要な投稿構成の作り方
第5章:中の人リールを“企業ブランディング”につなげる方法

AI音声や流行音源で“中の人感”を演出できるようになったら、
次のステップはそれをブランドの人格として定着させることです。
ここでは、企業アカウントで「信頼×親近感」を両立させる発信設計をまとめます。
5.1 “中の人の一貫性”がブランドの安心感を生む
フォロワーが安心して長く付き合えるアカウントには、共通する要素があります。
それは「同じトーンの人がずっと話している」ように見えること。
AI音声を統一し、テンプレート構成(導入→共感→補足→まとめ)を固定することで、
発信内容が変わっても“人格”がぶれません。
例:
- 「今日も中の人が話してる感」を出す定型フレーズを毎回入れる
- ナレーションの語尾やテンポを揃える
- 編集スタイルをテンプレ化(BGM、テロップ位置、色など)
この積み重ねが、「このブランドは人の声がする」という信頼感につながります。
5.2 “人の気配”と“ブランドの知性”を両立させる
中の人リールは、単に親しみやすいだけではもったいない。
AI音声やトーク調の解説を使って、ブランドの知識・想いを言語化する場としても活用できます。
構成のヒント:
- 「なぜこの商品を作ったのか」
- 「中の人が選んでいる理由」
- 「お客様の声に対してこう変えました」
こうしたストーリーをリールで語ることで、
“人っぽさ”と“信頼できるブランド”を同時に印象づけることができます。
5.3 AIキャラクターやマスコットとの共演で“中の人”を拡張
近年は、AI音声とキャラクターを組み合わせた「バーチャル中の人」も増えています。
担当者が顔を出さずとも、アバターやキャラが“中の人役”を担うことで、
親近感のあるブランド人格を継続的に運用できます。
応用例:
- ブランド公式キャラクターがAI音声で話す
- 担当者の代わりに“猫やぬいぐるみ”などがナレーションを担当
- 同じ声・同じテンションでシリーズ展開
これにより、「人は見えないのに、人の温度が伝わるブランド」を作ることが可能になります。
5.4 “声”の戦略をSNS運用の中心に据える
AI音声や流行音源をうまく活用できるブランドは、
今後のSNS運用で確実にアルゴリズム+共感の両面で優位に立ちます。
Instagramではすでに「視聴完了率」「音声再生率」が推奨要素に含まれており、
ユーザーが“耳で楽しむ投稿”を好む傾向が強まっています。
だからこそ、「声」を単なるBGMではなく、
“ブランドの声=ブランドの印象”として設計することが
2025年以降のInstagram戦略の鍵になります。
まとめ
Instagramのリール運用は、今や「顔を出すか出さないか」ではなく、
“人の気配をどう伝えるか”が問われる時代になっています。
AI音声や流行音源を活用すれば、
担当者が表に出られない企業でも“中の人感”を自然に演出できます。
しかも、毎回同じテンプレートや声のトーンを使うことで、
一貫した“声のブランド”を構築できるのが最大の強みです。
リールは、静止画では伝わらない「温度」と「テンポ」を届ける最適な場所。
AI音声で語りかける・流行音源で共感を作る——
そのどちらも、「中の人がそこにいるような空気」を視聴者に感じさせます。
顔出しが難しくても、“声”は企業の人格を表す新しいブランディング資産です。
2025年のInstagramでは、AI音声やトレンドBGMを活かして
“人が見える企業アカウント”をどう作るかが、運用の分岐点になっていくでしょう。
関連記事:
・https://www.active-note.jp/sns/ai-audio/?utm_source=chatgpt.com
・https://addness.co.jp/media/instagram-choicemusic/?utm_source=chatgpt.com