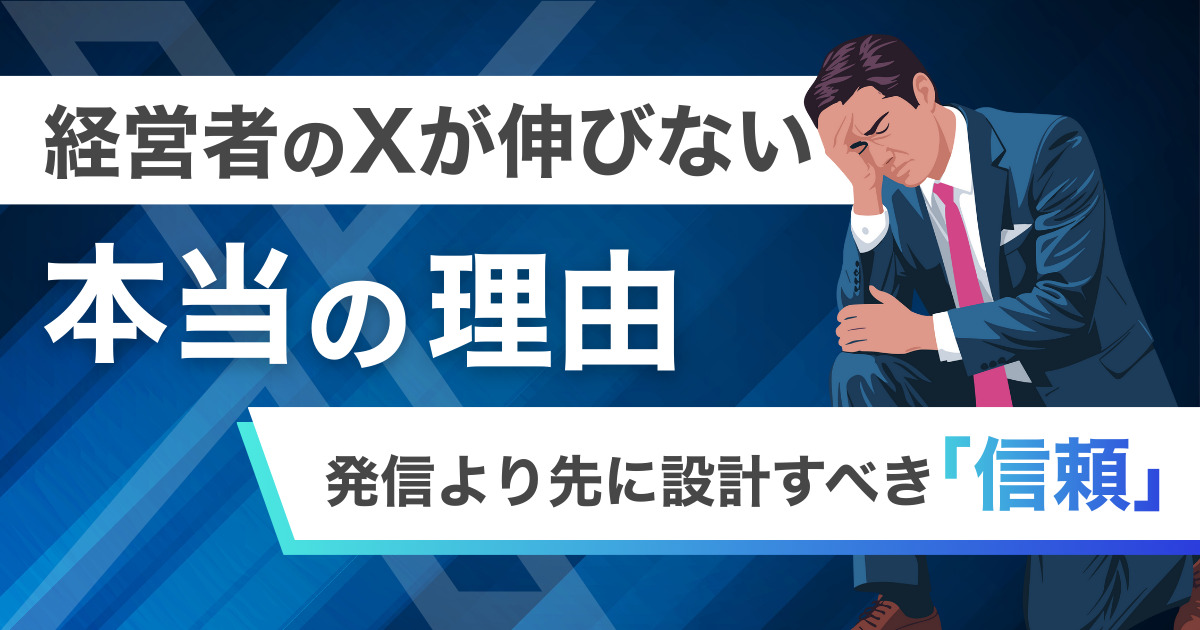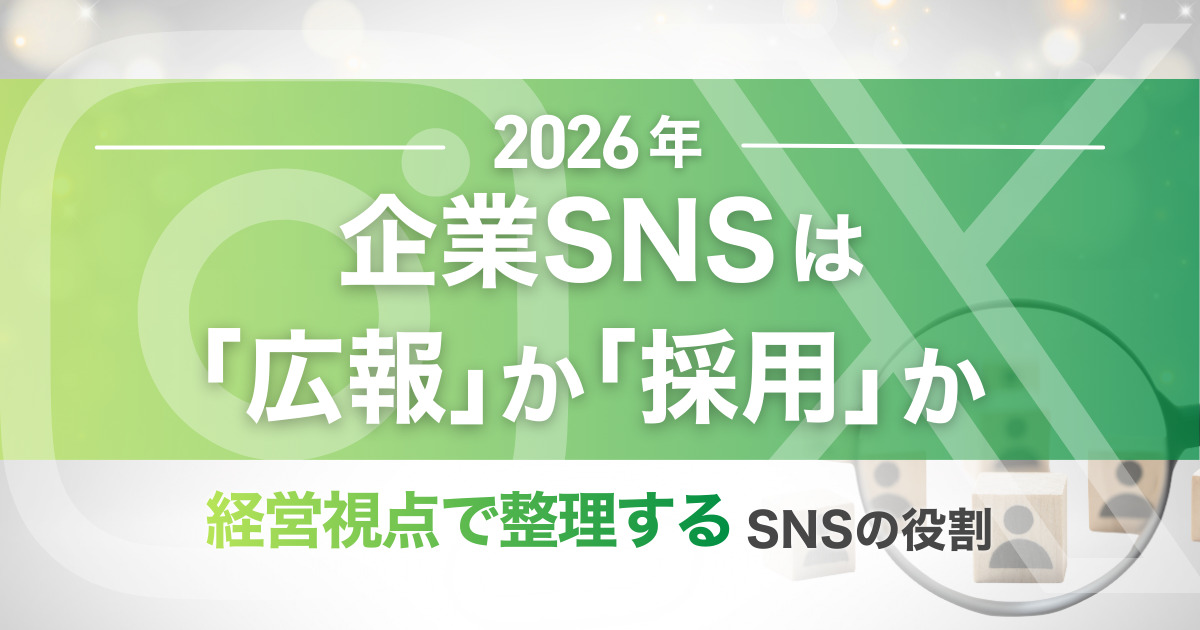2025.10.12
レシピ動画は「縦型で資産化」する ─ Before→After構成がファンを育てる理由

Instagramで成果を出すうえで、最も価値の高いアクションは「いいね」でも「コメント」でもなく、“保存”されることです。とくにレシピ・料理系アカウントにおいては、ユーザーが「あとで作りたい」「この工程を真似したい」と思った瞬間に保存が発生します。つまり、“何度も見返される形式で投稿を設計できているかどうか”が、ファン化の分かれ目になります。
その中でも近年、保存数を伸ばしているのが「Before→After型の縦型ショートレシピ」です。
たとえば「混ぜる前/混ぜた後」「焼く前/焼き上がり」など、工程と完成形の差分を一瞬で理解できる構成は、視覚的にわかりやすく、「自分にもできそう」という心理的ハードルを下げてくれます。
さらに、縦型ショートであれば、1本の動画が“タイムラインで流れる広告”ではなく、“レシピブックの1ページ”として蓄積されていくというメリットもあります。単発で終わらせるのではなく、“資産として残す視点でコンテンツを作る”ことが重要です。
本記事では、レシピ動画を「縦型×Before→After」で構成するメリットと、今すぐ使えるテンプレート・運用ポイントを整理しながら、「保存される投稿=レシピ資産」へと育てる方法を解説します。
目次
第1章:なぜ「保存」が最重要指標なのか

─ アルゴリズムとレシピ投稿の親和性
Instagramのアルゴリズムは、単に「表示後すぐに反応される投稿」ではなく、「時間をかけて再び見返される投稿」ほど価値が高いと判断します。そのため、閲覧後にユーザーのアクションが終わる「いいね」や「スクロール通過型の視聴」よりも、“あとで見返す前提の保存アクション”が優先的に評価されます。
特にレシピ・料理ジャンルは、そもそもユーザーの心理が「観賞目的」より「活用目的」に寄っています。
- ファッションや風景投稿 → 見て終わり型
- レシピ投稿 → 作る/真似する前提の再訪型
この特性により、レシピ投稿は 「保存される前提」で構成できているかどうかが成果を左右します。
逆に言えば、“美味しそうな動画”を量産しているだけでは伸びづらく、「実用的」かつ「情報がすぐ取り出せる」構造になっていなければファン化にはつながりません。
そこで重要になるのが、「Before→After型の縦型設計」です。完成形だけを見せるのではなく、
- 「この材料がこう変わる」
- 「混ぜるとこうなる」
- 「焼く前と焼き上がりの差が一瞬でわかる」
という “変化の可視化” によって、ユーザーは 「自分でも再現できる」イメージを持った瞬間に保存行動へ移行します。
レシピ投稿における成功の鍵は、味ではなく“理解”である。
その理解を最短で届ける手段こそが、縦型ショート×Before→After構成なのです。
関連記事→食品ブランドのX戦略|レシピ動画と調理Tipsでファンを育てる方法
第2章:レシピ動画は「縦型」で残すべき理由

─ フィードとリールの役割が明確に分かれてきた
Instagramでは、投稿フォーマットごとに“見られ方”と“残り方”が異なる構造になっています。特に近年は、以下のような使い分けが定着しつつあります。
| フォーマット | 主な役割 | ユーザー行動 |
|---|---|---|
| リール | 新規接触・拡散 | スクロールして視聴/一瞬で印象づける |
| フィード(縦型動画) | ストック・保存 | あとから見返す/“レシピ帳”として使う |
レシピ投稿の場合、最初の入口になるのはリールですが、ファン化や固定読者化の決め手になるのはフィードの“残り方”です。
そこで重要なのが、“縦型で統一する”という設計です。
なぜ「縦型統一」が資産化に効くのか?
- スマホ閲覧の圧倒的大多数が“縦持ち”固定
- 横型だと保存後に「見づらくて開かれない」ケースが多い
- 同じ構図で並ぶことで「レシピ帳のような一覧性」が生まれる
- アカウント印象が揃い、“世界観の統一”がブランド化につながる
つまり、単に“見せる”のではなく、“残すために縦で作る”という視点が必要です。
Before→After構成は「縦型」と相性がいい
縦型の中に
- 1カット目|Before(材料・工程途中)
- 2カット目|After(完成形)
という流れを入れるだけで、ストーリー性と理解の早さが両立します。
動画尺が長くなくても成立するため、
- 1本8〜12秒でも説明が完結
- 途中離脱が減り、最後まで見られる=リーチに有利
- 保存時の「情報の取り出しやすさ」も高い
というメリットがあります。
「見せるため」ではなく「残すため」に縦型で投稿する。
その設計の中核にあるのがBefore→After構成である。
関連記事→Instagramリール広告はなぜ伸びている?成果を出すポイントをプロが解説
第3章:Before→Afterレシピ投稿の基本テンプレート

─ 8〜15秒で完結させる構成
レシピ動画を「保存されるフォーマット」に落とし込む際、重要なのは“説明しすぎないこと”です。長尺で丁寧に解説するよりも、“変化を早く見せる構成”のほうが保存率は高くなります。
ここでは、8〜15秒の縦型ショートレシピで使える基本テンプレートを紹介します。
Before→Afterレシピ構成テンプレート(8〜15秒)
| カット | 内容 | 役割 |
|---|---|---|
| ① Beforeカット(0〜2秒) | 材料/生の状態/混ぜる前/焼く前など | 「これがどう変わる?」という期待を作る |
| ② 変化カット(3〜6秒) | 調理途中・混ぜ・焼き・流し込むなど動きのある工程 | 編集テンポで“プロセスの理解”を与える |
| ③ Afterカット(7〜10秒) | 完成形/盛り付け/断面/湯気など | 一瞬で「作ってみたい」を引き起こす |
| ④ テキストまとめ(任意) | 材料一覧 or 手順簡易メモ | 保存向きの「情報引き出しポイント」 |
テロップは“解説”ではなく“誘導型”にする
レシピ動画では 「作り方を全部説明する」よりも「見れば理解できる構成」にしたほうが保存されます。
そのため、テロップは以下のように“主観コメント寄り”に振ったほうが効果的です。
| NG例(説明型) | OK例(誘導型) |
|---|---|
| 「卵と砂糖を混ぜます」 | 「混ぜるだけでこんなにフワフワ…!」 |
| 「電子レンジで3分温めます」 | 「3分待つだけで完成!」 |
| 「タレを上からかけます」 | 「追いタレで優勝」 |
情報の羅列ではなく、“感情を引き出し保存させるテロップ”。
BGMは「静かな環境」より「生活音寄り」のほうが良い
料理系は意外にも、ASMR要素(焼き音・混ぜ音)や生活BGMのほうが没入感が高くなります。
「音=食欲スイッチ」になるため、BGMも“清潔感+生活音”を意識すると効果的です。
第4章:アカウント全体を“レシピ帳”として設計する
── 単発投稿ではなく「ストック型コンテンツ」の発想へ
レシピ動画を投稿する際、「1本ごとの反応」だけを見て一喜一憂する運用では、ファン化やフォロワー定着にはつながりにくくなっています。なぜなら、ユーザーは投稿単体ではなく、アカウント全体の“蓄積の質”を見て判断するようになっているからです。
ここで意識すべき視点は、「アカウント=レシピ帳として成立しているか?」という設計です。
レシピ帳型アカウントの条件
- 縦型フォーマットで統一されている
- Before→After構造が一貫しており、一覧で見ても“変化の連続”が伝わる
- 料理ジャンルが明確(朝食/お弁当/おつまみ/時短など)
- 似た構成の動画が横に並ぶことで“テンプレ化による信頼感”が生まれる
このように、投稿は単発の“作品”ではなく、ユーザーのスマホ内にストックされる“レシピ資産”として積み上がっていきます。
だからこそ、アルゴリズム対策の前に 「人にとって使いやすい形で並んでいるか」 が重要です。
ストック視点で運用するためのチェックリスト
- 「この投稿が“あとで見返す価値”を持っているか?」
- 「サムネイルだけで“何の料理か・どんな変化が見られるか”が判断できるか?」
- 「保存して並べたときに“自分だけのレシピフォルダ”として成立するか?」
もし “見て終わるだけの流し見コンテンツ” になっているなら、方向転換のサインです。
これからは “消費される投稿”ではなく、“保存される投稿”を積み上げる運用が主流になります。
関連記事→2025年版|Instagramストーリーズ運用の最新戦略4選
第5章:保存率を高める撮影・編集テクニック

「Before→Afterの構成にすれば自然と保存される」── というわけではありません。視聴者が“保存しておきたい”と思う瞬間を意図して演出することが重要です。
ここでは、保存率を高めるための具体的な撮影・編集ポイントを整理します。
① カメラアングルは“揃える”ことで見やすくなる
レシピ動画では 「工程ごとにアングルを変えすぎないこと」がポイントです。
- Before(材料・生の状態)
- After(完成形・盛り付け)
この 2つのカットの画角を揃えておくことで、“変化”が視覚的に理解しやすくなります。
逆に、Beforeが俯瞰でAfterが横アングルだった場合、視聴者は「何がどう変わったのか」を頭の中で補完する必要が生じ、理解コストが上がって保存行動が遠のきます。
② 「調理を見せる動画」ではなく「変化を見せる動画」にする
料理動画というと、つい調理の“過程”を見せることに集中しがちですが、保存される動画はむしろ
「変化する瞬間だけを強調して見せている動画」
です。
例えば
- とろけるチーズが溶ける瞬間だけ見せる
- プリンを揺らして弾力を見せる
- ソースをかけた瞬間に全部切り替わる
といった “視覚的な快感ポイント”を主役に据える構成にすることで、完成形への期待が高まり、「あとで見返したい」につながります。
③ テロップは“説明型”ではなく“感情誘導型”にする
レシピ動画のテロップは 「文字で工程を説明する」のではなく、「最後まで見たくなる一言にする」ほうが保存されます。
| 説明型テロップ | 感情誘導型テロップ |
|---|---|
| 「ソースを上からかけます」 | 「追いソースで仕上げのご褒美」 |
| 「焼き色がついたら完成です」 | 「こんがり焼けた瞬間が最高」 |
| 「冷蔵庫で1時間冷やして固めます」 | 「待つだけで神デザートになる」 |
視聴者は“作り方が正しいから保存する”のではなく、“気持ちが動いた瞬間に保存する”という前提を忘れないことが大切です。
第6章:投稿を「シリーズ化」してファンを定着させる

── 単発視聴から“継続フォロー”へつなげる設計
保存される投稿を作れるようになっても、「またこの人の動画を見たい」と思われなければフォローにはつながりません。
そこで重要になるのが、レシピ動画を“シリーズ化”して届ける設計です。
シリーズ化の基本は「テーマ・タイトル・構図の固定」
ユーザーは「知らない投稿者」には興味を持ちにくい一方、「見覚えのある型」には安心感を覚える傾向があります。そこで運用側は以下を揃えて、“このアカウントの投稿だ”と一瞬で識別できる状態を作ることが重要です。
| 要素 | 固定するポイント | 効果 |
|---|---|---|
| テーマ | 「朝食レシピ」「1食100円」「5分で作れる」など | 軸が明確になると“このアカウント=◯◯の人”と認識される |
| タイトルフォーマット | 《◯◯するまで◯秒》《◯◯するだけで完成》など | 並んだときに「シリーズ一覧」として成立する |
| サムネイル構図 | 文字位置・色・背景などを統一 | スワイプ中でも“ブランド力”が出る |
この「シリーズ化」は、単なる投稿の統一ではなく、“次も見たくなる心理” を誘発する導線設計です。
シリーズ化が生む「次の保存」
- 1本目を保存 → ユーザーの保存フォルダに入る
- 同じシリーズが複数本並んでいると、ユーザー側が「まとめて保存しておこう」と判断する
- さらに「この人の投稿を逃したくない」と感じた瞬間にフォローへつながる
つまり、保存率の高い投稿を“連続して並べること”がフォロワー成長の鍵になります。
第7章:シリーズ運用に合わせたハッシュタグとキャプション設計

── “検索対策”ではなく“自分の棚を作る”という発想
レシピ系アカウントでは、ハッシュタグを「見つけてもらうための導線」ではなく、“ユーザーが後から整理するための棚”として機能させることが重要です。
ハッシュタグは“検索されなくても役に立つ”
一般的には
「タグ付けすれば検索される → 新規リーチが増える」
と考えがちですが、実際のレシピ系アカウントでは、保存後にハッシュタグ経由で再訪するユーザーのほうが多い傾向があります。
そのため、
- #朝ごはんレシピ
- #5分で作れるシリーズ
- #〜の作り置き弁当(※自作シリーズタグ)
といった形で “自分でシリーズ用タグを作り、そのタグ内に投稿を並べていく” という設計が最も有効です。
キャプションは「説明」ではなく「整理用メモ」として使う
キャプションも同様に、料理工程をすべて書く必要はありません。
むしろ以下のような “保存後に役立つ最小構成” に絞り込むほうが、ユーザーにとって利用価値が高くなります。
【材料メモ】
・◯◯:大さじ2
・◯◯:ひとつまみ
【ポイント】
・混ぜすぎないこと
・最後に追い◯◯するとおいしい
このように 「作るときに必要な情報だけを残す」 スタイルにすることで、キャプション自体が“保存の価値を裏付ける存在”になります。
まとめ ─ レシピ投稿は「流すもの」から「残すもの」へ
レシピ動画は、ただ見てもらうだけの“消費型コンテンツ”ではありません。
正しい構成と設計さえ整えば、ユーザーのスマホの中で何度も開かれ続ける“資産”になります。
その鍵となるのが、
- 縦型で統一すること
- Before→Afterの“変化”を中心に見せること
- シリーズとして並べること
という3つの視点です。
単発でバズる動画を追いかけるのではなく、静かに積み重ねていくことで“レシピ帳としてのアカウント価値”が育っていきます。
これからのレシピ投稿は、「どれだけ見られたか」ではなく「どれだけ保存されたか」で語る時代です。
── レシピは流さず、残す側に回ろう。
・関連記事