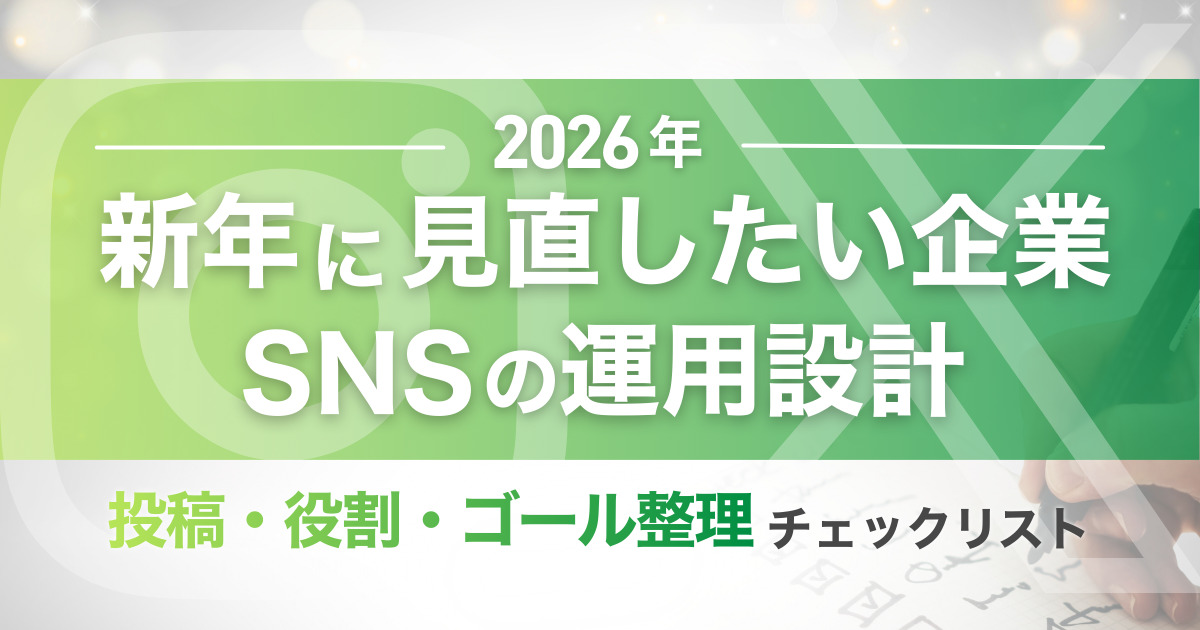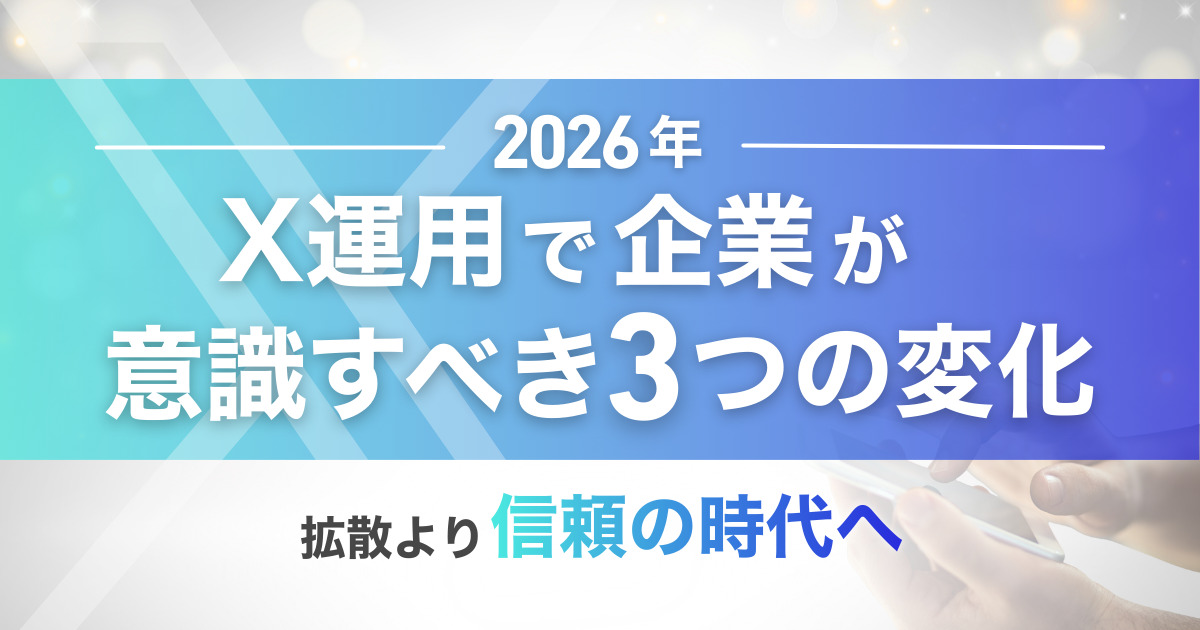2025.8.29
業界特化型X運用術|BtoB企業でも成果を出す教育・医療・製造業の成功事例
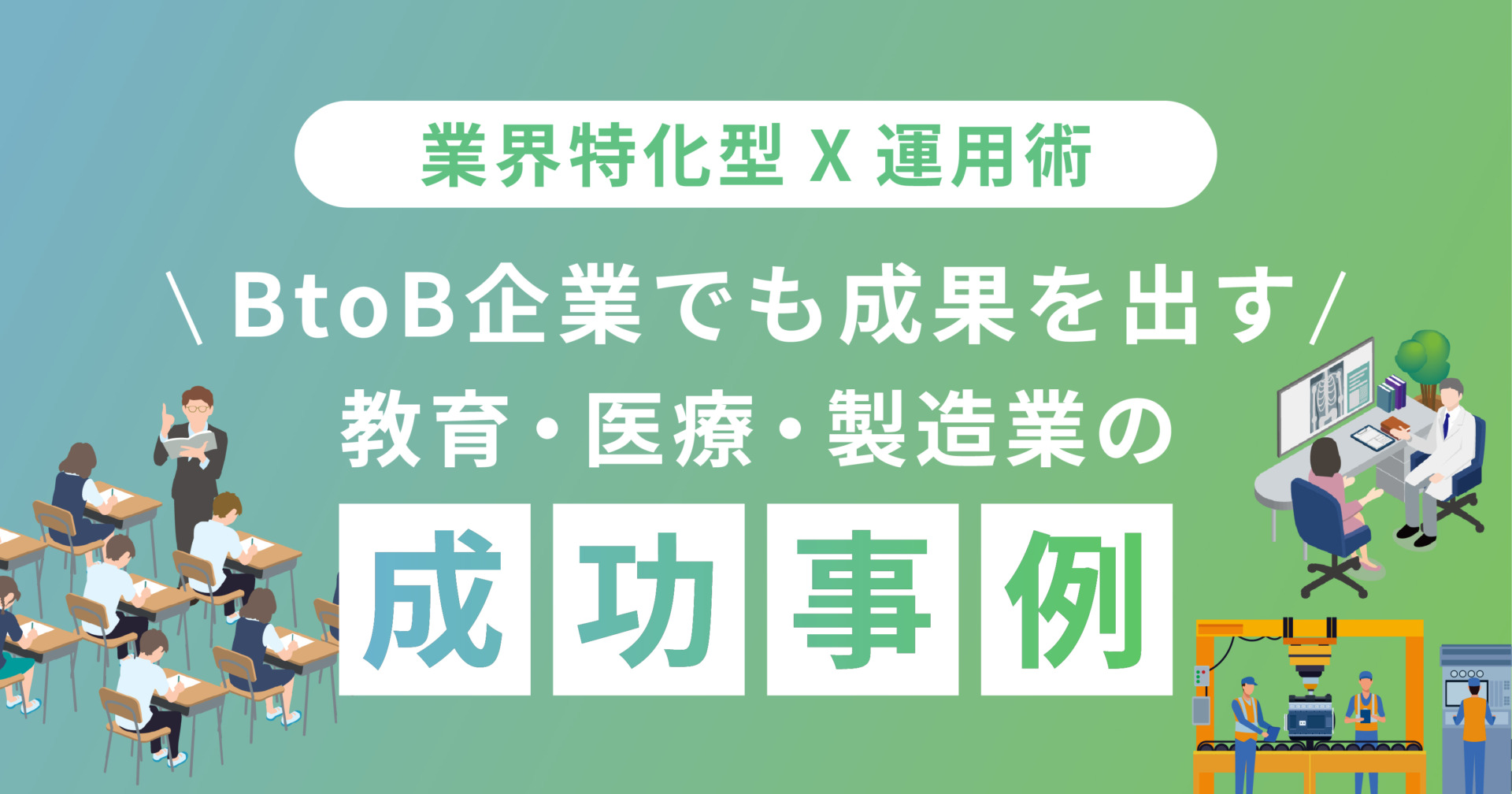
BtoB企業にとって、X(旧Twitter)は「BtoC向けのSNS」「お堅い業界には合わない」と思われがちです。特に教育・医療・製造といった分野では、専門性が強く、カジュアルなSNSで成果を出せるのかと疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
しかし実際には、これらの業界でもXを活用して成果を上げている企業は存在します。ポイントは「フォロワー数やバズ」を追いかけるのではなく、信頼性・専門性を可視化し、業界の中で影響力を築くことにあります。
本記事では、教育・医療・製造といったBtoB業界にフォーカスし、Xをどう運用すれば成果につながるのかを具体的な事例とともに紹介します。これまで「自社には向かない」と感じていた方にこそ、ヒントになる内容です。
目次
1. BtoB企業がXを活用する意義

BtoB企業の多くは「Xをやっても取引先は見ていないのでは?」と感じがちです。しかし実際には、意思決定者や業界関係者が情報収集のためにXを活用しているケースは少なくありません。特に次のような点で、BtoB企業にとって大きなメリットがあります。
速報性と業界ニュースの共有
Xはニュース性のある話題が拡散されやすい特徴があります。新製品リリースや業界動向、研究発表などをいち早く発信することで、業界内での認知を広げ、存在感を高めることができます。
専門性の可視化と信頼構築
BtoBにおける競争優位は「技術力」「専門性」「信頼性」にあります。Xで継続的に専門的な知見やノウハウを発信すれば、フォロワー数が少なくても「この会社は業界をリードしている」という印象を築けます。これは受注や提携のきっかけになり得ます。
人脈形成とコミュニティ参加
Xは双方向のコミュニケーションが前提のSNSです。業界団体、研究者、企業の担当者と気軽につながることができ、展示会やセミナーとは異なるオンライン上の「人脈づくり」に役立ちます。特に採用や共同研究を見据えた動きでは、この関係構築が強力な武器になります。
2. 教育業界の事例と運用術

教育業界は、一見するとXでの発信が難しそうに思えます。実際、「学生や保護者はInstagramやTikTokの方が多いのでは?」と感じる方もいるでしょう。しかし、教育業界におけるX活用には、他のSNSにはない強みがあります。
学校・教育機関による発信
大学や専門学校、各種スクールでは、オープンキャンパスやイベントの告知をXで行うケースが増えています。速報性のある発信によって「今週末の体験授業」「説明会の申し込み〆切」などを即座に届けられるのは大きな利点です。また、卒業生や在校生とのコミュニケーションの場としてもXは機能します。
研修・教育サービス企業の活用
BtoB向けの研修サービスや人材教育の会社では、ノウハウや業界知識を発信することで専門性を示すことができます。例えば「部下の育成に使える1on1のコツ」「新入社員研修のトレンド」といった内容は、企業担当者が“つい保存したくなる情報”です。フォロワー数が少なくても、意思決定者に直接届く可能性があるのがXの強みです。
教育業界ならではのポイント
- 情報の鮮度:入試、説明会、教育制度の変更など、最新情報を求める人に刺さりやすい。
- 専門知識の発信:教育関係者同士のネットワークづくりにもつながる。
- 信頼の可視化:継続発信により「教育に真剣に取り組んでいる企業」というブランド構築が可能。
教育業界においてXは、「学生募集」だけでなく、「業界内での存在感を高めるプラットフォーム」として機能するのです。
3. 医療業界の事例と運用術
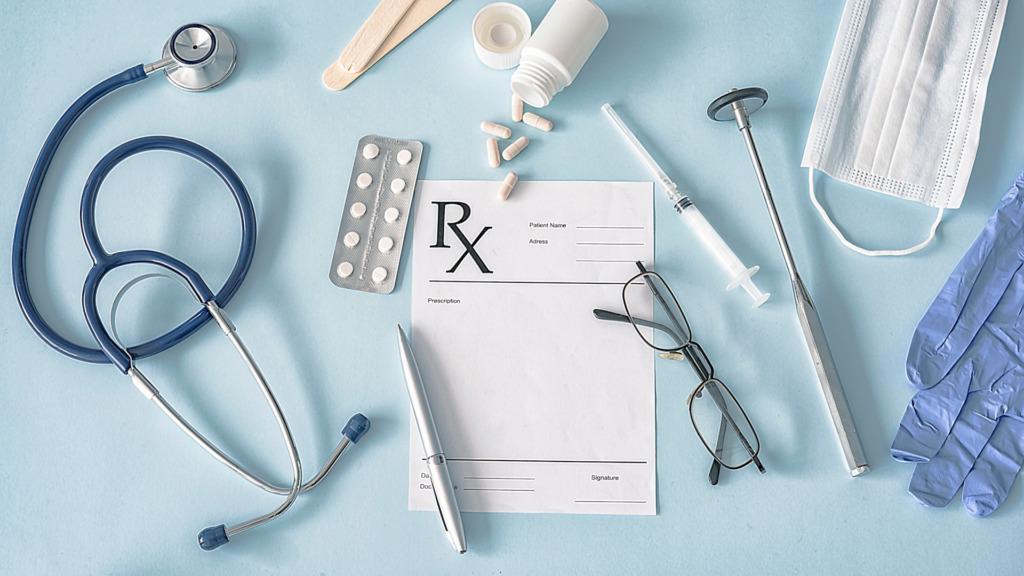
医療業界は規制や情報の正確性が求められるため、SNS運用は難しいと思われがちです。しかし、正しく活用すれば信頼性を高め、患者や業界関係者との関係構築に役立つプラットフォームとなります。
病院・クリニックの活用例
地域の病院やクリニックでは、診療時間の変更や休診日のお知らせといった「生活に直結する情報」をXで発信するケースが多くあります。リアルタイム性が強いXは、地域住民にとって身近な情報源として機能します。
さらに、健康に関する豆知識や予防策を短文で発信することで、地域住民の信頼を獲得しやすくなります。
製薬会社や医療機器メーカーの活用
BtoB寄りの製薬会社や医療機器メーカーでは、展示会・学会の発表内容や研究成果をXで速報的に発信するケースが増えています。これにより業界関係者や医療従事者の関心を集め、「専門性の高い情報を発信する企業」というブランドイメージを確立できます。
採用広報としての活用
医療業界では人材不足が課題となっており、採用広報にもXは有効です。
現場のスタッフの声や働く環境を伝えるポストは、応募を検討する人にとって安心材料になります。SNSを通じて「信頼できる職場」という印象を与えることが、応募数増加につながる事例も出ています。
採用関連記事→「Instagram採用|実践から成果へ!応募につながる運用テクニック」「“就活=SNS”の時代到来?企業が今すぐ取り組むべきSNS採用」
医療業界ならではのポイント
- 正確性と透明性が最優先:誤情報や誇張を避け、事実ベースの発信を徹底。
- 学会・研究連動が強い:業界関係者に向けた専門発信が有効。
- 採用広報の強化:求職者に現場の雰囲気を伝え、安心感を与える。
医療業界におけるX運用は「バズ狙い」ではなく、信頼性の可視化と関係構築にフォーカスすることが成果につながる鍵となります。
4. 製造業の事例と運用術

製造業は「現場が中心でSNS発信は難しい」「製品は一般ユーザーには馴染みがない」と考えられがちです。しかし実際には、技術力を可視化し、取引先や人材との接点をつくる場としてXを活用する事例が増えています。
中小製造業の活用例
ある町工場では、自社の加工技術を動画や写真で紹介し、同業者や取引先から注目を集めています。「こういう加工ができます」という発信は検索ではなかなか見つけてもらえませんが、Xで継続的に共有することで、思わぬ新規取引につながるケースがあります。
大手メーカーの情報発信
自動車や機械メーカーでは、展示会や新製品発表をXで速報的に発信するのが一般的になっています。展示会のリアルタイム実況や社員レポートを通じて、業界関係者との交流を深めることができ、オンライン上でも「展示会の延長線」を作り出せるのが特徴です。
採用や若手人材へのアプローチ
製造業は人材確保の面でも課題が多い業界です。Xで日常の現場風景や社員インタビューを発信することで、求職者に「働くイメージ」を伝えやすくなります。実際に「現場スタッフの声を見て応募した」という採用事例も出ています。
製造業ならではのポイント
- 技術力を見える化:加工技術や製品特長をわかりやすく発信
- 展示会や発表と連動:リアルイベントとSNSを掛け合わせる
- 採用広報への活用:働く現場を“リアル”に伝え、若手人材を惹きつける
製造業におけるX活用は、一般消費者向けではなく業界内や採用市場での影響力を築く手段として強みを発揮します。
5. 業界を超えて共通するX運用のポイント

教育・医療・製造業といったBtoB業界にはそれぞれ独自の事情がありますが、成果を出しているアカウントには共通する運用術があります。ここでは3つの重要ポイントを整理します。
① バズより信頼を重視する
BtoB企業がXを活用する目的は「拡散」ではなく「信頼の蓄積」です。派手なバズ投稿よりも、専門知識や実務に役立つ情報を地道に発信する姿勢が評価されます。フォロワー数が少なくても、業界の意思決定者に届けば十分な価値があります。
② 専門性を継続的に“見える化”する
継続発信が信頼のベースです。毎日のように発信する必要はありませんが、定期的な発信を積み重ねることで「業界にコミットしている会社」という認識を得られます。専門的な話題をシンプルに伝える工夫も欠かせません。
③ 双方向の発信でエンゲージメントを育てる
Xは「一方的な宣伝」だけでは成果につながりません。リプライや引用ポストで業界関係者と対話を重ねることで、業界コミュニティに自然に入り込むことが可能です。小さなやり取りの積み重ねが、信頼関係と将来のビジネスにつながります。
教育・医療・製造といった異なる業界で成果が出ているのは、結局のところこの共通ポイントをしっかり押さえているからです。
まとめ|BtoBだからこそX運用が効く理由
「XはBtoBには向かない」と思われがちな教育・医療・製造業でも、実際には成果を出している企業が増えています。共通するポイントは、バズを狙うのではなく、専門性と信頼性を継続的に発信すること。その積み重ねが業界内での認知や人脈形成、そして採用や新規取引へと結びついていきます。
BtoBにおけるX運用は、一般消費者に広く届けるのではなく、狭くても深く、正しく届くことが価値になります。教育業界では学生や保護者、医療業界では患者や業界関係者、製造業では取引先や人材候補。届けたい相手に信頼を持って接点を作れるのがXの強みです。
とはいえ、継続的な情報発信や業界特有のルールに配慮した運用は簡単ではありません。だからこそ、SNS運用代行のプロがサポートに入ることで、業界特化のノウハウと仕組み化された発信設計を提供できます。
「自社の業界にはXは合わないのでは?」と感じている企業こそ、一度視点を変えてみてください。XはBtoBだからこそ活かせる場面が必ずあります。